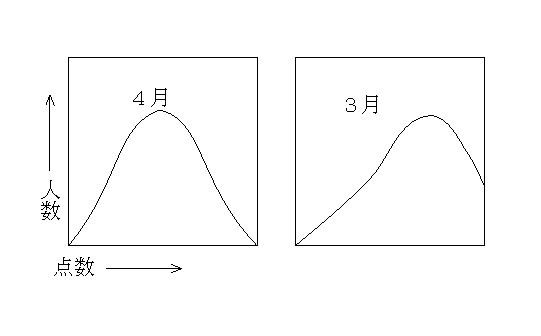教育 平成18年後半
愛知・大河内清輝くんいじめ自殺事件1994年について思う
いじめという言葉を正しく使った方がよいと思います。大河内君の場合は、いじめの部分がないわけではないと思いますが、基本的には刑法に触れる行為で「いじめではなく刑法犯罪」と言うべきだと思います。
オワリナキアクム愛知・大河内清輝くんいじめ自殺事件
このホームページを事実とすれば、 器物破損罪、名誉毀損罪、強制わいせつ罪、器物破損罪、窃盗罪、暴行罪、傷害罪、恐喝罪、強要罪、これらの言葉の方が似合うと思います。このような場合は、いじめ扱いではなく、刑法犯として、警察の少年科ではじめから、扱うべきではなかったのでしょうか。このような陰惨な事件を防ぐには、まず、「どのような場合が刑法に触れるのか、警察などが広報し、警察署の少年課の窓口で相談できるような状況を作ることが大切だと思います。」新聞やテレビのタイトルも「いじめ」ではなく、「集団暴行・恐喝グループ」のような取り扱いであるべきだと思います。
個人的には、「いじめ」は、「弱い者を苦しめる」とし、しかも「刑法犯にならない範囲」としたいです。そして、純粋な「いじめ」については、学校・家庭・児童相談所などで解決することを基本とし、刑法に触れる「いじめ」については、純粋に犯罪として扱い、児童相談所、警察、家庭裁判所を通して解決していくことが基本だと思います。
本件の処分は、「1995年2月10日、愛知県警と西尾署は男子生徒11人のうち4人を恐喝容疑で書類送検した。4月4日、3人を初等少年院(内2人は長期、1人は短期)、1人を教護院に送致。少年院送致となった1人は抗告したが、棄却された。」とのことです。本日が大河内君の13回忌だそうです。
関連: ウィキペディアで「自殺」で検索してみてください。WHO(世界保健機構)の自殺報道ガイドライン の抜粋が記載されています。
WHOガイドライン抜粋
1.写真や遺書を公表しない
2.自殺手段の詳細を報道しない
3.自殺の理由を単純化しない
4.自殺の美化やセンセーショナルな報道は避ける
詳しくは 自殺対策支援センター
自殺対策支援センター 「自殺を予防する自殺事例報道のあり方について」のWHO勧告(2000年)
H18.11.27
いじめ
子供の世界にもいじめがありますが、大人の社会の方がもっと陰湿ないじめがあります。だからこそ、毎年交通事故の死亡者よりもはるかに多い3万人も自殺しています。マスコミは、子供のいじめを徹底的に問題にしても、大人のいじめをあまり問題にしないのはどうしてでしょうか。そして、学校教育が終わったとたん社会のいじめにさらされます。このギャップは何でしょうか。子供達が社会に出て、突然いじめの嵐にさらされれば、何が起こるでしょうか。耐えられる子供もいればそうでない子供います。耐えられなければ、その職業をやめたり(フリーターへの道)、閉じこもったり、自殺したりすることでしょう。
それでは、いじめは完全になくなるものでしょうか。「人をけ落として、出世する。・・・いじめ?」「人をけ落として、高校や大学に入学する・・・いじめ?」、「妻が夫に出世することを口うるさく言う。」「子供に○○に入学するように口うるさく言う。」「子供が言うことを聞かなかったら、口をきかない」「自分に対して少しでも嫌なことをされたら、それをした友達に口をきかない。」「親会社がここまで値段を下げろと言う・・・下げなければ取引をしないと言う。親会社よりもずっと安い給料なのに」「バスケットボール部で下手だから、パスを回さない。あるいは、わざとパスを回して笑う。」、「運送会社で○○時までに荷物を届けろと言う・・・そして、高速料金は払わない。高速道路を使わないと間に合わない。普通の道路ではスピード違反や信号無視をせざるを得ない。」「オーナードライバー・・・運送会社が運転手からピンハネをする。」「野党が与党に同じ質問をしつこくする。」「O157を貝割れ大根にドレッシングをつけて増殖させる実験をする・・・ハンバーガーにO157をつければ確実に増殖する・・・O157を貝割れ大根につけても増殖はしない」、犯罪といじめの狭間にあるグレーゾーンの出来事は数多くあります。いじめを「相手が嫌だと思えばいじめ」だとすれば、世の中はいじめであふれていることになります。しかし、これらのことが、完全になくなるとはとても信じられません。そして、学校は社会の縮図なのです。社会で起こっていることは、必ず学校でも起こるのです。なぜなら、そういう大人を見て育っているからです。社会で行われているいじめの縮小版が学校で起こるのです。そして、たまに、大人顔負けの犯罪も行われるのです。学校と社会を分離することは不可能なのです。学校と社会を分離できない以上、学校のいじめをなくすためには社会のいじめもなくさなくてはなりません。学校のいじめがなくなれば、社会のいじめがなくなると考えるのは、絵空事に過ぎません。親を通して、地域を通して、絶えず子供と社会は関わっているからです。いじめを減らすことを同時に進行させないといけないのです。
H18.11.19
自殺の報道について
最近、自殺の報道が目立ちます。何のために自殺の報道をするのでしょうか。新聞やテレビの視聴率を上げるためでしょうか。それとも、自殺を少しでも減らそうと思っているのでしょうか。もし、報道機関に聞けば、きっと、「報道することによって、自殺を防止したい。」というようなことを言うと思います。しかし、その防止のプロセスが明らかでないと、逆に自殺を誘発する場合だってあります。自殺を報道することによって、自殺のきっかけを作ってしまっては、報道のモラルに反します。従って、自殺の報道は誰が悪いということを追求する報道ではなく、どのようにしたら、自殺が防止できるかということに主眼を置いて報道すべきなのです。自殺を報道した時点で、その報道者自身も関係者になっていることを自覚する必要があります。報道者が外部の者であるような振る舞いをしていることは、全くの偽善だと思います。「報道した時点、もっと言えば、取材をした時点でその事件及び、今後の事件の関係者となる。」と考えるべきだと思います。
最低限、「生きてこそ、問題の解決につながる。」、「自分一人の命ではない。」「道はまだ他にもある。例えば・・・・。」とか、「悩み事の相談窓口の電話番号、メールのアドレス」を記事の末尾につけるなど、読者に対する配慮が必要だと思います配慮が必要です。最低限のことは行って欲しいと思います。報道すればよしでは、責任感がないと思います。責任の持てない報道はして欲しくないですね。
H18.11.3
「福岡県筑前町三輪中学校 二年生男子生徒 いじめを苦に自殺」報道について思う。
「偽善者にもなれない偽善者」という言葉がなぜ流行るのでしょうか。テレビ番組のお笑いでも見るように・・・。それをきっかけにいじめがひどくなったそうである。確かに1年の担任は問題であったようですが、それが、2年になってからも続くと言うことは別にも問題があるということでしょう。
自分は自分という考えが中学校ではできていないといけないはずなのに、はやり言葉のように、相手の気持ちを考えずに言ってしまう。言葉を覚えたての低学年の子供が、やたらにその言葉を使いたがるのと同様な雰囲気を感じてしまいます。自分は自分という考えの子供が多ければ、「可愛そうだから、そんなこと言うなよ。」という言葉が、何人もの口から聞こえそうなものなのに・・・。そう言えば、ついこの間まで高校生のルーズソックスが流行っていましたが、ルーズソックスが流行っていると報道されると、ルーズソックスでなければならないと思うのか、多くの高校生達がそうしていました。ルーズソックスが自分に似合うかどうか、学校の決まりを破ってまでしないといけないかどうかを自分の頭で判断しないといけないのに、流されるままに従っていました。価値判断の基準が自分の中にできてこなければならないのに、価値判断の基準を外部に求めているようです。テレビは、テレビ、自分はそれに対してどう感じて、どう行動するかを考えられるようにならなくてはいけないのです。
自殺のテレビ報道があると、その報道をきっかけとして次の自殺が起こる場合があります。いじめ問題・自殺問題は、「本人、加害者、学校、家庭、地域、報道」など全てが関わっています。まず、加害者の反省が問題となるはずです。その次が家庭・学校ということになります。特に、いじめの自殺を報道する場合は、1面に1回目の報道を載せたら、よく調べた上で、後日1面に、加害者や学校・家庭など全て関わった人たちの反省の言葉が必要でしょう。報道の仕方も含めてね。2面だったら、2面にね。それができないのならば、自殺やいじめの報道をするべきではありません。自殺やいじめをなくそうと思って報道するのならば、視聴率を上げて儲けることだけを考えているのならば、今のままでよいでしょう。
もう1つ問題になることがあります。いじめた側の名前が公表されるということになると社会的に非常に不利な立場になることです。報道機関が社会的制裁をするとも言えます。教師がいじめた立場でも、子供がいじめた立場でも、その程度によって責任は違います。それ相応の処罰は受けるべきだと思います。しかし、報道機関が処罰して良いことにはなりません。
それでは、報道されることによって事件は解決されるのでしょうか。逆に報道されてしまうことによって、社会的制裁を恐れるあまり、事実が隠蔽される可能性が高く、事実が隠蔽されることによって、真相が究明されず、解決にならない可能性が高くなってしまいます。報道のマイナス面を報道側は真剣に受け取る必要があります。
「いじめによる物理的な殺人=殺人」、「いじめによる自殺」、「物理的ないじめ」、「精神的ないじめ」、それぞれ異なるものです。従って、事件の性質が不明確である間、そして、どうしても報道の必要な場合は、校名などすべて匿名にすることが基本だと思います。そういった慎重さが報道機関には必要です。それが報道のモラルです。
もっとも、校内においては、徹底的に究明する必要があります。そのいじめの種類に応じて、それぞれのレベルで究明されるべきだと思います。教師、子供、保護者など、何よりも関係者による解決が必要なのです。刑事事件の場合は、当然警察が関わって解決することになるでしょう。
外部の野次馬が事件の解決や今後の事件の防止をするとはとても思えません。なによりも、報道機関の自重がいじめ問題には必要なのです。
また、いじめられた側にしても報道されることを好まない場合も、好む場合もあると思います。そっとして欲しいことだってあるのです。報道機関はその意思を尊重すべきではないでしょうか。
モラルのない報道機関のために事件がうまく解決できないのであれば、その報道機関は必要ないと思います。報道の自由だって必要ないのだと思います。社会に害悪をばらまくのですから。
事件を解決するための報道機関であることを切に望みます。例えば、事件の関係者の迷惑のかからない形で、「どのように解決していったか」を報道するというように。
H18.10.29
H18.10.8
学力テスト
全国一斉の学力テストは、公教育の成果という面で必要なのかも知れません。ただし、正しく学力テストが行われるにはいくつかの条件が必要だと思います。
イギリスのように、学校とは直接の関係のない者が、全国共通のテストを行い。成績を出すのならば、ある程度正確な学力が判定できるでしょう。しかし、お金をかけないことばかり気にして、担任にテストを行わせ、その平均点がその担任の評価につながるかも知れないとすれば、事前にテスト問題を子供に漏らして、平均点を簡単に上げることにつながり兼ねないのですね。そのようなことが行われれば、、正確な学力は判定できないと言うことになってしまうのです。
次に、学級ごとに学力テストの平均を出して、それを問題にした場合のことを考えてみましょう。
登校拒否あるいは、知能が低くて養護学校に入らないといけない子供が普通学級に入級してきた場合、学力テストの平均点が下がってしまいます。学校の平均点も下がってしまいます。次の例を考えてみます。
全国平均が80点のテストがあり、40人のクラスがあったとしましょう。
次のような子供がいたとします。
・養護学校に入るべき知能の子供が1人いて0点。
・登校拒否の子供が1人いて30点。
・他の38人は全国平均の能力がある。
すると平均は次のように計算できます。
(0+30+80×38)÷40=76.75
となります。きっと、その学校の中で学力の低いクラスということになってしまいます。そういう子供を受け入れると、学力を伸ばすことのできない担任だということになります。
すると、上からの評価を気にする担任はどう考えるでしょうか。「あの2人の子供がいるから、自分は過小評価されている」「二度とあんな子供をいけ入れるものか。」
つまり、学力テストの平均がどうのこうのと細かいことを言い出すと、障害や問題のある子供を受け入れることが難しくなってしまうのです。そんなことでよいのでしょうか。だから、学力テストの平均で教員を評価してはいけないのです。公平に行われた学力テストで、「4月の平均が○点で3月の平均が上がったから、下がったから」ということでないといけないのです。しかし、ここで問題があります。「4月の学力テストと3月の学力テストの全国平均が同じ点数か、もっと言えば同じ点数分布を示す学力テストか」ということです。」
下のような全国のテストの分布があったとしましょう。
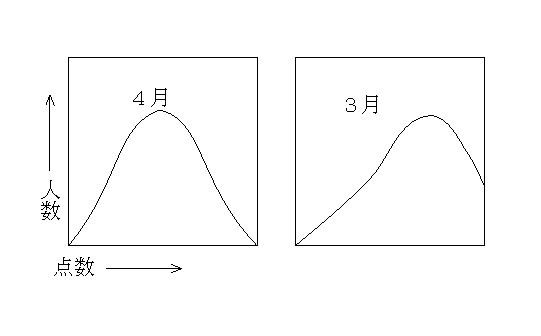
3月の分布は、右の方がかけていますね。ここが問題です。4月のように、右も左もかけてない分布であって初めて正しく比べることができます。しかし、平均点が4月も3月も同じ問題を作ることはきわめて困難です。そのために、4月と3月の平均を50点にするように、計算しなおします。さらに、分布の状態を同じようなものに計算しなおします。この統計的な手法が標準偏差なのです。そうすると、比較的精度の高い比較ができるのです。
4月のような分布になるためには、難しい問題から簡単な問題まであるテストを作ればよいのです。平均点が90点のテストは悪いテストで3月のような分布をします。能力の高い子供を正しく評価していないことになるのです。テストの分布で右側がかけているのは、能力の高い子供は、本当はもっと難しい問題もできるのに、難しい問題を解く機会が与えられていないということなのです。もっと、縮めて言えば、能力の高い子供を切り捨てていると言うことなのです。
現在のように、障害児やLD児、ADHD児、などを普通学級に受け入れれば、学級の学力テストの平均点が下がると言うことになると、受け入れが難しくなります。それでよいのでしょうか。学級単位で学力テストの平均を比べて担任を評価するような愚を犯しては、学級編成が正常に行えなくなってしまいます。すなわち、教員としての能力と経験のある人が、難しい子供達を数多く担任しないと学校全体としてうまくいかないからです。難しい子供を数多く担任すれば、学力テストの平均はかなり低くなるからです。そして、学力テストの平均を小数点単位で問題にすれば、微妙に在籍数に対して99.5パーセントとか98パーセントの学力テストの実施率の差が出ててくることになります。この2パーセントが難しい子供なのかも知れませんね。2パーセントもテストを受けていない子供がいれば、小数点単位の平均点の差は十分出せますから。
次に学力テストの結果を学校平均に利用することを考えてみましょう。学校の学力テストの平均は、義務教育諸学校の選択制とも関わってきます。学校の平均と言うことは、・教師の質、子供の質、親の質、地域の質が関わってきます。学区に低所得者層向けのアパートや入居料の安い市営住宅があったとしましょう。多くの場合、所得も低く子供のしつけがなっていない場合が多いわけです。当然、学力テストの学校平均は低くなります。そして、そういう子供には手が掛かります。そういう子供に手が掛かれば、担任は普通の子供にかける時間を減らさなくてはならなくなります。かくして、普通の子供も学力が伸び悩むのかも知れません。学校選択制になれば、少し裕福な家の子供は隣の学校に通うことになります。するとますますその学校は学力テストの平均が下がります。そうなった場合、どのような対策をとるのでしょうか。「低所得者向けの学校にしてしまえ。」ということなのでしょうか。学力テストの平均だけで学校を評価することは問題なのです。その原因が何であるか。仕方がない問題なのか、そうではないのかしっかりと分析をして、改善していくことが重要なのです。その時に、教育委員会が、問題の多い学校に優秀な先生を送らないと教育委員間の管轄する学校全体の学力の保証ができないのだと思います。学校選択制で、校長が優秀な先生を集めて良いと言うことになると学校間格差が大きくなり、30年50年後にはスラム街ができるのかも知れません。うがった見方かも知れませんが、スラム街では犯罪が横行することになることでしょう。もともと、公教育は国民全体の学力を向上させることが目的です。地域間格差が増せば、公教育としての役割も十分に果たされていないことになります。地域医療が難しいことになっているのと似ていませんか。
学力テストを細かいところまで問題にしだすと、かえって学校教育をいびつなものにしてしまいます。それぞれの段階(国、県、市町村、学校、学級)でどのように学力テストを利用するのかで、ますます教育を駄目にするのか、よくするのか差が大きいのです。両刃の剣ですね。
H18.10.22
指導要録
「指導要録」は指導するために必要な記録です。指導される側が見るための記録ではありません。まず、このことが基本です。そして、「良いところも悪いところも分からなければ、その子供を知ったことにはなりません。」と言うことなのです。「良いところも悪いところもある。」それが、人間なのです。「長所もあって短所もあって」それが、人間なのです。長所ばかりの人間もいませんし、短所ばかりの人間もいません。短所があることをおおらかに認め、少々の短所は許すべきなのです。
10年以上も前は、良いところも悪いところも指導要録に記載されていました。通知票と同じような感じです。◎○△という風にですね。ここの△は乱発ではなく顕著でなければつけなかったはずです。今は△はなくなってしまいました。○があるとなしで、2段階になりました。悪いところもは、一切載せないと言うことです。実際の社会に出れば、△、×だってあるはずです。義務教育というのは、社会生活に適応させることも重要な学習の一つです。それなのに・・・。最近は、義務教育で甘く甘く育てておいて、社会に出たとたん厳しくなっています。バブル崩壊以降、社内教育をするよりも、即戦力を望むようになってきました。学校と社会とのつなぎが離れるようになってしまいました。何割かの子供はそれでも大丈夫ですが、何割かの子供がこの格差のために適応できず、「ニートになる、就職しても定着しない。登校拒否の延長で引き続いて家に閉じこもっている。」などの問題が起きています。指導要録のあり方で起こっていることではありませんが、指導要録のあり方の発想「良いことのみに目を向け、悪いところに目をつぶるという態度」が問題になるのだと思います。
どんな指導要録であるべきでしょうか。良いところと悪いところが公平に書かれてあることが重要なのです。それだから、良いところも悪いところも包み込んであげることができるのです。良いところのみを見て、悪いところは見ないということでよいのでしょうか。
指導要録の開示について考えてみましょう。本人が「指導要録に書いてある自分の悪い部分を見て、自分はこんな風に見られていたんだ。」と落胆することが起こる可能性があります。子供も親も落胆するのかも知れません。しかし、実際の「指導要録」は指導するために必要な記録なのです。指導される側が見るための記録ではないのです。指導される側が見ることを前提に書かれるということは、「△をなくして、良いことのみを書くこと」につながります。それでは、指導の役にはあまり立たないのです。転校したとき、指導要録の写しが送られます。そして、転校してくる実際の子供は「長所も短所もある子供」なのですね。肝心なことが書いてないのではね。感心なことが書けないのなら指導要録が必要かどうかも議論の必要がありますね。そして、指導要録の項目の再検討も必要でしょう。
そこで問題になってくるのは、誰が指導要録を見るかと言うことです。義務教育の間は、試験無しに転校することができます。従って、義務教育間で指導要録のやりとりがされることは大きな問題はありません。そして、裁判所が必要に応じて、指導要録を見ることも必要がある場合があります。問題は、義務教育と義務教育ではない場所への提示と言うことになります。つまり、高校入試の問題です。高校入試が入試と面接のみで決まるのであれば、全く問題がありません。ところが、たった1回のテストで入学が決まるのでは可愛そうだという意見があり、そのため、中学校の成績を加味するということになったようです。そして、その成績の中に学業ばかりでなく生活様子まで書かれていて、「入試に受からなかったのは、指導要録のせいだ。」と疑念を持つ親がいることです。入試のための書類に悪いことを書く教師はいないはずです。ただし、「担任と親や子供との関係がきわめて悪くなった場合」100パーセントあり得ないことではないでしょう。もちろん、公正に入学のための書類を書くべきです。その場合は、裁判所を通すか教育委員会を通して確認することが必要かも知れません。そのような場合、悪意を持った教師を想定するのならば、高校入試に指導要録を使うのは、学業成績のみにすればよいのではないのでしょうか。高校は義務教育ではないので、その高校の学力に見合わない、授業をまじめに受けない、重要な法律違反をするなどのことがあれば、その子供にやめてもらえば良いからです。高校は、義務教育だけでは、学習が不十分だから通うのであって、その高校の学習を行いたくないのであればやめるべきなのです。そして、高校の転校で試験なしというのならば、指導要録の全項目必要なのかも知れませんが、転校のための試験と面接があるのならば、転校前の成績を加味しないのならば指導要録は、必要ありません。加味するのならば、指導要録の学業成績が必要ですね。このように、高校入試や転校の形態に応じて、指導要録の利用の仕方を変えることも大切なことだと思います。
H18.10.22
教員免許更新制度
教員は、教員免許があっても採用されるわけではないのです。教員免許があった上に教育委員会に採用されなければならないのです。従って、自動車免許とは本質的に違うのです。「自動車免許が取得できれば、レンタル車だろうと自家用車だろうと、お客さんさえ乗せなければ会社の車だって運転できます。どこかの会社に入社しないと運転できないわけではありません。」自動車免許を例に挙げて教員免許更新制度を話す人は、「法の知識がないか、悪意(後ろめたい気持ち)をもってごまかしている」のだと思います。
地方公務員法で、特別な理由がなければ公務員を免職させることができません。教員で、指導力の問題がある場合は、採用した教育委員会が採用を取り消すことが筋となります。ただし、公正な決定かどうかを判定する場は、通常の会社であれば、組合があり不当解雇をストライキなどを行い阻止できることもありますが、公務員はストライキ権がないのそれもできません。裁判を起こさないといけないのです。「ストライキ権がない」ことと、「よほどの理由がない限り免職させることができない」こととは、表裏一体の関係になります。従って、「教員を免職させることが、比較的簡単にできる」のならば、「ストライキ権を与える」と言うことになります。もし、ストライキ権なしで、免職ができるようにすれば、制度のアンバランスと言わざるを得ません。「法の下の差別」と言わざるを得ないのです。憲法第14条の「 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とあることに違反しています。
これからは、推論になりますが、他の公務員に影響させずに、教員のみを簡単に免職できる方法を政治家が考えたのです。それが、「教員の免許更新制度」です。免許を更新するのに、「研修、その他」としておくだけでよいのです。その他の中に、普段の勤務成績を入れておけばよいのです。
免許更新制度をする理由として、「ベテランの教員が指導できなってきている。だから、研修する必要がある。」ということを挙げていますが、全ての県で行われている化は知りませんが、今まででも、「○年目研修」といって、採用されてから○年目の研修が、教員委員会で行われています。だから、もっと、研修をさせたければ、そのように、文科省が全国の都道府県に、指示するだけでよいのです。公務員には、「研修の義務」があるからです。免許更新制度を行うことと、研修を行うことに因果関係はありません。別の理由があるから免許更新制度を持ち出しているのです。「教員を簡単に解雇させたい」からです。
さて、どのようなところに問題点があるのでしょうか。
(1)ある年度に大量採用した教育委員会があれば、何十人もの教員に研修の機会を与えないこといけないことになります。そうすると、担任がその間、担任できなくなり代わりの講師を雇わなくてはならなくなります。それでは、夏休みに行うと言うことになります。すると、教育大学の教員が、夏休みに、小中高の教員の研修を行わなくてはならなくなります。それでは、教育大学の教員の教員免許の更新はどうなるのでしょうか。そして、教育大学の教員(教授、助教授、講師、助手)の研修は何処で行うのでしょうか。
また、教員の場合、年次有給休暇は病気などではない限り、夏休みなどの長期休業中にとります。免許の更新のために、年次有給休暇は保証されないというのでしょうか。それでは、労働基準法違反になってしまいます。
(2)講師の問題
教育委員会に正規教員として採用されていない人たちはどうなるのでしょうか。まず、ペーパードライバーのように免許をとって以来運転していない人たちには、免許を無条件に更新させるというのでしょうか。無条件に更新させておいて、講師として採用するときに何十時間もの研修を行ってから講師として採用するのでしょうか。それとも、採用されていない人たちは、免許を更新する必要がないと言うのでしょうか。それでは、法のもとの平等ではありませんし、免許更新制度とはとても言えません。
こんなことでは、産休の講師、担任が病気のための講師、その他の講師、採用が大変になってしまいます。おそらく、講師不足に拍車が掛かることになるでしょう。講師が不足すると、担任がいなくなったクラスは、管理職など、何人もの教員が入れ代わり立ち代わり教えることになってしまいます。それでは、子供は安定した気持ちで授業を受けることができません。
(3)全ての管理職は立派な人たちである
こんなことを前提にされては、非常に問題です。平の教員である間は、良い先生であっても、校長になったとたん横暴になる人も時々いますし、校長に合わない人もいます。人間ですからいろいろな人がいるのです。このような問題校長に、判定されるのでは困るのです。運で裁かれるのは法治国家とは言えません。「悪い校長に当たると不利になる。最悪の場合、あることないこと報告されて、研修を行いにくいようにさせ、教員免許を更新させてもらえない。」と言う意味です。
「校長に任免権に近い権限を持たせること」は、「校長の公正な人間であるか判断する公正な機関」が必要です。公正な機関には「教育委員会、教員組合」。そして、教育委員会のメンバーは、「校長会と利害関係がない人、有識者」などが条件になると思います。
校長が大きな権限を持つのならば教員にも学校を選ぶ権利があるのではないでしょうか。そうでないと、特別な考えを持った校長や、公正な判断のできない校長の学校に転勤した場合、非常に不利な査定を受けたり、免職されてしまうからです。
(4)学級崩壊は簡単に起こせる
今は、しつけのできていない子供達が増えています。「小学校1年生で、授業中でも教室を歩き回る。」「社会性が育っていないためにトラブルをいつも起こす。起こさせる側も社会性が育っていないのでけんかが止まらない。」「両親が離婚し、子供の精神状態が不安定である。」「両親共働きのため、家に帰っても家人はいず、夜まで子供達だけで過ごしている。」などなどです。学年のクラス編成をするときに、校長がわざと、気に入らない教員のクラスの問題の子供を少し多く入れれば、たちまち学級崩壊を起こしてしまいます。今度は、問題の親、「大したことでもないのに、学校や教育委員会に怒鳴り込んでいく親。」「子供同士けんかをしても、自分の子供は常に正しく、相手の親の子供が常に悪いと考える親。」「自信がなく、子育てに常に不安を持ち、常に担任や養護教諭と相談しなくては、いられない親」などなど。このような親が、2〜3人もクラスにいれば、担任はかなりまいってしまいます。他のクラスより、このような親を少し増やしておけば、学級崩壊には、十分です。
管理職が気に入らない教員をわざと学級崩壊させて、解雇してしまうことだって可能なのです。立派な管理職ばかりでないことを自覚しないといけません。だからこそ、免許更新制度の発足と同時に、労働三権(団結する権利、団体交渉をおこなう権利、団体行動をおこなう権利)が、教員にも必要となるのです。
(5)指導力不足の教員を解雇すれば教育は良くなるのか
ほとんどの人間は、その会社、役所、学校など、その職場でうまくいかなければ、そこにとどまることを悩みます。そして、自分から退職するものなのです。
一時、公務員だから、簡単に解雇できないので、教員以外の公務員に採用するという方法が考えられましたが、いつの間にか立ち消えになったようです。年をとってから、新しい職場で働くのが大変だからだと思います。入った方も入られた方も居心地が悪いような気がします。
もっと、大きい問題に目を向けなくてはなりません。人間はいても、よい人材がいないと言うことなのです。良い人材がたくさんいた頃には、良い人材が教員にまで回ってきましたが、良い人材の減った今では、教員にまでなかなか良い人材が回ってこないことになります。それでは、良い人材が少ないからと言って、あきらめていたのでは仕方がありません。5段階で3の段階ならば3を4にすることが必要なのです。教員評価制度のようにお互いに足を引っ張るような、個別の評価のようなことではうまくいかないのです。教員同士助け合い伸びていくような仕組みが必要なのです。いつ、足下をすくわれるかも知れないと思っていては、まともな教育はできないのではないのでしょうか。
もう一度、言いますが、「教員免許があれば、教員として採用されるわけではありません。教員委員会が採用したのです。指導力不足な教員を採用した責任は教育委員会にあります。従って、解雇するのは教育委員会であるのです。教育委員会が責任を持って身長に行うべきことなのです。教員免許があるなしは関係ないのです。教員免許にかこつけて、信条や個人的な理由(気に入らないなど)で免許を陰に隠れて取り消し、解雇してしまう危険があります。」
H18.10.2
学校のIT化の遅れたわけ
教員は、残業が基本的にないことになっています。大都会では、出世を望まない人たちは、あまり残業をしなくても良いと聞いていますが、地方ではそうはいきません。特別手当が出ていたとしても1日15分程度であす。1時間くらいの残業は当然で、それ以上が当たり前の地域が多くあります。しかも、手当はありません。週40時間労働なんて、夢のまた夢、週45時間、週50時間なんて珍しくありません。土日が休みになったから言って、週労働時間が減ったわけではありません。土日に休日出勤をする人もいます。勿論、1銭もでません。これらは、労働基準法違反は明らかであるのにもかかわらず。黙認することになっているようです。
ここで、労働基準法に則って残業手当を出すことになったとしてみましょう。そうすると、業務の能率化が急務となります。例えば年間400時間の残業があったとしましょう。時間あたり3000円とすれば、400×3000=120万、コンピュータは20〜30万で手に入ります。コンピュータを導入した方が安上がりですね。実際には、このような単純な 計算では行かないと思います。このような理由で、残業手当を出すことになれば、IT化がすることは間違いないと思います。
H18.9.20
総合学習について
総合学習は、物事を総合的に有機的に考える学習形態である。しかし、それを教えることの出来る人材が少ないことが問題なのである。本家のイギリスのように、何十年という伝統のある国ならばそれも可能かもしれないが、日本ではそうはいかないのである。なぜなら、「出る釘は打たれる」国だからである。ただ、それでも、難問奇問のある大学入試が存在していた間は良かったのである。自由に発想する能力がなくては解けないからである。ところが、この難問奇問が社会問題になって、大学入試センターがマークシート式の問題になってしまった。しかも、高校の学習をしっかり理解できていれば出来るという問題である。マークシート式というのは、客観的であるかもしれないが、大学としてあるべき能力を検査できるとは思えない。なぜなら、「よく分かっていなくても番号を選ぶことが出来る。」からである。客観性は落ちるかも知れないが、記述式の入試が良いと思う。しかも、その大学が必要としている能力の人物を、その大学が入試問題を作り、選定するべきだと思う。
マークシート式の大学入試になったからといって、全ての大学生の能力が下がるわけではないが、能力の高い学生の割合が減少していることは間違いがない。そして、その能力の下がった大学生が企業、教員になっていくのである。そして、能力の高い学生の奪い合いが起こり、教員にはなかなか回らないようになったのである。
そういう状況に文部省がしておいて、総合学習の指導ができる教員があまりいないという議論は馬鹿げている。能力が低い教員はやめさせればよいという安易な対策は無意味である。教員志望は多くても、総合学習を教えられるような人物は少ないのである。そして、総合学習が行えるような人物は、もっと給料の良い優良企業に入社してしまうのである。
総合学習は、とても良い形態だとは思うが、今の人材では困難であるので、とりあえず廃止すべきである。面目にこだわっている場合ではないだろう。それよりも、急務なのは、教科書の質が落ちると同時に、通常の授業をきちんと行える教員が減りつつあることである。まず、国語ならば、読めば読むほど、様々な解釈のできるような教材文が必要である。少し、詳しく読むと矛盾をしたり、破綻したりする文章ではどうしようもなのである。そして、20〜30年後、教科書及び教員の資質が上がったところで、再導入すればよいだろう。目新しさばかり追求し、よく検討しないで実施すれば、逆効果になるだけである。
H18.8.20
公教育とは何のため?
日本国民の育成のためである。
日本は間接民主主義を取っている。
「有権者→政治家→行政」と言うようにである。
現在は、貿易が盛んになり、1つの国だけで成り立っていくことは困難である。そこで、国民が幸福になるためには、国民一人一人が最大限の力を出し切る必要があることになる。特に、イギリスで産業革命が起こってからそういうことになった。ナポレオン戦争の頃から民衆も巻き込んだ総力戦ということが言われるようになった。総力戦とは、戦争ばかりでなく経済でも同じことである。
「国民一人一人が幸福」←→「国が幸福」のように車の両輪の関係である。
そして、その一人一人が最大に力を出すことは、困難な場合も存在する。能力があったとしても、貧困などで教育の機会が与えられない場合も生ずる。そこで、公教育の登場である。
(1)社会生活を送るのに有用な能力をつける。
(2)社会生活を送るのに最低限の能力をつける
(1)について
家族の中ならば法律がなくても大丈夫である。家族の中の決まりを文章で表さなくても大きな支障はない(財産があって遺産相続の問題があるなら別だけれども)。しかし、複雑な社会になると文章を使って意思を伝えたり、契約をしたりすることになる。また、工場で働いたり食堂で料理をしたりするにも、やり方を学ぶ必要がある。工場で生産するものが、料理が高度になればなるほど、様々な知識や試行錯誤が必要となる。忍耐と学習が大切である。
(2)について
例えば、新しい規則ができた場合、それを国民が理解できなくてはならない。もし、文字が読めなければ絵で示したり、身振り手振りで大変である。語彙が少なければ理解さえ難しいかもしれない。文章の理解力が劣る人は法律や物事の仕組みが分からないので、社会的に非常に不利な状況になる。車の運転が出来ないなど様々な資格を取ることが出来ない。アパートを借りるときの手続きなど・・・・。
国民の意見→政治家→行政→国民の利益&国力の向上」と言うことになる。
ただ、勘違いしてはいけないのは、公教育は個人(一部の業界)の利益の追求の場ではないことである。決められた範疇での教育で、国民の能力を全体として向上させることが目的である。バランスよく国民を向上させることが大切だからである。
国民が向上すれば国力が向上することになる。
しかし、一部の利益のみを図ったり、全体を考えずに公教育を行うと学力の低下を招く。次に、企業にも影響が出て人材不足を招く。次に貿易赤字を起こし、国は貧乏になっていく。そうすると、食糧自給率が低ければ、農薬まみれや危険な遺伝子組み換えの食料を買わざるを得なくなる。こじつけのような気もするがあり得ない話ではない。30年後の国民に何が必要かを考え公教育を行って行かなくてはならない。
H18.8.19