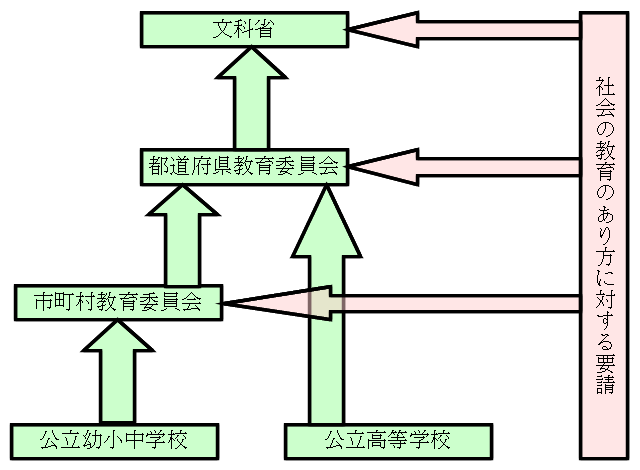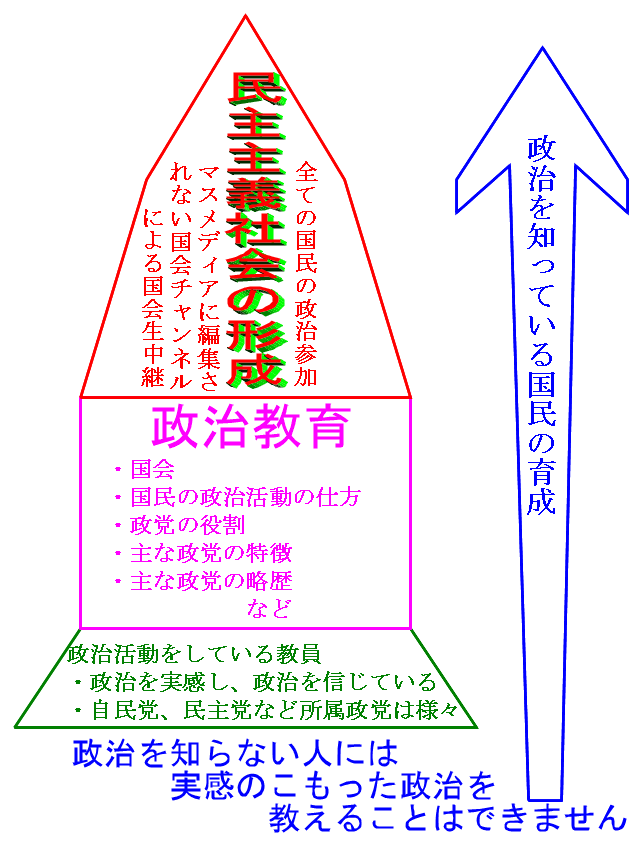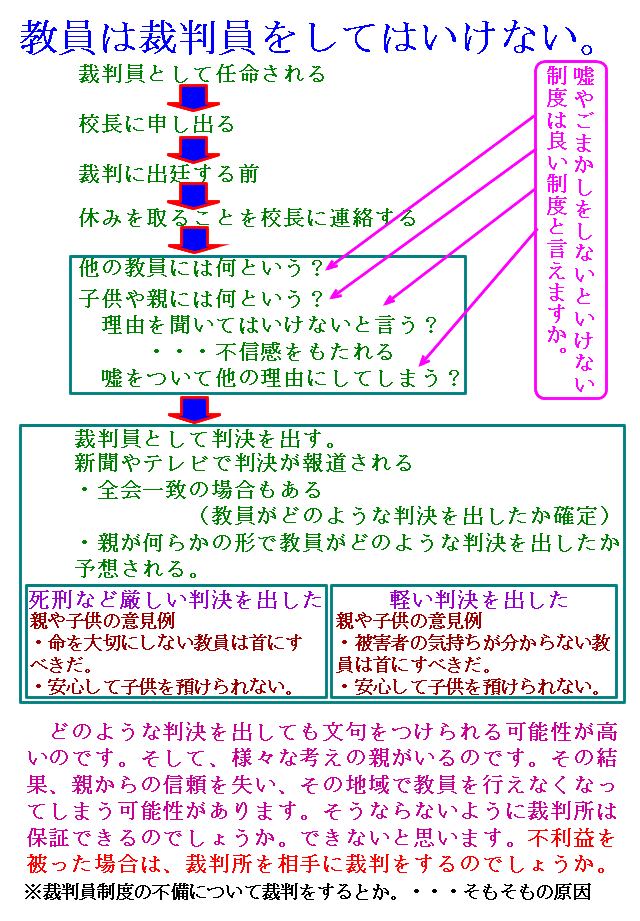教育 平成20年
携帯電話について(教育再生懇談会)
小中学生が学校に携帯電話(註1)を持ってきて良いかどうかを教育再生懇談会が指示することが適切でしょうか。本来は、総理大臣が教育に要請する場合は、文科省大臣に指示することです。ところが、私的な団体である経団連の意見を直接教育に反映させたいために、教育再生会議(現教育再生懇談会)なるものを作ったとも勘ぐれます。
「携帯電話がどうのこうの」と言うのは、本来は家庭教育の問題です。家庭教育が崩壊している家庭が多いことが問題なのです。家庭教育を立て直していくことが必要です。それは、公立学校が行うことではありません。社会教育の範疇です。家庭教育を行っていくための組織や法律が必要です。児童相談所の延長のような組織です。家庭教育に関する指導を行います。問題のある家庭については、強制的な指導も可能にするべきです。例えば、虐待を行っている親に対して、強制的な指導ができるようにすることです。また、児童・生徒が携帯電話(インターネットを使った出会い系サイトを利用した売春や麻薬販売など)に関する犯罪を起こした場合は、児童・生徒の携帯電話を禁止したり、インターネットの使用できない携帯電話しか許可しないなどの措置ができるようにするべきです。保護者が子どもを指導できなかったら保護者を処罰します。処罰の程度で、家庭裁判所の裁定が必要な場合も考えます。そして、保護者が児童・生徒を育てる能力がないと裁判所が認めた場合は、強制的に保護者と児童・生徒を離し児童保護施設送致(少年院のことではありません)にします。
今回の「小・中学校携帯電話原則持ち込み禁止」は、対処療法であり、根本治療ではありません。しかも、学校本来の業務ではありません。家庭教育力の向上という観点で仕切り直す必要があります。そのためには、教育委員会の立て直しが必要です。政治は、大枠を作ることが仕事です。つまり、教育委員会制度が適切に機能するようにすることが仕事です。
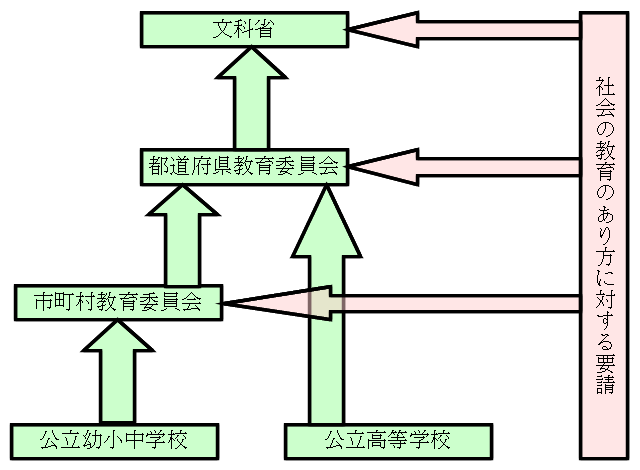
註1:
小中携帯、原則禁止を…教育再生懇が提言素案(12月16日読売新聞より引用)
政府の教育再生懇談会(安西祐一郎座長)がまとめた子供の携帯電話利用に関する提言の素案が15日、明らかになった。小中学校への持ち込みの原則禁止などの方向性を示したことが特徴で、来月、麻生首相に提出する予定だ。大阪府の橋下徹知事が、政令市を除く府内の公立小中高校で携帯電話の持ち込みや校内での使用を禁じる方針を示して波紋を呼んだばかりだけに、政府の今後の対応が焦点となる。
家庭内ルール、保護者に要請
素案では、子供の携帯電話利用の弊害に関し、「わいせつ情報や暴力、いじめを誘発する有害情報が悪影響を与える」と指摘、保護者が「家庭内ルール」を作ることや、小中学校が「持ち込みの原則禁止」を打ち出すなど、利用方針の明確化が必要だとした。
子供が携帯電話を持つことそのものの是非については、家庭との緊急連絡などのために必要との主張に配慮し、「通話先限定や、GPS(全地球測位システム)機能のみの携帯電話や、これらの機能に緊急連絡用のメール機能を付加した携帯電話は有効」とした。
その上で、PTAや教育委員会が連携して、機能限定機種の「推奨制度」の確立を提案している。電話会社にも、学校などに子供が使いやすい公衆電話を確保するなどの協力を求めた。
また、保護者の判断で有害サイトに接続できないようにする「フィルタリング機能」の利用状況や、有害情報の影響について、国が3年後に検証し、改めて対策を講じるとした。
註2:教育再生懇談会
名簿
赤 田 英 博 社団法人日本PTA全国協議会顧問
◎ 安 西 祐一郎 慶応義塾長
池 田 守 男 株式会社資生堂相談役
小 川 正 人 放送大学教授
木 場 弘 子 キャスター、千葉大学特命教授
篠 原 文 也 ジャーナリスト
菅 原 眞 弓 東京都立川市立第九小学校教諭
田 村 哲 夫 学校法人渋谷教育学園理事長
野 依 良 治 独立行政法人理化学研究所理事長
若 月 秀 夫 東京都品川区教育委員会教育長
(注)◎座長
平成18年10月10日の閣議決定により設置された教育再生会議は廃止され、教育再生懇談会が設立された。(平成20年2月26日)
日本経済団体連合会 委員会委員長等一覧 平成20年10月1日現在
政策委員会
【政策全般】
1.総合政策委員会
委 員 長:御手洗 冨士夫 (キヤノン会長)
2.国の基本問題検討委員会
委 員 長:清 水 正 孝 (東京電力社長)
【経済・法制関係】
3.経済政策委員会
共同委員長:奥 田 務 (J.フロント リテイリング社長)
共同委員長:畔 柳 信 雄 (三菱UFJフィナンシャル・グループ社長)
4.税制委員会
委 員 長:張 富士夫 (トヨタ自動車会長)
共同委員長:大 橋 光 夫 (昭和電工会長)
5.財政制度委員会
委 員 長:氏 家 純 一 (野村ホールディングス会長)
共同委員長:秦 喜 秋 (三井住友海上火災保険会長)
6.社会保障委員会
委 員 長:森 田 富治郎 (第一生命保険会長)
共同委員長:井 手 明 彦 (三菱マテリアル社長)
7.金融制度委員会
委 員 長:古 川 一 夫 (日立製作所社長)
共同委員長:奥 正 之 (三井住友銀行頭取)
8.経済法規委員会
委 員 長:張 富士夫 (トヨタ自動車会長)
共同委員長:萩 原 敏 孝 (小松製作所相談役)
【行革・産業・国土関係】
9.行政改革推進委員会
委 員 長:前 田 晃 伸 (みずほフィナンシャルグループ社長)
10.道州制推進委員会
委 員 長:中 村 邦 夫 (パナソニック会長)
共同委員長:池 田 弘 一 (アサヒビール会長)
11.産業問題委員会
共同委員長:原 良 也 (大和証券グループ本社最高顧問)
共同委員長:西 田 厚 聰 (東芝社長)
12.起業創造委員会
共同委員長:高 原 慶一朗 (ユニ・チャーム会長)
共同委員長:齋 藤 宏 (みずほコーポレート銀行頭取)
13.運輸・流通委員会
委 員 長:宮 原 耕 治 (日本郵船社長)
共同委員長:亀 井 淳 (イトーヨーカ堂社長)
14.農政問題委員会
共同委員長:荒 蒔 康一郎 (キリンホールディングス会長)
共同委員長:小 林 栄 三 (伊藤忠商事社長)
15.都市・地域政策委員会
委 員 長:岩 沙 弘 道 (三井不動産社長)
共同委員長:山 口 昌 紀 (近畿日本鉄道会長)
16.観光委員会
委 員 長:大 塚 陸 毅 (東日本旅客鉄道会長)
17.住宅政策委員会
委 員 長:渡 文 明 (新日本石油会長)
【技術・環境・エネルギー関係】
18.産業技術委員会
委 員 長:榊 原 定 征 (東レ社長)
共同委員長:中 鉢 良 治 (ソニー社長)
19.知的財産委員会
委 員 長:野間口 有 (三菱電機会長)
共同委員長:足 立 直 樹 (凸版印刷社長)
20.情報通信委員会
共同委員長:石 原 邦 夫 (東京海上日動火災保険会長)
共同委員長:渡 辺 捷 昭 (トヨタ自動車社長)
21.電子行政推進委員会
共同委員長:秋 草 直 之 (富士通取締役相談役)
共同委員長:渡 辺 捷 昭 (トヨタ自動車社長)
22.海洋開発推進委員会
委 員 長:元 山 登 雄 (三井造船会長)
23.環境安全委員会
委 員 長:坂 根 正 弘 (小松製作所会長)
共同委員長:鮫 島 章 男 (太平洋セメント会長)
24.資源・エネルギー対策委員会
共同委員長:柴 田 昌 治 (日本ガイシ会長)
共同委員長:岡 素 之 (住友商事会長)
【社会関係】
25.広報委員会
委 員 長:清 水 正 孝 (東京電力社長)
26.企業行動委員会
委 員 長:渡 文 明 (新日本石油会長)
共同委員長:大 歳 卓 麻 (日本アイ・ビー・エム社長兼会長)
27.社会貢献推進委員会
共同委員長:古 賀 信 行 (野村證券会長)
共同委員長:佐 藤 正 敏 (損害保険ジャパン社長)
28.政治対策委員会
委 員 長:大 橋 光 夫 (昭和電工会長)
29.教育問題委員会
委 員 長:三 村 明 夫 (新日本製鐵会長)
共同委員長:蛭 田 史 郎 (旭化成社長)
30.防災に関する委員会
共同委員長:數 土 文 夫 (JFEホールディングス社長)
共同委員長:木 村 惠 司 (三菱地所社長)
【経営労働関係】
31.経営労働政策委員会
委 員 長:大 橋 洋 治 (全日本空輸会長)
32.雇用委員会
委 員 長:鈴 木 正一郎 (王子製紙会長)
33.労使関係委員会
共同委員長:指 田 禎 一 (日清紡績会長)
共同委員長:市 野 紀 生 (東京ガス会長)
34.労働法規委員会
委 員 長:三 浦 惺 (日本電信電話社長)
35.中小企業委員会
委 員 長:澤 部 肇 (TDK会長)
36.国民生活委員会
委 員 長:岡 部 正 彦 (日本通運会長)
37.少子化対策委員会
共同委員長:池 田 守 男 (資生堂相談役)
共同委員長:鈴 木 茂 晴 (大和証券グループ本社社長)
38.国際労働委員会
委 員 長:立 石 信 雄 (オムロン相談役)
【国際関係】
39.貿易投資委員会
委 員 長:佐々木 幹 夫 (三菱商事会長)
40.国際協力委員会
委 員 長:槍 田 松 瑩 (三井物産社長)
共同委員長:矢 野 薫 (日本電気社長)
41.OECD諮問委員会
委 員 長:本 田 敬 吉 (イー・エフ・アイ会長)
42.経済連携推進委員会
委 員 長:大 橋 洋 治 (全日本空輸会長)
共同委員長:勝 俣 宣 夫 (丸紅会長)
地域別・国別委員会
1.アメリカ委員会
委 員 長:長谷川 閑 史 (武田薬品工業社長)
共同委員長:村 瀬 治 男 (キヤノンマーケティングジャパン社長)
2.カナダ委員会
委 員 長:青 木 哲 (本田技研工業会長)
3.ヨーロッパ地域委員会
共同委員長:横 山 進 一 (住友生命保険会長)
共同委員長:小 林 喜 光 (三菱化学社長)
4.アジア・大洋州地域委員会
共同委員長:宮 内 義 彦 (オリックス会長)
共同委員長:土 橋 昭 夫 (双日会長)
(1) 中国委員会
共同委員長:三 村 明 夫 (新日本製鐵会長)
共同委員長:中 村 邦 夫 (パナソニック会長)
(2) 日本・インドネシア経済委員会
共同委員長:興 津 誠 (帝人顧問役)
共同委員長:辻 亨 (丸紅相談役)
(3) 日タイ貿易経済委員会
共同委員長:丹 羽 宇一郎 (伊藤忠商事会長)
共同委員長:西 松 遙 (日本航空社長)
(4) 日本ベトナム経済委員会
委 員 長:加 藤 進 (住友商事社長)
(5) 東亜経済人会議日本委員会
委 員 長:上 島 重 二 (三井物産特別顧問)
(6) 日本・香港経済委員会
委 員 長:鈴 木 邦 雄 (商船三井会長)
5.中南米地域委員会
委 員 長:佐々木 幹 夫 (三菱商事会長)
(1) 日本メキシコ経済委員会
委 員 長:小 枝 至 (日産自動車相談役名誉会長)
(2) 日本ブラジル経済委員会
委 員 長:槍 田 松 瑩 (三井物産社長)
(3) 日本ベネズエラ経済委員会
委 員 長:小 島 順 彦 (三菱商事社長)
(4) 日本コロンビア経済委員会
委 員 長:小 島 順 彦 (三菱商事社長)
6.中東・北アフリカ地域委員会
委 員 長:渡 文 明 (新日本石油会長)
(1) 日本トルコ経済委員会
委 員 長:梅 田 貞 夫 (鹿島建設会長)
(2) 日本イラン経済委員会
委 員 長:野 村 哲 也 (清水建設会長)
(3) 日本アルジェリア経済委員会
委 員 長:重 久 吉 弘 (日揮会長兼CEO)
7.サブサハラ地域委員会
委 員 長:土 橋 昭 夫 (双日会長)
8.日本ロシア経済委員会
日本NIS経済委員会
委 員 長:岡 素 之 (住友商事会長)
特別委員会等
1.防衛生産委員会
委 員 長:佃 和 夫 (三菱重工業会長)
2.宇宙開発利用推進委員会
委 員 長:谷 口 一 郎 (三菱電機相談役)
3.自然保護協議会
会 長:大久保 尚 武 (積水化学工業社長)
4.企業人政治フォーラム
会 長:大 橋 光 夫 (昭和電工会長)
5.1%クラブ
会 長:佐 藤 正 敏 (損害保険ジャパン社長)
6.むつ小川原開発推進委員会
委 員 長:佃 和 夫 (三菱重工業会長)
7.NICC協議会
委 員 長:立 石 信 雄 (オムロン相談役)
日本経済団体連合会の運営に関する委員会
1.事業委員会
委 員 長:福 原 義 春 (資生堂名誉会長)
2.財務委員会
委 員 長:森 田 富治郎 (第一生命保険会長)
H20.12.22
政治教育と自由民主党
自由民主党は、日教組が民主党を応援しているので日教組を嫌っているようですが、逆に自由民主党を支持している日教組組合員は、「存在していないと思っている」か「黙殺している」のではないでしょうか。民主党を応援する日教組を教員免許法更新制度でいじめ、言論の自由(註1)や政治活動の自由を奪って良いものでしょうか。どの日本国民にも、言論の自由や政治活動の自由はあるはずです。現実的に日教組で自民党を支持するのは隠れキリシタンみたいなものです。日教組の自民党を指示する人(註2)は、自民党からも日教組からも圧力を受けることになっています。自民党はこのような状態をよいと思っているのでしょうか。
自由民主党が、民主主義政党だというのならば、公務員だろうが、会社員だろうが、フリーターだろうが、ワーキングプアーだろうが、日本国民であれば、政治に参加する権利と保障をするべきです。公務員に政治活動ができないように制限しておきながら、組合組織として野党を支持しているから気に入らないのでは、筋が通りません。個人でも勤務時間以外は、自由な政治活動ができるように法律を改正するべきです。英国や米国などでは認められていることです。民主主義が成熟している国家は全て認められていることです。教員の政治活動を認められていなくて、政治教育ができるわけがありません。政党を支持できない教員がまともな政治教育ができるはずがありません。政治教育の貧困が、「誰が総理大臣でも同じ」と言う民主主義にふさわしくないことを言うようにさせているのです。政治が悪ければ世の中も悪くなるのです。逆に政治が良ければ世の中が良くなるのです。もちろん、特定の政党を応援するような政治教育は行ってはいけません。
改正すれば、すぐに効果が現れるわけではありませんが、子供達から民主主義への道が開いていく必要があります。政治教育が良くなれば、できもしないようなことを平気で言う政党は淘汰されていくはずです。そのためには、いかなる職業に就いていようとも、日本国民ならば、同じ自由と権利が保障されるべきです。憲法で「法の下の平等」は、保証されているのです。
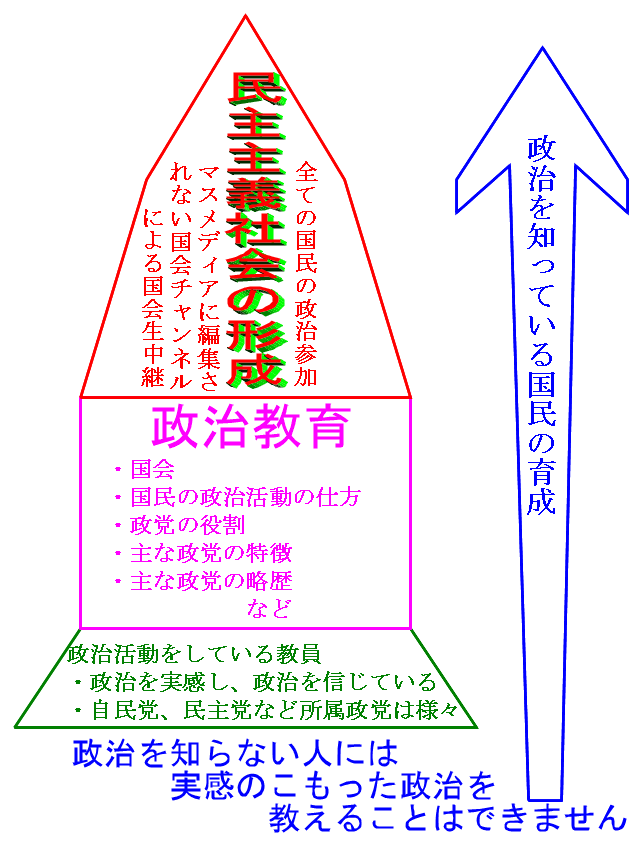
註1:国民投票で意見を言う活動をしてはいけない
註2:鈴木政洋は自民党も民主党も指示していません。過去の包容力のあった頃の自民党は指示しても良いと思っています。
H20.9.22
大分県の汚職による教員採用取り消しについて
大分県の教員採用に関する汚職(註1)で、大分県教育委員会は、21人を退職に追い込みました。本人が汚職を頼んでいたのであれば、採用取り消しは仕方ありませんが、汚職に身に覚えが無ければ、汚職で採用された教員には責任はありません。その教員にとってみれば、大分県教員委員会に問題があったことになります。だから、その教員にとって見れば、最強が取り消し、あるいは退職させられた責任は、大分県教育委員会にあることになります。従って、大分県教育委員会に賠償責任があることになります。
つまり、身内が汚職を起こしたからと言って、汚職の責任のないものが責任を取るのは間違っています。日本は、法治国家ですので、連帯責任(註2)を負うことはないのです。
大分県教育委員会の行っていることは、自分の責任を直接責任のない個人になすりつけるものです。本人の知らないうちに身内が行ったことまで責任をとるのは、おかしいです。 この教員採用に関する汚職はかなり以前からなされているようです。昨年度で21人の規模で、慣例的に以前からなされていた問い事になれば、当然、直接は関わらなくても、大分県教委の方々ははっきりと汚職を知っていたか、汚職があると感づいていたはずです。感づいていても、知らない振りをしていたと言うことです。「汚職のにおいがするだけでは、警察に届けるわけにもいかない。」「積極的に汚職の調査をすれば、別のことで汚職をしている人々から足下をすくわれるかも知れない。」ということでしょうか。大分県は、平成20年8月現在で120万人の小さな県です。教員の採用が少ないと汚職の可能性も増えます。数百人とか数千人の受験者という規模になれば、汚職の加わる余地がありません。一覧表で見られるくらいの人数なので簡単に操作できてしまうのです。しかし、逆に少しの受験者なので、汚職がないかチェックするもの簡単にできます。
汚職は、頼む者と頼まれる者がいて成り立ちます。「○○を教員採用で手心を加えて欲しい。」と金銭(金券)を持ってきたとしても、断ればそれで済んだことです。だいたい、「お金を持って行けば何とかなる」という噂がなければ、大分県教育委員会に行くわけがありません。きっと最初のうちは金額が少なかったと思います。それが、長年の間に相場ができてきたのではないかと思います。
鈴木政洋が考えた対処の仕方:
(1)直接、金銭授受を行った者の処分を行います。
(2)県教育委員会の汚職によって、嵩上げで受かった者については、教員としての資質の調査(註3)を行います。教員としての適切な能力が発揮されているかと言うことです。そのまま採用します。ただし、汚職に直接関わっていた場合(註4)は、退職してもらいます。
(3)今までの採用についても、時効になっていない範囲で、かさ上げで採用された教員としての資質の調査を行います。そして、能力が無い場合は、退職してもらいます。
(4)汚職に直接関わっていた場合は、その程度に応じて、処分を行います。訓告、戒告、減俸、依願退職、解雇(悪質な場合)などです。
(5)汚職がないかのチェックを教育長自身が行うようにします。
教育の独立という意味で、教育委員会以外の人間が関わるのには問題があります。県庁の職員でも同じことです。教育委員会の内部情報を関係者以外が関わるのはよくないのです。緊急避難的に、本年度だけ行うならばともかく永続的に行うことは問題です。教育長が陣頭指揮を執って汚職防止をするべきです。それが、教育委員会制度というものです。県庁の下請けのような扱いも教育委員会制度の理念とは、相反します。
※なお、この対処は何日も検討を重ねたものではないので、もっと良い方法があると思います。
註1:大分県の教員採用汚職について 平成20年9月7日 読売新聞より引用
「4教諭自主退職せず、大分県教委が採用取り消しへ 大分県教委汚職」
大分県の2008年度教員採用試験で、不正合格者とされた21人のうち、少なくとも4人が採用取り消しになる見通しであることが6日、わかった。
4人は採用取り消しを受け入れるとした内申書を県教委に提出しており、7日の臨時教育委員会で正式に決定する。
県教委によると、21人中1人は8月に退職済みで、残る20人のうち15人は自主退職を選び、県教委に退職届を提出。1人は態度を保留している。県教委は、自主退職者以外は本人の了解が得られなくても採用を取り消す方針で、最終的に5人が採用取り消しになる可能性もある。
自主退職、採用取り消しのどちらを選択しても臨時講師として勤務を続けることは可能で、自主退職の15人中10人、採用取り消しに応じている4人中3人の計13人が臨時講師を希望。うち12人は現在の所属校に残れるよう求めており、県教委は「本人の意思を尊重する」としている。現時点で臨時講師になるか明確な意思表示がない7人についても、希望があれば今後、臨時講師としての再雇用を検討するという。
県教委によると、自主退職の場合は公務員としての職歴が残るのに対し、採用取り消しは勤務実績自体がなくなるため、今後の再雇用時にも勤務歴を書けない。さらに、共済年金の加入歴も抹消されるため、年金の未納期間が生じるという。
註2:保護者、親戚、兄弟など、採用された教員が、その汚職に荷担した者が姻戚関係であることが犯罪なのでしょうか。
註3:もともと、教員採用試験は、ある程度の人数の募集があった場合、優秀な人材を集めるには、公平である方が集まりやすいから公募するということです。臨時講師を公募して試験を行いはしません。”つて”で探すことが多いのです。教員採用試験は、採用の1つの形態です。
参考:足立区の例
小学校教員(臨時的任用)募集
最終更新日 2008年8月28日
対象
◇資格◇
小学校全科の免許状を有し、昭和18年4月2日以降に出生した方
勤務内容および勤務条件
◇勤務場所◇
区内の小学校
◇採用予定日◇
9月中を予定
◇雇用期間◇
平成21年3月末まで
◇勤務内容◇
教科指導・学級担任・校務分掌など
◇勤務時間◇
8時15分から17時まで
報酬など
◇給与◇
大学卒 約239,500円
短大卒 約218,100円
※前歴がある場合は、一定の基準により加算されます。
※上記金額は、教員特別手当・調整額等を含みます。
◇その他◇
通勤手当、期末・勤勉手当別途支給あり
社会保険・年次有給休暇等あり
選考方法など
◇申込方法◇
担当部署まで電話でご連絡ください。
◇選考方法◇
書類選考及び学校での面接により決定します
註4:裁判で汚職が立証されてからです。立証もせずに怪しいだけで処分することはできません。ないとは、思いますが「この機会にやめさせたい教員を汚職で採用されたことにして処分してしまおう。」ということもやろうと思えばできます。公明正大に処分を行うには、公正な証拠の提示が必要です。証拠を調べるには、利害関係のない人の調査でないといけません。利害関係のある大分県教育委員会の調査では完全に信用することはできません。汚職に感づいていても何もしなかった人たちですから。曖昧な証拠だけで採用を取り消したり退職に追い込むのは、「汚職で点数を嵩上げして採用・・・ルール違反をして」とちょうど逆の行動です。「汚職が公になったので自分たちの立場を守るために、ルール違反をして、退職させてしまおう。」ということです。
H20.9.7
教員免許更新制度4
文科省メールマガジン(註1)に「教員免許を所有していても公立学校に関係ないのならば免許更新の必要がない」と言う意味のことが書かれています。これは、非常に重要な問題です。はじめ、自民党は「教員免許更新制は運転免許と同じだ。」と言っていました。しかし、運転免許はペーパードライバーでも免許更新します。「運転免許と同じ」という議論自体(註2)おかしいと思いますが、その自民党の言っていたことすら自民党は守っていないのです。これでは、自民党は詐欺師と言われても仕方がないです。以前のような健全な形での族議員(註3)の復活を望みます。
今回の教員免許更新制度は、正規教員差別法と言えます。すなわち、法の下の平等に反する(身分や地位に関係してはいけない)ということです。
もともと、「教員免許者の資質向上を謳ってていたはずです。もしそうならば、公立・私立校や塾で教えていない教員免許所有者に対しての方が厳しくしないといけないはずです。しかし、現実は、全く逆となっています。分かっているはずの現職に研修を義務づけ、教員でない者には、何ら研修を課しません。これでは、「教員免許社の資質向上なんて名目上で、免許更新講習を受けさせないで教員を首にしようとする悪質な免許法改正である。」と言わざるを得ません。また、現職の教員に対する差別法だとも言えます。くどく言います。その教員に資質がないというのならば、採用した教育委員会が教員免許とは無関係に首にすべきです。教育委員会は怠けてはいけません。また、「教員免許更新制度3」で述べたように、法の不遡及の原則にも反します。このような理由から、教員免許更新制度は、憲法違反(法の基本原則に反する)の法律だと考えられます。また、このようなことをしては、法治国家とも言えません。日本は、文明国であるべきなのに、文明国であることを放棄するような法律を作るとは情けない自民党(民主党も同罪)です。文明国であることを否定するような法律を作っておきながら「愛国心」とは笑止千万です。
現在の教育をよくするには、教員免許更新制度のような違法な法律に頼るのではなく、教科書の質の向上を行うべきです。教科書は、暗記することが主ではなく、様々な考え方ややり方があることを学習するような教科書にするべきです。そして、どのような順番で指導することが適切なのか研究するべきです。今のように、教科書にキャラクターを載せて喜んでいるような低俗な教科書ではダメなのです。公教育にふさわしい教科書にするべきです。そして、その教科書を使って、弾力的に教えることのできる教員研修を行えるようにするべきです。硬直化した大学教授の講義など聞く必要はありません。大学教授と学校との連携。つまり、大学と公立学校との連携や研究などを積極的に行うなど、大学の活性化が必要です。現在の教員の資質の低下の大きな原因は、大学の堕落に始まっています。昭和1桁生まれが大学生だった頃、講義に出席しなくても単位が取れてしまいました。これを放置してきたつけが今になって出てきたのです。学生が勉強しなくなったと言うことは、小中学校などの学級崩壊と同じことです。昭和1桁生まれは、それなりの教育をそれまでに受けてきたので、堕落まではしませんでしたが、その子供になるとだんだんとダメになってきました。そして、その孫の代で決定的に良くない状態になってきたのです。だから、大学の再建が急務なのです。文科省が大学の研究に制限を加えるような硬直的な体制は直ちに止めるべきです。大学は自由な研究が保証されなくてはなりません。
大学の活性化と同時に教員の資質向上を図っていく必要があります。そのためには、無駄な書類を減らし、研究のためのグループを作り、その成果に応じて、報奨金を払うような制度も必要かも知れません。無料で、質の向上のみを求めることは難しいことだからです。教育関係の世界にも売れるデータベースを作るのも面白いかも知れません。教育活性化のための投資が必要なのです。
本来資質向上は、自主的な内容の研修が必要です。それぞれの教員の能力や興味に応じた研修・研究です。免許更新とは関係のない話です。その研修の道筋を作るのが教育委員会の役目です。免許更新制度ではありません。
不的確教員はの排除という考えで、教員評価制度や免許更新制度を行おうとしています。筋違いもいいところです。どんな教員も、上手く授業を行いたいという願いがあります。しかし、現在は、教員が孤立化する方向で動いています。教員評価制度で、校長と教員個人の個人契約みたいな形にしています。教員は教員というチームで仕事をするべきです。そのチームを作るのが校長の役目です。教員同士がお互いに助け合う学校が素晴らしいのです。その態度は子供にも現れます。今のやり方を進めていけば、教員一人一人が孤立し、それと同時に、子供同士助け合わせる指導が少なくなり、自分さえ良ければよいという子供が増えます。そうすると、いじめがはびこるようになるのです。
世知がない制度は、必ず子供に反映されていきます。そのことを自民党はゆめゆめ忘れてはいけません。民主党憎し、教員組合憎しだけでは、うまく公教育を運営することはできません。
教育委員会がふさわしくない教員を解雇できないのは、教育委員会制度が機能していないからです。そして、教員の身分が市町村なのか県なのか曖昧な状態で放置されているからです。だから、市町村は県職員である教員は一歩退いて対応してしまうことになります。県職員である教員を県のような大きな単位では掌握しきれません。従って、教育委員会制度を見直す必要があるということになります。今後考えたり調べていきたいと思います。
話を戻しましょう。地方公務員法に反して、教員を解雇するというのならば、公務員であってもストライキ権などの労働基本権を付与してから行うべきことです。そうすれば、法の下の平等は、守られたことになります。このようなやり方は、米国を中心とた占領軍が銃口を向けて大日本帝国憲法を日本国憲法に変えさせたやり方と同じです。法治国家のルールを守るべきです。不的確なのか、その教員に対する指導が甘かったのかそこが難しい問題なのです。
つぎに、サービス残業です。サービス残業などの違法労働行為を厳重に取り締まるべきです。職務専念義務(註4)は、勤務時間内に限定されるべきなのに、実質上勤務時間外までも拘束しています。勤務時間外に教員とは別の仕事をしていては、残業命令(註5)ができないという意味でしょうか。一般の企業でも職務専念義務を課しているところが多くあります。職務専念義務は、終身雇用制度の元での規則です。終身雇用制度に反する行為をするのならば、職務専念義務は勤務時間内に限るべきです。雇用者は残業手当を出すにしても、多くの残業を従業員に課してはならないと思います。つまり、解雇の可能性がある以上、他の職業に変わることができるように自己研修などの準備する時間を確保できるようにすべきです。鈴木政洋的には、サービス残業OKですが、終身雇用制度が確保され、老後の心配もないという条件付です。多くの仕事人は同じように考えているのではないでしょうか。
教員免許更新制度のような終身雇用制度を外すような法律を作ったのだから、勤務時間外に他の仕事に就くことを妨げてはいけないと思います。個人的には、終身雇用制度は良い方法だと思います。研修制度が充実して、その個人も研修に専念していることが必要です。労働者の質が向上することは、公務員に限らず、一般の企業にも言えることです。世界との競争に勝ち抜いていくためには、労働者の質の向上が必須条件です。低賃金労働とサービス残業に依存している企業は、淘汰されるべきです。これらに依存している企業は、日本に後進国を持ち込んでいるのです。後進国が持ち込まれれば、日本の治安が不安定になります。日本人としてのアイデンティティや誇りが失われます。
その労働者の質の向上は、公教育に始まり、社会教育・社内教育に受け継がれていくのです。経団連を中心として、社内教育を怠るようになって来た社長のみなさん。このままでは、会社そのものをつぶしてしまいますよ。それは、1年、2年後のことではありません。10年、20年後のことです。このまま、思いつきの評価制度を会社や公務員に押しつけていけば、世知がない会社を作るだけです。よい思いつきをして、その思いつきを生かしていくことのできる会社や役所、学校を作っていきましょう。
****************************************
註1:初中教育ニュース(初等中等教育局メールマガジン)第90号 H20.6.12
□【シリーズ】教員免許更新制がはじまります!(第3回)
〔教職員課教員免許企画室〕
シリーズ第3回目となる今回のテーマは「免許状更新講習の受講義務のある方と受講できる方」です。
前回は、旧免許状所持者の方々には修了確認期限があることについて触れましたが、修了確認期限が割り振られた現職教員などの方々には、更新講習の受講義務があります。
受講義務のある方々を具体的に上げると以下のとおりになります。
(1)現職教員
→ 国公私立の幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校に勤務されている、校長・園長、副校長・副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師(臨時講師、非常勤講師も含む。)の職にある方々
(2)教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う者
→ 教育委員会の教育次長や指導事務を所管する課長、教育センターの所長、次長、研修部長などを含みます。
(3)(2)に準ずる者として免許管理者(都道府県教育委員会)が定める者
→ 都道府県又は市町村教育委員会からの要請に応じて退職したのち、国立大学法人の役職員や独立行政法人の役職員となっている方、あるいは、学校を設置している学校法人の理事などを想定していますが、具体的には教育委員会規則などで定められることになります。
(4)文部科学大臣が別に定める者
→ 文部科学省の視学官、教科書調査官、教科調査官などを想定していますが、具体的には告示などで定められることになります。
更新講習の受講義務のある方が、修了確認期限の2ヶ月前までに、更新講習を受講・修了し、修了確認を行わなかった場合には、免許状の効力が失われてしまいます(失効)。効力がなくなってしまった免許状については、免許管理者に返納する必要があります。
再び免許状の授与を受けるためには、更新講習の受講・修了を行い、その修了証明書を添えて、免許管理者に申請をしなければなりません。再び免許状が交付されなければ、教育職員として教壇に立つことができません。
そのため、前回、ご説明しました「修了確認期限」について、みなさんご自身でご確認いただき、定められた期間内に更新講習を受講していただかないと、たいへんなことになりますので、うっかり失効してしまうことのないよう、くれぐれもご注意をお願いします。なお、更新講習の受講義務者の中には、免除申請をすることで、更新講習の受講が免除される場合があります。この免除対象者については、回を改めてご説明します。
一方、更新講習の受講義務はありませんが、更新講習を受講することが可能
な方々(受講対象者)も定められています。
受講対象者の方々を具体的にあげると以下のとおりとなります。
(1)現職教員(受講義務者でもあります。)
(2)実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員
(3)教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育社会教育に関する指導等を行う者(受講義務者でもあります。)
(4)(3)に準ずる者として免許管理者が定める者
→ 更新講習の受講義務者の場合と同様に、具体的には、教育委員会規則などで定められることになります。
(5)文部科学大臣が別に定める者
→ 更新講習の受講義務者の場合と同様に、具体的には、告示などで定められることになります。
また、今後教員になる可能性が高い者として
(6)教員採用内定者
(7)教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者
(8)過去に教員として勤務した経験のある者
(9)認定こども園又は幼稚園を設置している者が設置する保育所などで勤務
している場合に限り、教員免許状を有している保育士についても、更新講習を受講することが可能です。
なお、更新講習の受講義務のない方が、更新講習を受講・修了・修了確認の申請をせずに修了確認期限を経過しても、免許状そのものは失効しませんし、免許状を返納する必要もありません。
ただし、教育職員として教壇に立つ際には、更新講習を受講・修了し、免許管理者の確認を受けておく必要があります。
註2:平成19年度後半「教員免許更新制度2」、平成18年度後半「教員免許更新制度」参照
註3:族議員は、その癒着して甘い汁をすることが問題です。しかし、族議員は勉強会をもち、徹底的にその分野の専門家になっていました。そのれは、非常によいことなのです。だからこそ、政治家が官僚をコントロールすることができたのです。政治家が主役となれたのです。今のように、自民党すら自分の専門の勉強が不足しています。だから、官僚も納得して指示に従わないのです。指示に従う振りをして実際には自分たちの利益のみを計るのです。政治家は勉強をしていないので、官僚は政治家を信じれなくなっています。そのために、本来国のために働く官僚が自分自身のためにしか働かない傾向が強まったのです。これを打開するためには、族議員を復活させるべきです。民主党は、次の内閣○○大臣なんて格好をつけていますが、勉強何てしていません。自民党から政権を奪うことのみ考え、国のためを考えていません。
註4:終身雇用制度が教員に対して守られないというのならば、別の職業に就くための保証制度が必要です。即ち、勤務時間以外は拘束しないと言うことです。万やむを得ない場合のみ残業手当を出したうえ残業させるべきです。基本的には、勤務時間以外に何をしようと法律に違反しない限り自由であるべきです。例えば、勤務時間外はどんな職業についても良いと言うことです。また、教員評価制度で、教員を競争させようとすることは、完全な間違いではありませんが、サービス残業を放置したままでは、公正な競争が行われているとは言えません。つまり、管理職がサービス残業をする職員を優遇すれば、ますます法律が守られないという事態になるからです。従って、サービス残業は、厳しく取り締まる必要があります。
註5:残業命令は基本的にはありません。キャンプなどの学校行事の時には、命令がなされることもありますが、ほとんどの場合、勤務時間にはやりきれない仕事を、計画的に勤務時間内に行うことになっています。
H20.6.22
教員は裁判員になってはいけない。
教員が裁判員になった場合、様々な問題が生じると思います。特に、死刑が想定されるような事件の裁判の場合、厳しい判決でも、甘い判決でも、慣例上の判決でも、それに文句をつける人たちは必ずいるものです。そして、裁判員になったことは、職場では分かってしまいます。そして、職場から保護者に漏れる可能性がかなり高いことになります。そして、裁判の結果が新聞やテレビなどのマスメディアで報道されないのならばともかく、報道されることがほとんどです。そうすると、保護者が「その教員がどんな判断をしたか予想できる場合があります。予想できなくても詮索好きな人たちもいます。そして、勝手な噂が流れてしまうこともあります。そして、裁判員になったことでその教員が信頼を失ってしまうこともあり得ます。
教員に限らず、そのような状態になってしまう職業があると思います。そのようにならないための配慮がないのに裁判員制度を強行するのは、裁判所が世の中の敵になると言うことです。裁判所の信頼をも失いかねないことになります。裁判所を信頼しない国民を裁判員制度で作ってしまってはよくないのです。
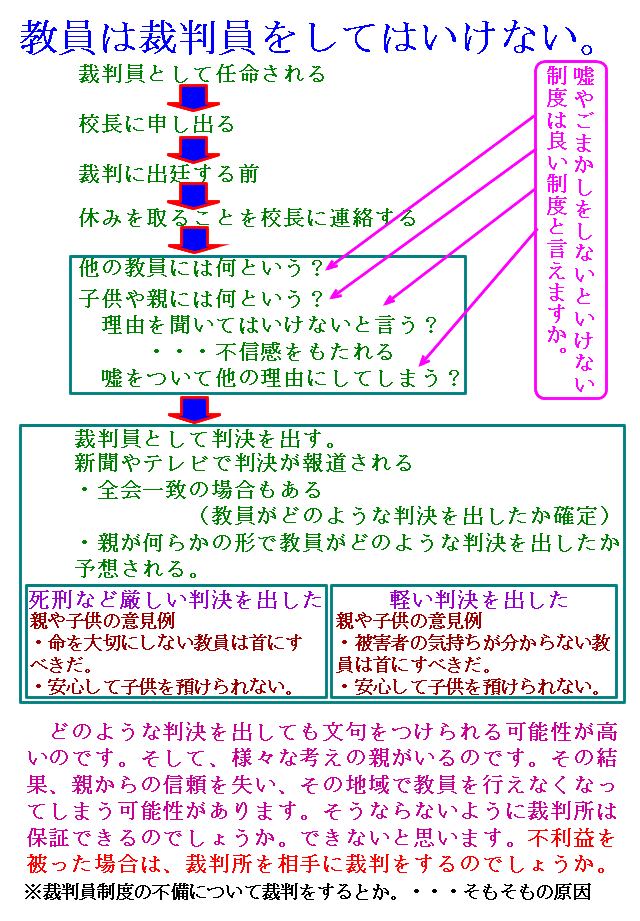
H20.6.15
英語を3年生から(教育再生会議)について
教育再生会議が、「英語を小学校3年生から・・・5000校をモデル校に 年間35時間の英語の授業を行う。」と 平成205月26日に発表しました。
教育再生会議だから、国民全体のためだと思ってはいけません。実態を考えてみて下さい。教育再生ではなく、一部のエリートのための英才教育を全ての子供に行ってしまおうということです。つまり、小学校3年生から英語の授業を行うということです。エリートの利己主義(あるいは、公教育の私物化)としか言いようがありません。20年くらい前の3年生だったならば、カタカナ言葉も覚えて、国語力も適切についていました。しかし、今の3年生は、エリートの子供は別にして、カタカナ言葉もしっかり覚えていない子供もいる状態です。そして、普通の子供ですら「筆算の足し算のやり方は分かっていても、1桁同士の和の計算を間違えている子供もいます。更に、カタカナを間違えて書いてしまう子もいます。助詞の”は”を”わ”と書いてしまう。更に、集中して学習できない子もいます。」と言うような状態で英語を3年生から行う必要性があるのでしょうか。却って学習の効率が下がるように思えます。
もし、小学生から英語を学ばせたいのならば、私立のエリート専門校(あるいは、学級 註1)で行うべきです。英語を学習させるレディネスのない子供達に英語を教えるのは、能率が悪いし、英語を教えるくらいなら国語をきちんと教えた方が、中学での英語学習に弾みをつけることができます。国語力を犠牲にして英語の学習をしてしまっては、国民全体のためになりません。主権在民とは、「日本国民全体に権利がある」と言うことです。つまり、「経団連のメンバーの子供の権利ばかり有利に取りは計ってはいけない」のです。エリートだけのために公教育があるのではありません。国民全体のためにあるということを忘れてはならないのです。小学校3年生から英語を指導しては、不利になる子供の方が多いのです。結果的に、エリートが通常の子供の学習権を奪っていることになります。憲法にあるように、教育はその能力に応じて教育を受ける権利があるのです。エリートはエリートにふさわしい教育を、そして、通常の子供には通常の教育を、特別なハンディーのある子供には、それにふさわしい教育を受ける権利があるのです。そして、どの階層も日本を豊かにする一端を担い、豊かさを甘受する権利を有するのです。
註1:エリート教育が必要だと鈴木政洋は、考えています。日本のエリートは紳士らしく、武士道精神を持って育てるべきです。日本は、エリートのモラルが低いために様々な社会問題が起こっているのです。
H20.6.8