司法においては、「法の下の平等」が重要です。そして、裁判所は「法の番人」と言われるように、法の理念に基づいてその訴訟を判断しなくてはなりません。けして、新聞の報道や被告の身分や立場によって判決が左右されてはならないのです。また、裁判官の個人的な正義感で判決を出してはいけないのです。あくまで「法律を正しく解釈すること」が大切なのです。司法を人を罰することが目的ではないのです。法に照らし合わせて正当かどうかが大切なのです。
法が整備されていないために「世間がどう考えても悪党で、刑が軽すぎる。」と言う場合が時折あります。しかし、司法は法に照らし合わせて正しいかが大切なので、法を超えたような法の解釈をして、人を罰してはいけないのです。もし、「世間が刑が軽すぎる」と考えれば、「立法府に働きかけて法律を変え、次の同様な事件から対処する」べきなのです。それが「近代国家」あるいは「法治国家」としての正しい道なのです。
「新聞で報道されたら刑が重くなった」と言うのでは法治国家とは言えないのです。
マスメディアに左右されない司法が平成維新には必要です。
〈平成維新鈴木政洋〉H19.6.3
JR東海が認知症のお年寄りをひき殺して、殺された側の家族に賠償を要求する(註1)という異常な事態が起こっています。従来の日本では考えられなかったことです。鉄道会社が、殺された側に賠償することはなかったようですが、殺された側に賠償を要求することはあり得ませんでした。小泉首相以来、グローバル化によって、人情よりも拝金主義、契約主義が蔓延しました。日本人の心が失われつつあります。日本人の心があったからこそ、物作りが世界に冠たるものになったのです。
JR東海と言えば、公共交通機関です。公共交通機関が、これから増え続けるであろう認知症の対策をせずに、お年寄りをひき殺し、更に賠償を殺された側に求めるという愚行を、二度と行わないでいただきたいです。
昔は、認知症のお年寄りは、老人ホームに預けれて、安全に生活できました。しかし、お年寄りが増えて、民間に任せられるようになり、施設の数が少ないために自宅で認知症患者をみなくてはならなくなりました。認知症患者が家族に出ると、家族が崩壊してしまうことになります。それが、狙いでは無いかと邪推してしまいます。
こうならないためには、拝金主義を廃します。公共交通機関の会社から、投機家を閉め出します。そして、安全を願う投資家だけに、投資してもらいます。そうすれば、ある程度余剰金があるようにします。そうすれば、このような事故で、不正義な賠償を求めるようなことは無くなるはずです。そして、安全施設も作る余裕も出来ます。投機家が、公共交通機関の会社に、配当金をどんどん要求すると、会社に余裕が無くなります。そうすると、道徳に反するような行動を取ってしまうのです。日本から、投機家を追い出すことが、日本の心を公共交通機関の会社に取り戻させます。投機家は、日本人の心を荒(すさ)ませます。拝金主義を横行させ、お金のために魂を売ります。
日本人の心には、投機家、グローバル化は必要ありません。むしろ、害毒です。
註1:認知症JR事故、家族に監督義務なし 最高裁で逆転判決 市川美亜子2016年3月1日20時55分朝日新聞より引用
愛知県大府市で2007年、認知症で徘徊(はいかい)中の男性(当時91)が列車にはねられて死亡した事故をめぐり、JR東海が家族に約720万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は1日、介護する家族に賠償責任があるかは生活状況などを総合的に考慮して決めるべきだとする初めての判断を示した。
民法714条は、重い認知症の人のように責任能力がない人の賠償責任を「監督義務者」が負うと定めており、家族が義務者に当たるのかが争われた。JR東海は、男性と同居して介護を担っていた妻と、当時横浜市に住みながら男性の介護に関わってきた長男に賠償を求めた。
民法の別の規定は「夫婦には互いに協力する義務がある」とも定めるが、最高裁は「夫婦の扶助の義務は抽象的なものだ」として妻の監督義務を否定。長男についても監督義務者に当たる法的根拠はないとした。
一方で、監督義務者に当たらなくても、日常生活での関わり方によっては、家族が「監督義務者に準じる立場」として責任を負う場合もあると指摘。生活状況や介護の実態などを総合的に考慮して判断すべきだ、との基準を初めて示した。
今回のケースにあてはめると、妻は当時85歳で要介護1の認定を受けていたほか、長男は横浜在住で20年近く同居していなかったことなどから「準じる立場」にも該当しないとした。
結論は5人の裁判官の全員一致。ただ、うち2人は長男は「監督義務者に準じる立場」に当たるが、義務を怠らなかったため責任は免れるとの意見を述べた。
一審・名古屋地裁判決は妻と長男に請求全額の賠償を命じ、二審・名古屋高裁判決は妻に約360万円の賠償を命じていた。
JR東海は「最高裁の判断なので、真摯(しんし)に受け止める」とのコメントを出した。(市川美亜子)
遺族「施錠・監禁でいいのか」 認知症で徘徊事故訴訟2016年2月3日21時23分朝日新聞より引用
愛知県大府市で2007年、認知症で徘徊中の男性(当時91)が列車にはねられ死亡した事故で、JR東海が遺族に約720万円の損害賠償を求めた訴訟の弁論が2日、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)で開かれた。この日で結審し、判決は3月1日。認知症の高齢者が起こした事故の賠償責任を、介護してきた家族が負うべきかについて、最高裁が初めての判断を示す。
「一、二審の判決は、認知症の人や家族にとって、あってはならない内容。最高裁には、認知症の人たちの実情や社会の流れを理解した、思いやりのある判決をお願いします」。長男(65)は弁論を前に、そうコメントを寄せた。
JR東海から「監督義務者だ」と訴えられた長男は2年前に会社を退職。昨年2月に横浜市から愛知県大府市の実家近くに戻った。今は、父が営んでいた不動産業を継ぎ、母親(93)や妻(63)と生活している。
事故当時、妻は介護のため、父の自宅近くに住み込んでいた。妻が片付けのために玄関先に出て、そばにいた母もまどろんだ一瞬の間に、父は自宅を出た。
小銭も持たず、自宅近くのJR大府駅の改札を抜け、一駅先の共和駅まで列車に乗って移動。駅のプラットホーム端にある階段から線路に下りたとみられ、列車にはねられた。階段前には柵があったが、鍵のかかっていない扉から線路内に下りることができた。
「どうして大府駅の駅員は、父を入場させたのか。なぜ共和駅の駅員は、一般の乗客と逆方向に向かう父を呼び止めてくれなかったのか」。家族は裁判で疑問を投げかけた。
父は事故に遭った際、お気に入りだったニューヨーク・ヤンキースの帽子をかぶっていた。帽子にも衣服にも、妻が、連絡先を記した布を縫い付けていた。この名札をもとに、警察は家族に一報を入れた。
事故の約10カ月前、認知症が重くなり「要介護4」の認定を受けた際に、家族は一度は特別養護老人ホームへの入所も考えた。だが、結局は在宅介護を選んだ。「父は住み慣れた家で生き生きと毎日を過ごしていました」。長男は振り返る。一瞬のすきなく監視しようとすれば、施錠・監禁や施設入居しか残されない。それでいいのか――。そんな思いが、事故からの8年を支えてきたという。(斉藤佑介、市川美亜子、河原田慎一)
■介護家族、訴訟を注視
「認知症の人と家族の会」(本部・京都市)副代表理事の田部井康夫さん(68)は弁論を傍聴した後、「最高裁では、介護する家族が免責される判決を望みます。これまでの判決はあまりに酷です」と語った。同会は一、二審の判決後に出した見解で「認知症の人の実態をまったく理解していない」などとし、判決を「時代遅れ」と批判している。
多くの介護家族がこの訴訟に自分を重ね、注目する。一人暮らしの認知症の義父を支えるために仕事を辞めた千葉県の女性(48)は「介護で苦労した家族だけが責任を負わされた。判決が最高裁で変わらなかったら、私も介護から逃げ出したい」と話す。
家族の責任は、いま介護中の人だけにかかわるものではない。認知症の人は2012年に高齢者の7人に1人で、25年には5人に1人になる。徘徊(はいかい)中の事故のほか、車の事故や火の不始末などのトラブルの増加も避けられず、誰もが認知症と無縁でいられなくなる。そんな社会に最高裁の判断が与える影響は大きい。
一方、徘徊がからむ事故などの損害にどう備え、どう賠償するのかも、この訴訟が投げかける問題だ。
一般に、個人ができる対策として民間の「個人賠償責任保険」がある。火災保険や自動車保険などの特約として付ける場合が多い。日常生活でけがをさせたり、商品を壊したりして賠償を求められたとき保険金がでる。ただ一定の条件があり、すべての事故がカバーされるわけではない。
介護関係者からは、個人の責任で賠償するのではなく、国が関わる公的な救済制度の創設を求める意見も出ている。(編集委員・清川卓史、友野賀世)
H28.3.6
反日的な最高裁判事が、1票の格差が現在違憲状態にあると判決(註1)を出しました。自民党と公明党は、「10増10減案」を提案(註2)しました。これは、鳥取と島根から、議員2名、徳島と高知から議員2名ということで、このうち、2県が代表の議員が選ばれない可能性があります。これは、単に地方軽視という言い方では済まされません。地方自治制度を否定していることになります。つまり、自民党の中の地方自治を否定し、道州制に変えようとする連中の策略では無いかと予想しています。この人たちは、投機家と綱がつている議員では内で使用か。投機家は、日本を道州制にし、地方の同州に、法人税減税など投機先の会社に有利な条件の道州を作るために、道州制を推進しようとしているのです。
註1: 1票の格差:全国で提訴 衆院選、無効求め 全295小選挙区で原告毎日新聞より引用 2014年12月16日
最高裁が1票の格差を「違憲状態」と判断したにもかかわらず、選挙区割りの抜本見直しがされないまま実施された今回の衆院選は法の下の平等を定めた憲法に反するとして、「一人一票実現国民会議」を主宰する升永英俊弁護士のグループが15日、全国8高裁・6高裁支部に選挙無効を求めて一斉提訴した。今回は初めて全295選挙区で原告を立てた。【川名壮志】
今回衆院選の小選挙区では、当日有権者数が最多の東京1区と最少の宮城5区の間で2・13倍の最大格差が生じており、別のグループも同日、広島高裁に同様の訴訟を起こした。今後、東京高裁でも提訴する方針。
「一人一票」のグループは訴状で、2009年の衆院選に対する11年3月の最高裁判決が「違憲状態」と判断して以降、国会が抜本的な制度改革を怠ったまま12年、14年と2度の総選挙を実施したと強調。「11年判決から約3年9カ月が経過し、違憲・無効と判断するのに十分な期間が過ぎている」と主張している。違憲状態の早期解消が必要だとして、公職選挙法の「100日裁判」規定に基づく早期の判決も求めた。
提訴後、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見した升永弁護士は「司法は今度こそ違憲・無効判決を出すべきだ」と訴えた。伊藤真弁護士は「1票の価値が同一にならないまま選挙が強行された。民意を問えたとは言えず、フェアな選挙ではなかった」と話した。
公選法の規定により、選挙無効訴訟は高裁が1審となる。
衆院選の「1票の格差」について最高裁は、2009年と12年の選挙を2回連続で「違憲状態」と判断し、選挙制度の抜本見直しを国会に促し続けてきた。だが、前回選挙後も明確な抜本改革は進んでいない。是正を放置した国会の対応を司法がどう判断するか。まずは各高裁・支部の判断が注目される。
09年選挙に対する11年3月の最高裁判決は、47都道府県に最初に1議席ずつ割り振って残りを人口比例で配分する「1人別枠方式」の廃止を求めた。国会は12年選挙の直前、同方式の規定を削除し、小選挙区を「0増5減」する関連法を成立させたが、区割り変更が間に合わないまま12年12月に衆院選が行われた。この12年選挙も最高裁は「違憲状態」と判断している。
今回は「0増5減」を受けて見直された区割りで選挙が実施されたが、格差は依然として2倍を超えており、1人別枠方式も実質的には維持されている。弁護士グループは「小手先の措置」と批判を強めている。
12年選挙を巡る訴訟では、提訴から100日以内に高裁・高裁支部の判断が示された。今回も来春に判決が集中する可能性がある。
1票の格差・大阪高裁判決要旨(2009年12月28日15時58分 読売新聞より引用)
判決の要旨は以下の通り。
1 本件選挙においては、小選挙区選出議員1人当たりの有権者数の最大格差は、最少選挙区を1とすると、平成20年9月2日現在で2・255倍であり、投票当日現在で2・304倍であったと認められる。
2 憲法に定められた選挙権は、多年にわたる人類の努力と民主政治の歴史的発展の成果の現れで、議会制民主主義の根幹であり、その歴史的発展を通じ一貫して追求されてきたのは、投票の場面で国民は完全に平等視されるという理念で、憲法は選挙権に関し徹底した平等化を志向し、投票の価値の平等をも要求すると解される。
その前提の下で、選挙制度の仕組みの決定は、国会の合理的な裁量に委ねられているが、選挙制度自体以外に関する政策を考慮に入れるべきではない。いわゆる1人別枠方式は、従来の著しい格差を改善させる方式として、いわば過渡期の改善策としてそれなりの合理性と実効性があったが、国会議員を地域代表と理解するもので、全国民の代表者とされている憲法43条1項の趣旨にも反しており、このことは、遅くとも本件選挙時までには明らかになっていたと認められる。
3 近時たびたび投票行動により政治情勢が大きく変化し得ることが目の当たりに経験され、格差が2倍に達するような事態は、大多数の国民の視点から耐え難い国民の間の不平等と感じられてきており、客観的にも著しい不平等と評価される。
4 本件では、2倍を超える格差があったことが歴然としており、この格差は、1人別枠方式という憲法の趣旨に反するに至った選挙区割りの選挙方式により生じたと認められるから、本件選挙は違法との評価を免れない。
ただし、本件選挙を無効とした場合、公の利益に著しい障害が生じることは明らかで、原告の受ける損害等を考慮しても公共の福祉に適合しないと認められるから、行政事件訴訟法31条1項前段の趣旨に準じて、原告の請求を棄却する。
註2:参院選挙改革:「10増10減」自民合意、成立へ毎日新聞より引用 2015年07月09日 20時27分
自民党は9日、国会内で参院議員総会を開き、「1票の格差」を是正する参院選挙制度改革に関し、有権者数の少ない都道府県選挙区を統合する「合区」を受け入れ、定数を「10増10減」する案を決定した。同案を提案した維新、次世代、元気、改革の野党4会派と自民の議席を合わせると、参院の過半数(122)に達しており、公職選挙法改正案など関連法案は今国会で成立する見通し。成立すれば来年夏の参院選から導入される。参院選の選挙区が合区されるのは旧地方区時代を含めて初めて。
参院自民党の溝手顕正会長は同日の議員総会で、10増10減案を執行部案として提示。合区対象となる選挙区の議員から「人口減という理由だけで切り捨てるのか」など反対意見が相次いだが、最終的に溝手氏に対応を一任することを了承した。これを受け、参院自民執行部と4会派が会談し、10増10減案の実現を目指すことで合意した。
溝手氏は総会で「党議拘束をかけたい」との考えを示した。それでも、合区対象の議員は総会後も「地方軽視だ。地元の了解が得られるまで反対を貫く」(鳥取・舞立昇治氏)と反発を続けている。ただ、参院で114議席の自民党から造反が出ても、野党4会派(計26議席)の協力を得れば参院でも可決する見通しだ。
10増10減案は、いずれも定数計4の「鳥取・島根」と「徳島・高知」を合区して定数2(改選1)の2選挙区とする。また、北海道▽東京▽愛知▽兵庫▽福岡の5選挙区の定数を各2増し、宮城▽新潟▽長野の3選挙区を各2減する。4会派の試算では、2013年参院選で4.77倍あった最大格差は2.974倍まで縮小し、1947年の第1回参院選時の格差2.62倍に近づく。
一方、公明党の魚住裕一郎参院議員会長は9日、10増10減案について「(1票の格差が)3倍だと違憲だ」と批判。最大格差を2倍以内にする「20県10合区案」を、民主党と共同提出する考えを改めて表明した。ただし、民主、公明両党では過半数に届かない。採決では、与党内で自民、公明両党の対応が分かれることになるが、魚住氏は、連立政権への影響は否定した。【高橋克哉、佐藤慶】
◇参院選挙制度改革「10増10減案」◇
選挙区 現行定数 見直し後
北 海 道 4 6
東 京 10 12
愛 知 6 8
兵 庫 4 6
福 岡 4 6
宮 城 4 2
新 潟 4 2
長 野 4 2
鳥取・島根 計4 2
徳島・高知 計4 2
H27.7.11
最近、最高裁のとんでもない判決が続いています。新潟の拉致監禁事件9年(註1)では、法律がこのような長期にわたる監禁事件を想定しておらず、未成年者略取罪、逮捕・監禁致傷罪では、最高10年の刑になっています。ところが、最高裁裁判官が法律を越え、将来的に革命を起こしたい裁判官はなんと、下着の窃盗罪の被害額は2464円で、既に弁償もされています。確かに、下着を監禁した少女のための物ですが、窃盗が行われても行われなくても、監禁に影響があったとは思えません。このような窃盗事件の場合、通常だと、金額も少なく弁償もされているので、不起訴処分となる案件です。それを併合罪にするというのは、最高裁裁判官による法律を越えた判断です。最高裁裁判官によるリンチです。裁判官は法の番人であるはずです。それにもかかわらず、リンチをしました。裁判官として失格です。ところが、このとんでもない裁判官を辞めさせることが出来ないのです。民主主義を否定する裁判官がいても罷免できないのです。こんなことでよいのでしょうか。裁判官がとんでもない人間だったとき、国民審査(註2)で罷免出来るはずなのですが、現実的には罷免されることはありません。現在ほとんどが60歳以上でで最高裁裁判官になっていて、その10年目以降の衆議院選挙にしか国民審査がないので、現実的に、罷免された最高裁判所判事は1人もいません。ついに、最高裁判所判事は、立法府よりも上になりました。行政府よりも上になりました。そして、そのような横暴な判決を出しても何の罰もありません。それでは、民主主義を守ることは出来ません。日本転覆を謀る最高裁判事は、「憲法判断=判例(法律)」と考えています。これは、裁判官が立法を行っていると同じ意味です。これでは、三権分立に反します。何らかの最高裁裁判官がとんでもない判決を出した時、罷免させる手段が日本国民には必要です。
次に、裁判所が選挙に干渉しました。もっと言えば、裁判所が政治に介入したのです。それは、1票の格差(註3)の問題です。昔は、1対5が違憲状態と言っていたのが、だんだん1対4.4、キリスト紀元2009年には、1対2が違憲状態であると最高裁の判事が判断しました。違憲状態だが、選挙結果は支持しました。実はこの判決は良識があるように見えて、実は地雷になっていたのです。キリスト紀元2013年(註2)の広島高裁で、期限付ですが、選挙無効判決を出しました。これは、2009年の最高裁判決がなければ出来なかったことです。この最高裁判決が、高裁まで、政治介入できるようにしたのです。1裁判官が、1票の格差の解釈を時代と共に厳しく勝手に解釈し始めたのです。厳しくして、気に入らない選挙を否定しても良いことにしたのです。これは、完全に司法の政治介入です。三権分立に対する挑戦であり、違反です。最高裁の判事がこの行動が、今回の「最高裁で婚外子と嫡子と差別するのは不当」という判決を出しました。最高裁判決では、日本の家族に対する考えが変わり、様々な家族が容認されてきたから、時代に合わせたのだと言い放ったのです。憲法判断という形をとって、政治家が作った民法を否定しました。日本文化を否定する判決につながったのです。これは、三権分立に反します。しかも、その目的が非常に怪しいのです。最高裁の裁判官は、日本の共産主義革命の1歩だと考えていると疑います。最高裁の裁判官は、日本の家族制度否定したいのです。その家族制度の最たるものが、天皇を頂点とする君主国家。巨大な家族制度の日本国家なのです。その日本の家族制度を破壊するのが共産主義革命を狙っている革命家なのです。その共産主義革命を狙っていると、日本の最高裁裁判官がそうではないかと鈴木政洋は疑います。民主党菅直人首相が北朝鮮の傀儡政権のような行動をとりました。その一連の動きの中で、今回の「最高裁で婚外子と嫡子と差別するのは不当」という判決を考えるべきです。
平成25年9月4日、「最高裁で婚外子と嫡子と差別するのは不当」という日本の伝統的な家族に対する考えを否定する反日判決(註4)が出ました。家族として協力したり、助け合ったりしてきた子供と不倫相手の子供と平等にするのは、家族は意味が無いと言っているのと同じです。日本が安定しているのは家族制度がよいからです。現在、家族制度が崩壊しつつあるため、子供の精神の不安定化や核家族で老人の孤独死が起きたりしています。最高裁で、「最高裁で婚外子と嫡子と差別するのは不当」という判決を出すのは、さらに、崩れ始めた日本の家族制度を破壊し、家庭が不安定化し、子供の精神状態が不安定します。その子供が成人になっても精神が不安定化し、自殺が増え、殺人犯が増え、老人に対する詐欺事件が増えたり、家庭の不安定化によって様々な問題や犯罪が増えていきます。最高裁の裁判官が、犯罪を増長する行為を行って良いものでしょうか。日本をよくするための最高裁裁判官の筈なのに、日本を破壊しようとしています。現在の最高裁の判事は、問題です。更に言えば、もし、婚外子の子供が中共の国民だったらどうでしょうか。偽装日本人孤児で、日本にやってきて中共の女性が、日本人男性と結婚をし、実は女性には、中共に8人子供がいたとします。もちろん、日本人男性は女性に子供がいたことは知らなかったとします。しかし、今回の判決に従えば、日本人の夫が死亡した場合、中共に在住している中共にいる子供(黒子も含め:黒子とは国籍のない子供)にも遺産が日本人の子供と平等に分けられることになります。こんなことが合っても良いのでしょうか。しかも、その中共にいる8人の子供は、その結婚した中共の女性とは関係の無い財産目当ての子供であった可能性だってあります。日本人の財産を中共に奪われるのです。
まず、憲法は誰のためにあるのでしょうか。日本国民のためです。日本国憲法がGHQ憲法であることを忘れてはなりません。日本の裁判官は全て、現在の日本国憲法が国際法(戦争に勝ってもその国の内政干渉してはいけない)に違反して作られたことを忘れてはなりません。それが、法の番人である裁判官の役目です。誰であろうと、強盗に強制された契約書が無効であるのと同様に、軍事的に脅されて作られた憲法が無効であることは、裁判官が理解しないといけないことです。現在の日本国憲法が無効であることが理解できない裁判官は裁判官になってはなりません。もちろん、裁判官が直ちに日本国憲法を否定することは出来ませんが、そのことを頭に置いた判決を出すべきなのです。だからこそ、昭和中期までは、自衛隊は違憲であるという判決は出なかったのです。自衛隊が違憲だという判決を出した裁判官は全員、法律を理解していないという理由で、裁判官を辞職するべきです。
註1:新潟少女監禁事件(ウィキペディアより引用)
新潟少女監禁事件(にいがたしょうじょかんきんじけん)は、2000年1月28日、新潟県柏崎市の加害者宅にて発見・保護された女性が、9年2ヶ月もの長期間の監禁をされていた誘拐事件。
2000年1月28日、新潟県柏崎市の加害者宅に別件(母親への暴力)で訪れた保健所職員が、中にいた女性を発見・保護に至り、発覚した。
女性は小学校4年生だった1990年11月13日、新潟県三条市で下校途中に行方不明になっていた。実に9年2ヶ月に及ぶ誘拐監禁事件であり、社会に多大な衝撃を与えた。保護されたとき、被害者の女性は19歳で、PTSDと診断され、監禁生活の影響で、同年代の女性に比べて運動能力も著しく低下していたが、後に自動車を運転できるほどにまで回復し、引き続き療養しながら生活を送っている。
加害者(犯行当時28歳)の容疑は当初、未成年者略取罪、逮捕・監禁致傷罪であった。これら2つの容疑については観念的競合の考え方から当時の刑罰規定では監禁致傷罪の懲役10年が上限になるとされたが、地裁判決では「犯行は法が想定していた刑期をはるかに越えた最悪のもの」と認定されるなど、罪刑法定主義の観点から刑罰の上限の問題が浮上した。検察は監禁致傷罪以外に、更に別件である窃盗罪でも立件したが、監禁致傷罪と窃盗罪を併せた併合罪の処理が争点となり、最高裁まで争われた。また、検察側は論告で「未決勾留日数を1日でも算出すべきではない」として、長期服役させる意図を明白にしていた(判決では未決勾留日数は算出された)。男は懲役14年が確定し、服役中。
2004年の法改正により、逮捕監禁致傷罪の上限は懲役15年となっている。
裁判の争点
当時の監禁致傷罪(221条)の最高刑は懲役10年であり、窃盗罪(235条)もまた懲役10年であった。そして、併合罪(45条)は47条で「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。」と定めている。そうすると形式的には懲役15年の枠内で自由に量刑が出来そうである。
ただ、枠内で自由に量刑を定められるとすれば、普通なら不起訴になる軽微な犯罪を併合罪として起訴することで法定の最高刑を簡単に超えられてしまうとも考えられる。実際、本件で追起訴された窃盗罪の被害額は2464円相当であり、弁償もされていたので普通は起訴されることのない犯罪である。ただし、別に立件された窃盗罪は監禁されていた少女の衣類用に盗んだものであり、監禁事件と全く無縁ではない。
そこで、併合罪がいわゆる併科主義による過酷な結果の回避という趣旨を持つことを前提とした上で、個別の罪の量刑を定めて合算すべきなのか(高裁)、科刑上限の枠内で判断すれば良いのか(地裁)が争点となった。最高裁は後者を支持した。
関連する出来事
事件前に加害者は1989年6月13日に別の女児に乱暴し同年9月19日有罪判決を受けていたが、警察の被疑者リストには記載されず、警察のずさんな初動捜査が浮き彫りになった。
被害者が保護された際、新潟県警本部長が関東管区警察局長を東蒲原郡三川村(現阿賀町)で麻雀接待していたことが後に発覚。事件の報を聞いても幹部たちは接待を続けたことで、警察への信頼は大きく揺らぐ。 その接待麻雀についても図書券を景品にしていた賭け麻雀をしており、つまり現職警察官による賭博罪に該当するのではないかとの疑念が持たれた。このことについて、2000年3月6日に新潟県警は「景品となった図書券は新潟県警本部長のみが負担していることから図書券を提供した新潟県警本部長のみ財物を提供する危険負担をしており、他の参加者は財物を提供する危険負担をしていない立場だったため、賭博罪には該当しない」としている[1]。
後に新潟県警本部長と関東管区警察局長が辞職。二人の辞職について報道番組で報道された際、「自ら辞職することで、数千万円の退職金が支払われようとしている。」と報道。その後二人は退職金の受取を辞退した。
当時の警察庁長官であった田中節夫も減給処分された。
事件、裁判の経緯
1990年11月13日 - 新潟県三条市で下校途中に、小学4年生だった女性が連れ去られ、行方不明になる。 この後9年間にわたって監禁されていたことが後に判明する。
2000年1月28日 - 柏崎保健所職員が、母親への暴力という相談を受けて男の自宅へ入る。その際に被害者を発見し保護。男は精神不安定により入院。
2000年2月10日 - 犯人の男は1989年、当時9歳の女児を乱暴しようとして逮捕されていたにも関わらず、県警が男の名前を容疑者リストからはずしていたことが明らかに。
2000年2月11日 - 男を逮捕。
2000年3月3日 - 被害者を監禁し、酔ってけがを負わせた監禁致傷罪で起訴。
2000年4月 - 長岡市のガソリンスタンドなどで、被害者の実名などが書かれたビラが貼られているのが見つかる。
2000年5月23日 - 新潟地裁で初公判。男は罪を認めるものの、弁護側は精神鑑定を請求。
2000年6月26日 - 地元のデパートから女性用の下着を万引きした窃盗罪で男を追起訴。
2001年9月6日 - 「完全責任能力あり」と鑑定担当の医師が結果を提出。
2002年1月22日 - 新潟地裁、懲役14年判決(求刑15年)。
2002年1月24日 - 弁護側、判決を不服として控訴。
2002年12月10日 - 東京高裁、「第一審は併合罪の処理を誤っている」として懲役11年に減刑。
2002年12月24日 - 検察側、弁護側共に上告。
2003年7月10日 - 最高裁、「併合罪は個々の罪を別々に処理するのではなく、全体を統一し処理すべきだ」との初判断を示し、懲役14年判決 (控訴棄却の自判)。確定。
註2:国民審査
最高裁判所裁判官は、任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に国民審査を受け、その後は審査から10年を経過した後に行われる衆議院総選挙の際に再審査を受け、その後も同様とすると定められている(日本国憲法第79条第2項)。
註3:1票の格差(2013年3月26日13時55分 読売新聞より引用)
広島高裁岡山支部、1票格差で選挙無効の判決
「1票の格差」が最大2・43倍だった昨年12月の衆院選について弁護士グループが岡山2区の選挙無効(やり直し)を求めた訴訟で、広島高裁岡山支部(片野悟好のりよし裁判長)は26日、「違憲、無効」とする判決を言い渡した。
国政選挙を無効とする司法判断は、25日の広島高裁判決に続いて2件目。26日午前には、東京都と神奈川県の計7選挙区を対象とした東京高裁と、島根1区に関する広島高裁松江支部の判決もあり、いずれも選挙を「違憲」としたが、選挙無効の請求は棄却した。
25日の広島高裁判決は、無効判決の効力が一定期間後に生じる「将来効」という法律上の理論を適用した。しかし、同高裁岡山支部の片野裁判長は「投票価値の平等は最も重要な基準とされるべきだ」などとして、判決確定により猶予期間なく無効になると指摘。より踏み込んだ内容となった。
同支部の訴訟では、〈1〉2009年衆院選を「違憲状態」とした11年3月の最高裁判決から選挙までの国会の対応をどう評価するか〈2〉選挙が違憲である場合、無効とすべきか――が主な争点だった。
片野裁判長はまず、昨年12月の衆院選について、09年衆院選よりも1票の格差が拡大したことを挙げ、憲法の求める投票価値の平等に著しく反する状態だったと指摘。さらに、区割りを是正しなかったのは国会の怠慢で、司法判断に対する甚だしい軽視だと述べ、選挙は違憲との考えを示した。
岡山2区の1票の格差は、有権者が最少の高知3区に対し1・41倍だったが、判決は「2倍未満でも、憲法違反の区割りに基づいており、違憲だ」とした。
さらに、選挙を無効とすべきかどうかを検討。
片野裁判長は、選挙を無効とした場合には議員が不在になるなどの影響はあるが、1票の格差を容認することの弊害に比べて大きいとは言えず、公益に与える影響を考慮して原告の請求を棄却できるとした「事情判決の法理」を適用するのは相当ではない、とした。
註4:「婚外子」相続差別 最高裁が違憲判断9月4日 NHKより引用
両親が結婚しているかどうかで子どもが相続できる遺産に差を設けている民法の規定について、最高裁判所大法廷は「社会が変化し、家族の多様化が進むなかで、結婚していない両親の子どもを差別する根拠は失われた」と指摘し、「憲法に違反する」という初めての判断を示しました。明治時代から続いてきた相続に関する民法の規定は改正を迫られることになります。民法では、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」は結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できないと規定されています。これに対して、東京と和歌山のケースで、遺産相続の争いになり、ことし7月に最高裁判所の大法廷で弁論が開かれていました。最高裁判所大法廷の竹崎博允裁判長は決定で「子どもは婚外子という立場をみずから選ぶことも取り消すこともできない。現在は社会が変化し、家族の多様化が進むなかで、結婚していない両親の子どもだけに不利益を与えることは許されず、相続を差別する根拠は失われた」と指摘し、「民法の規定は法の下の平等を定めた憲法に違反している」という初めての判断を示しました。この決定は、審理に加わった裁判官、全員一致の結論です。大法廷は平成7年に「憲法に違反しない」という決定を出しましたが、その後、結婚や家族に対する国民の意識が変化している実情を踏まえ、今回、18年前の判断を見直しました。また、決定では「話し合いなどで合意し、遺産相続が確定している場合、今回の判断が改めて影響しない」と指摘し、過去のケースについてさかのぼって争うことはできないとしています。今回、憲法違反とされたことで明治31年から100年以上続いてきた民法の規定は、改正を迫られることになります。申し立てた婚外子女性「差別ない社会を」申し立てを行った和歌山県の婚外子の40代の女性は和歌山市で会見を開き「決定をきいて心が高揚しています。私の価値は相手の方の2分の1ではなく、本当の価値を取り戻したと父に伝えたい。今後は1日も早く法改正が行われ、差別のない社会が築かれることを強く望みます」と話しました。和歌山のケースの嫡出子「違憲判断は納得できず」和歌山のケースの嫡出子は、「最高裁の違憲判断は、納得できるものではなく非常に残念で受け入れがたいものです。私たちの母は法律の規定を心の支えに40年間、精神的苦痛に耐えてきました。決定は日本の家族の形や社会状況を理解せず、国民の意識とかけ離れたものと思います」というコメントを出しました。専門家「迅速に法改正を」最高裁の決定について、家族法が専門の早稲田大学の棚村政行教授は「大法廷が全員一致で憲法違反だと判断したことは画期的で、非常に重い決定だ」と述べました。そのうえで、今後の国会の対応について「相続は誰にでも身近に起こる問題で、いまだに解決していない多くの人のケースできょうの決定が影響を与えることが考えられる。国会は迅速に法律を改正すべきだ」と指摘しました。婚外子制度の歴史は両親が結婚しているかどうかで子どもの相続に差を設ける規定は、115年前の明治31年に施行された民法で設けられました。当時の資料などによりますと、この規定は「法律上の結婚を重視しながら、結婚していない両親の子どもにも一定の相続を認める」という理由から作られたということです。その後、改正すべきだとする声が高まり、平成8年には国の法制審議会が見直しを求める答申を提出したほか、3年前にも国が民法の改正案をまとめました。また、この規定に対しては、国連の委員会から、「差別的だ」と勧告されるなど少なくとも10回にわたって見直しが求められています。一方で、「制度を見直せば結婚せずに子どもを産む人が増える」とか「家族制度が崩れかねない」といった反対の意見もあり、改正は行われないままとなっています。違憲判決は過去いずれも法律改正最高裁判所が法律の規定そのものを憲法違反としたのは今回が9例目で、過去のケースではいずれも法律が改正されています。最高裁は昭和48年に、両親や祖父母などを殺害した場合の刑罰を通常の殺人よりもはるかに重くする刑法の規定を憲法違反と判断しています。また、平成17年には海外に住む日本人の国政選挙の投票を制限していた公職選挙法の規定、平成20年には日本国籍を取得する際に両親の結婚を条件にしていた国籍法の規定について、いずれも憲法に違反するという判決を出しています。過去の例では最高裁の判決前に法律が見直されたケースを含め、いずれも「憲法違反」と判断された法律は改正されています。今回、最高裁が違憲判断を行ったことで、相続に関する民法の規定も改正を迫られることになります。谷垣法務大臣「違憲判断を厳粛に受け止める」谷垣法務大臣は記者団に対し「違憲立法審査権を有する最高裁判所が、憲法違反の判断をしたことは厳粛に受け止める必要がある。判断内容を十分に精査して必要な措置を講じていきたい。相続は日々起きることなので、『法律にはこう書いてあるが、最高裁判所はこう判断している』ということで、いたずらに混乱を生じさせてはいけない。できるだけ速やかに検討して、速やかに対応策を講じていくのは当然だ」と述べ、民法改正に向けた作業を急ぐ考えを示しました。今後の動き最高裁判所大法廷の判断を受けて、法務省は、内容を精査したうえで、民法の改正に向けた作業を進めることにしており、「憲法に違反する」と判断された民法900条の「いわゆる婚外子の相続分は、嫡出子の半分とする」という規定を削除することを検討しています。この規定を巡っては、法務大臣の諮問機関である法制審議会が、平成8年にすでに見直しを求める答申を出していることなどから、法務省は、今回は法制審議会に諮問せずに作業を進めたいとしています。法務省幹部は「民法の改正案がまとまりしだい、できるだけ早く国会に提出したい」としていて、早ければ秋の臨時国会にも改正案を提出する方向で、政府内や与党との調整を行うことにしています。ただ、自民党をはじめ与野党の保守系の議員からは、「婚外子と嫡出子の相続を平等にすれば、現在の結婚制度そのものが崩れかねない」といった懸念も出ており、今後の調整に手間取ることも予想されます。
婚外子相続差別 家族観の変化に沿う違憲判断(平成25年9月5日付・読売新聞より引用)
日本人の家族観の変化を踏まえた歴史的な違憲判断である。 結婚していない男女間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を、結婚した夫婦の子の2分の1とした民法の規定について、最高裁大法廷は「法の下の平等」を保障した憲法に違反するとの決定を出した。 「区別する合理的な根拠は失われた」との理由からだ。 最高裁は1995年、民法のこの規定を「合憲」と判断した。今回、正反対の結論になったのは、婚外子を巡る状況の移り変わりを重視した結果と言えよう。決定は、相続制度を定める際に考慮すべき要件として、国の伝統、社会事情、国民感情を挙げた。そのうえで、これらの要件は「時代と共に変遷するため、合理性について不断に検討されなければならない」との見解を示した。 民法が国民生活に密接に関わる法律であることを考えれば、当然の指摘である。 近年、婚外子の出生が増えている。シングルマザーという言葉も定着した。事実婚も珍しくなくなった。婚外子を特別視する風潮は薄れているだろう。 住民票や戸籍の続き柄の表記では、出生による区別が既に廃止されている。 欧米では相続格差の撤廃が進み、主要先進国で格差が残っているのは日本だけになっている。 違憲判断は、こうした流れの延長線上に位置づけられよう。 今回の決定で特徴的なのは、婚外子の権利保護を最優先に考えるべきだという姿勢を色濃くにじませている点だ。 内閣府の昨年の世論調査でも、婚外子に対し、法律上、不利益な扱いをしてはならないと考える人は61%に上っている。 「父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択・修正する余地のない事柄を理由として、その子に不利益を及ぼすことは許されない」。最高裁のこの判断を、多くの国民は違和感なく受け止めるのではないか。 婚外子の相続格差の規定は明治時代に設けられ、戦後の民法に受け継がれた。法律婚の重視という伝統的な結婚観が根底にある。 相続分を半分にするという規定が、結果として婚外子の差別を助長してきた面は否めない。 最高裁の決定を受け、菅官房長官は「立法的手当ては当然だ」と語った。早ければ臨時国会に民法改正案を提出する方針だ。
速やかな改正を求めたい。
婚外子の相続差別は違憲 「確定事案に影響せず」 最高裁初判断2013.9.4 産経ニュースより引用[民事訴訟]
婚外子相続格差の違憲判決で、最高裁前で「憲法違反」の旗を掲げる弁護士ら=4日午後、東京都千代田区の最高裁判所南門(鈴木健児撮影) 結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に違反するかが争われた2件の家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博(ひろ)允(のぶ)長官)は4日、規定を「違憲」とする初判断を示した。14裁判官全員一致の結論。 また、すでに決着済みの同種事案には「この違憲判断は影響を及ぼさない」と異例の言及を行った。 明治時代から続く同規定をめぐっては大法廷が平成7年に「合憲」と判断、小法廷も踏襲してきた。最高裁が法律の規定について憲法違反と判断したのは戦後9件目で、国会は法改正を迫られることになる。 規定の合憲性が争われたのは、13年7月に死亡した東京都の男性と、同年11月に死亡した和歌山県の男性らの遺産分割をめぐる審判。いずれも家裁、高裁は規定を合憲と判断し、婚外子側が特別抗告していた。 大法廷は決定で、婚外子の出生数や離婚・再婚件数の増加など「婚姻、家族の在り方に対する国民意識の多様化が大きく進んだ」と指摘。諸外国が婚外子の相続格差を撤廃していることに加え、国内でも平成8年に法制審議会(法相の諮問機関)が相続分の同等化を盛り込んだ改正要綱を答申するなど、国内でも以前から同等化に向けた議論が起きていたことに言及した。 そして、法律婚という制度自体が定着しているとしても「子にとって選択の余地がない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、権利を保障すべきだという考えが確立されてきている」とした。 その上で、遅くとも13年7月の時点で「嫡出子と婚外子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていた」と結論づけ、審理を各高裁に差し戻した。 一方で、決定は7年以降に出された最高裁判断については、「その相続開始時点で規定の合憲性を肯定した判断を変更するものではない」とも言及した。 さらに、今回の違憲判断が他の同種事案に与える影響については「先例として解決済みの事案にも効果が及ぶとすれば、著しく法的安定性を害することになる」とし、審判や分割協議などで決着した事案には、影響を及ぼさないとした。 今回の審理には法務省民事局長などを務めた寺田逸郎氏(裁判官出身)は加わらず、14人で審理された。
H25.9.8
広島高裁に左翼裁判官登場。最高裁しか憲法判断をしてはいけないはずなのに、平気で広島高裁は行いました。それに先だって、最高裁は一票の格差は二倍未満が基本というあいまいな判決を出し、最高裁が高等裁判所に憲法判断を許すが如き判決を出しました。それに悪のりして広島高裁(註1)が広島選挙区の選挙の無効判決を出しました。過激な政治介入です。日本各地の高裁が、平成24年12月の選挙が違憲判決を出しました。もはや、最高裁も高等裁判所も法律を守ろうという気持ちは少なくなっているようです。革命のためならば何でもすると言うことでしょうか。このような政治介入する最高裁裁判官は止めさせるべきです。もし、平成24年12月の選挙で、自民党が勝っておらず、民主党が勝っていたらこのような判決を出していたのでしょうか。結局、広島高裁が政治に口を出したことになり、三権分立(立法、行政、司法の独立)に反したことになります。
最高裁にいる左翼裁判官が、一票の格差が1.2倍までと言えばそうなるのでしょうか。まるで、最高裁は立法府気取りです。小選挙区制に最高裁は反対だと言うことでしょうか。最高裁の政治介入です。一票の格差を縮めるためには、小選挙区制よりも中選挙区制の方が有利です。小選挙区制のままだと議員定数を引き上げる必要があります。しかし、小選挙区制が良いか中選挙区制が良いかは政治が判断するべきことです。裁判官がやるべきことではありません。やってはならないことです。
たとえ、最高裁が政治介入をやっても、下級裁も政治介入して良いことにはなりません。裁判官はモラルを持ってもらいたいです。「三権分立を守ること」「法治国家を守ること・・世論に迎合せず法律に照らし合わせて正しいかどうかを判断すること」、最高裁しか憲法判断してはいけないという理由は、司法が立法に介入することだからです。どんな裁判所も介入して良いことになると、政治が混乱することになるからです。見識がない裁判官が政治介入することは、法治国家であることを放棄することにつながるからです。そして、最高裁の裁判官は内閣が任命するからです。ある面で政治家に選ばれているから最高裁の裁判官が憲法判断(法律が憲法に合致しているか判断)してよいのです。
鈴木政洋は、日本の司法が左翼に汚染され、法治国家であることを放棄し、下級裁にいる多くの左翼裁判官を支援することになることを危惧しています。まずは、最高裁の裁判官は、革命家(左翼)でないことを条件にするべきです。革命家と裁判官は相容れません。
註1:社説:衆院選無効判決 警告を超えた重い判断
毎日新聞 2013年03月26日 02時32分
わが国の議会政治史上、異例の事態といっても過言ではあるまい。
「違憲状態」だった小選挙区の1票の格差是正がないまま実施された昨年12月の衆院選広島1、2区について、広島高裁が「違憲・選挙無効」の判決を言い渡したのだ。
選挙無効の判断は、過去の国政選挙の1票の格差をめぐる裁判で高裁・最高裁を通じて初めてだ。
憲法が要請する投票価値の平等に基づいて実施されなかった選挙で選ばれた衆院議員に正当性はない。判決はそう言っているのに等しい。
裁判所はこれまで「違憲」の判断をした場合でも、混乱を回避するため「事情判決の法理」を適用し、選挙を有効としてきた。
広島高裁が過去の例にならわなかったのはなぜか。最高裁は11年3月の大法廷判決で「選挙区間の人口の最大格差は2倍未満が基本」とした法律の区割り基準について合理的との見解を示し、1票の格差が最大2・30倍だった09年選挙は「違憲状態」との結論を導いた。だが、昨年12月の選挙時点で格差は2・43倍に拡大。格差2倍以上の選挙区も09年選挙の45選挙区から昨年は72選挙区に激増していた。
高裁判決は、こうした状態を招いた国会の対応はもはや許されないと判断したのだ。最高裁判決から1年半が経過した昨年9月が是正のタイムリミットだったと結論づけ、「民主的政治過程のゆがみの程度は重大で、最高裁の違憲立法審査権も軽視されている」と強く警告した。国会は率直に批判を受け止めるべきだ。
最高裁で無効判決が確定すれば、訴訟対象の衆院議員は失職する。失職議員が関与して成立した法律は有効なのか。そんな疑問も湧く。
さらに根本的な問いかけもある。他の議員も「違憲状態」で選出された点は同じだ。ならば再投票は失職議員の欠員補充だけで足りるのか。解散して全議員を選び直すのが筋だとの意見も出てこよう。
広島高裁判決は、混乱を避けるため、無効の効果は今年11月26日を経過して発生するとした。最高裁が85年に「違憲」判断をした際、当時の寺田治郎裁判長らが補足意見で示した見解を援用したもので、定数是正に一定の猶予期間を与えたものだ。
「0増5減」を前提に第三者機関の審議会が近く、区割り案を安倍晋三首相に勧告する。最低限、その是正を今国会で済まさねばならない。
ただし、「0増5減」の定数是正は不十分だと札幌高裁が指摘したように、小手先改正への批判もある。投票価値の平等を実現するような定数是正と削減、さらには衆参両院一体の選挙制度改革に本気で取り組む時がきた。
選挙無効判決の裁判長、中華航空事故で50億円賠償命令 朝日新聞より引用 平成25年3月25日
「一票の格差」が最大で2・43倍となった昨年12月の衆院選をめぐり、弁護士グループが「法の下の平等を定めた憲法に違反する」として選挙の無効(やり直し)を求めた訴訟。判決を言い渡した広島高裁の筏津(いかだつ)順子裁判長(62)は1978年に京都地裁の判事補となり、東海地方の地裁や家裁を中心に異動してきたベテラン。2010年1月から那覇家裁所長、11年12月から広島高裁部総括。03年12月には名古屋地裁の裁判長として、名古屋空港で乗客・乗員264人が死亡した中華航空機墜落事故をめぐる損害賠償請求訴訟で、中華航空に総額約50億2640万円を遺族側へ支払うよう命じる判決を言い渡した。
昨年の衆院選は無効 一票の格差訴訟で初判断 広島高裁]朝日新聞より引用
【山本孝興】「一票の格差」が最大で2・43倍となった昨年12月の衆院選をめぐり、弁護士グループが「法の下の平等を定めた憲法に違反する」として選挙の無効(やり直し)を求めた訴訟で、広島高裁(筏津〈いかだつ〉順子裁判長)は25日、広島1、2区について「違憲で無効」とする判決を言い渡した。弁護士らが1962年に始めた一票の格差訴訟で、無効判決が出たのは全国で初めて。
広島1区の当選者は岸田文雄氏(自民)、2区は平口洋氏(同)。ただ、被告の広島県選挙管理委員会は上告するとみられ、最高裁で無効判決が確定しない限り失職はしない。高裁は選挙時の区割り規定そのものを違憲と判断したが、無効訴訟は選挙区ごとに起こす形式となっており、対象となった広島1、2区のみを無効とした。
一連の訴訟では、二つの弁護士グループが全国14の高裁・支部すべてで、計31選挙区を対象に提訴。6日の東京高裁を始め、5高裁・支部も違憲としたが、弊害が大きい場合はあえて無効としなくてもよい「事情判決」の考えを採り、違法の宣言だけをした。名古屋、福岡の両高裁は「違憲状態」と判断した。
H25.3.31
9年2ヶ月の長期にわたる新潟少女監禁事件(註1)は、法律が想定していなかった事件です。だから、犯人が監禁した期間に拮抗した最高刑10年しか出来ないはずです。
更に、第二審が11年とまともに見えますが、最高刑が11年では、最高刑の10年を越えています。少女のために盗んだ2000円程度の下着の万引きが併合罪になるとは通常の法治国家では考えられません。下着を盗まなくても監禁は出来たからです。下着を買うという方法だってあったのです。しかも、その万引き事態は既に賠償が終わっているのです。従って、万引きと監禁の併合罪は法治国家では行ってはならない判決だとわかります。第一審と最高裁の第三審は法治国家を無視した判決を出したのだとしか、鈴木政洋は考えられません。万引きを併合罪にするのは言いがかりです。裁判官が言いがかりをつけるとは恐ろしい時代になったものです。
むしろ、このような長期間にわたる監禁が米国やヨーロッパなどでは既に起こっていたのであって、政治家とマスメディアが問題にしなかったので、国民は気付くことがありませんでした。本来は、長期にわたる監禁事件に関する法律ができていなかったことが問題なのです。それを裁判所が法律を越えて判決を出すことは、自分が神様になったような気持ちでいるのではないでしょうか。裁判官は神様ではありません。どんなことがあっても、裁判官は法律を超えてはならないのです。それが三権分立であり、法治国家であるのです。裁判官が法律を越えれば、法律が無意味になると言うことです。裁判官に取り入れば、法律を越える判決が得られると言うことです。裁判官の汚職が当たり前になる前触れなのです。
註1:新潟少女監禁事件(ウィキペディアより引用)
当時の監禁致傷罪(221条)の最高刑は懲役10年であり、窃盗罪(235条)もまた懲役10年であった。そして、併合罪(45条)は47条で「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。」と定めている。そうすると形式的には懲役15年の枠内で自由に量刑が出来そうである。
ただ、枠内で自由に量刑を定められるとすれば、普通なら不起訴になる軽微な犯罪を併合罪として起訴することで法定の最高刑を簡単に超えられてしまうとも考えられる。実際、本件で追起訴された窃盗罪の被害額は2464円相当であり、弁償もされていたので普通は起訴されることのない犯罪である。ただし、別に立件された窃盗罪は監禁されていた少女の衣類用に盗んだものであり、監禁事件と全く無縁ではない。
そこで、併合罪がいわゆる併科主義による過酷な結果の回避という趣旨を持つことを前提とした上で、個別の罪の量刑を定めて合算すべきなのか(高裁)、科刑上限の枠内で判断すれば良いのか(地裁)が争点となった。最高裁は後者を支持した。2004年の法改正により、逮捕監禁致傷罪の上限は懲役15年となっている。
1990年11月13日 - 新潟県三条市で下校途中に、小学4年生だった女性が連れ去られ、行方不明になる。 この後9年間にわたって監禁されていたことが後に判明する。
2000年1月28日 - 柏崎保健所職員が、母親への暴力という相談を受けて男の自宅へ入る。その際に被害者を発見し保護。男は精神不安定により入院。
2000年2月10日 - 犯人の男は1989年、当時9歳の女児を乱暴しようとして逮捕されていたにも関わらず、県警が男の名前を容疑者リストからはずしていたことが明らかに。
2000年2月11日 - 男を逮捕。
2000年3月3日 - 被害者を監禁し、酔ってけがを負わせた監禁致傷罪で起訴。
2000年4月 - 長岡市のガソリンスタンドなどで、被害者の実名などが書かれたビラが貼られているのが見つかる。
2000年5月23日 - 新潟地裁で初公判。男は罪を認めるものの、弁護側は精神鑑定を請求。
2000年6月26日 - 地元のデパートから女性用の下着を万引きした窃盗罪で男を追起訴。
2001年9月6日 - 「完全責任能力あり」と鑑定担当の医師が結果を提出。
2002年1月22日 - 新潟地裁、懲役14年判決(求刑15年)。
2002年1月24日 - 弁護側、判決を不服として控訴。
2002年12月10日 - 東京高裁、「第一審は併合罪の処理を誤っている」として懲役11年に減刑。
2002年12月24日 - 検察側、弁護側共に上告。
2003年7月10日 - 最高裁、「併合罪は個々の罪を別々に処理するのではなく、全体を統一し処理すべきだ」との初判断を示し、懲役14年判決 (控訴棄却の自判)。確定。
H25.3.25
オーム真理教の菊池直子が逮捕(註1)されました。通常の法治国家では逮捕されません。殺人の時効がなくなったのは(註2)、キリスト教歴2010年4月27日からなので、2004年12月31日までに発覚した殺人事件については、時効は15年です。2005年1月1日から2010年4月26日までに発覚した殺人事件の時効は25年です。2010年4月27日以降に発覚した殺人事件には時効はありません。このような遡って法を適応させてはならないという原則を「法の不遡及の原則」と言います。その法律が施行されるまでについては、以前の法律が適応されると言うことです。そうしないと、当時合法であったことが、その人を罰するために後で法律を作り、当時合法であったことを違法にしてしまうからです。このような状況では、国民は法律を守っていても、いつ法律が変わって罰せられることになるか不安になります。ただし、その人にとって有利になる場合だけは、法を遡って適応することができます。つまり、今回の菊池直子の逮捕については、法の不遡及の原則に従って、逮捕してはならないのです。
ある人が憎いからと言って、法の不遡及の原則を無視することは、日本が法治国家であることを否定することに等しいのです。売国的な法の適応です。
むしろ、菊池直子及びオーム真理教の地下鉄サリン事件(註3)については、テロ行為であるので破防法を適応し、徹底的に通級し、時効の前に逮捕するべきだったのです。破壊防止法を適応させなかった人々こそ、罰せられるべきです(人道的に)。
鈴木政洋は、公訴時効に関する法律で、「2010年(平成22年)4月27日までに公訴時効が完成していない罪については、すべて新法が適用されることとなる。」については、違法な法律だと考えます。
以上の理由により、菊池直子の地下鉄サリン事件に関する時効は成立している者だと考えます。それが法治国家というものです。そして、破防法を適応させていれば、菊池直子を生涯監視し、自由を制限することができるのです。
また、高橋克也容疑者(註4)は、犯人蔵匿容疑で捜査されていますが、日本では、家族は家族の犯罪をかくまってもよいという法律になっています。つまり、高橋克也容疑者は内縁関係にあったので、それが適応されると思います。つまり、日本は家族を大切にする国家なのです。しかし、今回の警察は家族制度を破壊しようという勢力ではないかと疑われます。
日本は、法治国家であり続けるべきです。
註1:オウム菊地直子容疑者逮捕 逃亡17年、殺人などの疑い2012年6月4日朝日新聞より引用
1995年3月の地下鉄サリン事件で、警視庁は3日、警察庁が17年間にわたり特別手配していたオウム真理教元信徒の菊地直子容疑者(40)を相模原市内の住宅で発見した。警視庁は同庁本部に任意同行し、殺人容疑などで逮捕した。警視庁は菊地容疑者と同居していた男性についても、犯人蔵匿容疑で逮捕状を請求する。
警視庁によると、菊地容疑者は教団前代表・松本智津夫(麻原彰晃)死刑囚(57)=地下鉄サリン事件の殺人罪などで確定=らと共謀。95年3月20日午前8時ごろ、地下鉄日比谷、千代田、丸ノ内の3線の車内でサリンを発散させて乗客12人を殺害、5553人を負傷させた疑いがある。警察庁は死者を13人と認定したが、警視庁はサリンとの関係が不明として逮捕状は12人で更新していた。
菊地容疑者はサリン製造の中心人物とされる「化学班」責任者の土谷正実死刑囚(47)のもとで実験データをまとめるなど、サリンの製造を手助けしたとされる。菊地容疑者は調べに対して「サリンの生成に関わっていたことは間違いないが、当時は何を作っているのか知りませんでした」と供述しているという。
警視庁によると、3日午前、同庁本部を訪れた男性が「菊地容疑者に似た女が男と相模原市緑区城山の一戸建てに住んでいる」という趣旨の情報を提供。捜査員が張り込んだところ、コンビニの袋を持った女が午後8時近くに歩いて帰宅した。捜査員が「菊地か」と問いかけると、「はい」と答えたという。
手配写真などに比べてやせており、肩までの黒髪にトレーナーとズボン、スニーカー姿。警視庁は指紋の照合で本人と確認した。菊地容疑者は調べに「職業は会社員」と話しているという。
警視庁が同居している男性に連絡を取ったところ、男性は午後10時15分ごろに神奈川県警大和署に出頭した。捜査関係者によると、男性は40代で、菊地容疑者は男性の名字を名乗り、約2年前から相模原市内で暮らしていたとの情報もある。男性はオウム事件関連の捜査で浮上していた人物だったという。
註2:公訴時効(ウィキペディアより引用)
2010年(平成22年)4月27日に公布・施行された新法(刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成22年法律第26号))には、経過措置が定められている(同法附則3条)。この経過措置によれば、改正後の刑事訴訟法250条の規定は「この法律の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。」とし(附則3条1項)、改正後の刑事訴訟法250条1項の規定は「刑法等の一部を改正する法律(平成16年法律第156号)附則第3条第2項の規定にかかわらず、同法の施行前に犯した人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもので、この法律の施行の際その公訴の時効が完成していないものについても、適用する。」とされる(附則3条2項)。したがって、2010年(平成22年)4月27日までに公訴時効が完成していない罪については、すべて新法が適用されることとなる。

註3:地下鉄サリン事件(ウィキペディアより引用)
地下鉄サリン事件(ちかてつサリンじけん)は、1995年(平成7年)3月20日に東京都の地下鉄で宗教団体のオウム真理教が起こした神経ガスのサリンを使用した同時多発テロ事件で、死者を含む多数の被害者を出した。警察庁による正式名称は地下鉄駅構内毒物使用多数殺人事件[1]である。この事件は日本だけでなく世界にも大きな衝撃を与えた。
註4:高橋克也容疑者と連絡か 菊地容疑者2年前まで2012年6月4日朝日新聞より引用
1995年の地下鉄サリン事件で特別手配され、殺人容疑などで逮捕されたオウム真理教元信徒の菊地直子容疑者(40)が、少なくとも約2年前まで元信徒の高橋克也容疑者(54)=特別手配中=と連絡を取り合っていた可能性が高いことが、捜査関係者への取材でわかった。
捜査関係者によると、菊地容疑者を自宅にかくまっていたとして犯人蔵匿容疑で逮捕された相模原市緑区の自称会社員、高橋寛人(ひろと)容疑者(41)が警視庁の調べに、菊地容疑者と出会ってからの経緯を供述した。
その供述によると、寛人容疑者は2006年ごろ、菊地容疑者と暮らすために同容疑者が住む川崎市のアパートに荷物を取りに行った際、克也容疑者と似た男と会った。その後も何度か会い、10年ごろに同じアパートで3人で会って話をしたという。警視庁は菊地、克也両容疑者がこの時期まで連絡を取り合っていたとみて、捜査員が4日にアパートに向かったが、克也容疑者は住んでいなかった。
H24.6.10
6年前の平成17年4月にJR福知山線で脱線事故がありました。脱線事故の大きな原因を作った社長などの管理職は無罪になりそうなのです。これはどうしたことでしょうか。
事故が報道された初めのうちは、脱線した運転手が非難されていましたが、収益改善のために急カーブを設定、安全装置(ATS-PまたはATS-SW改良版)の欠如、時間を守るのが困難な過密ダイヤ、パワーハラスメントが疑われる日勤教育、車両の安定性を欠くボルスタレス台車、・・・など、次第に本当のことが分かってきました。むしろ運転手は被害者なのでは無いでしょうか。
本当の加害者は誰なのでしょうか。利益ばかり追求し、安全をないがしろにしていた管理職だったのではないのでしょうか。直接、運転して列車を脱線させなくても、事故が起こる要因を作り続けた幹部に問題があったのです。これは、大東亜戦争の責任についての東条英機の態度と対照的です。東条英機は東京裁判をとおして「自己弁護」は行わず、この戦争は「侵略戦争」ではなく「自衛戦争」であり国際法には違反しないと「国家弁護」を貫いたが、「敗戦の責任」は日本国民に対し負うと宣誓口述書で明言していました。ところが、脱線事故に関係した管理職は、自己弁護の塊です。更に、検察や裁判官まで援護しています。つまり、「ATS設置」だけを問題にして、「安全装置だけでなく、日勤教育や過密ダイヤなどが原因で大事故につながった。それを予想し対策を行わなかったこと。」が問わなかいことです。これでは、検察が「JR西日本前社長山崎正夫被告」を無罪にするために、「ATS設置」だけを問題にしているとしか思えません。
江戸時代だったらこのような大事故を起こせば、それに関係した重鎮は切腹をしたはずです。それだけの覚悟と責任をもって行動していたのです。明治時代もそうです。ところが、大東亜戦争後はひどいものです。大東亜戦争に参戦していた人々が現役だった頃は、まだましでしたが、大東亜戦争を直に知らないエリート層は責任の取り方を知りません。JR西日本の社長と関係した管理職は切腹どころではなく、責任を回避することばかり考えています。そのときのポストを辞任すれば良いという安易な対処しかしませんでした。107名の死者と562名の負傷者はどうしてくれるのでしょうか。お金だけで解決などできません。JR西日本の管理職は、このような大きな事故を起こせば切腹しなくてはならないという覚悟で会社を運営しないといけないと言う気持ちがないようです。だから、金儲けばかりに走り、安全面を軽視したに違いありません。
JR西日本の管理職が問題だけではありません。危険ボルスタレス台車売った住友金属工業にも責任があるはずです。住友金属工業の管理職は、ボルスタレス台車が安定性を欠き脱線事故を起こしやすいことは知っていたはずですし、その危険を隠した罪があるはずです。つまり、ボルスタレス台車の危険を隠すように指示した管理職の責任が問われなくてはなりません。初めのうちの公害裁判と同じ事です。会社は責任を問われなかったのですが、公害が問題になるにつれ会社としての責任を問われるようになりました。
現場(運転手)だけに責任を負わせて、その事故の原因を作った管理職の責任が問われないのは間違っています。これでは、まるでやくざの親分が子分に殺人を依頼したのに、殺したやくざだけが逮捕され、指示した親分はおとがめなしと同じ事です。そんなことが世の中で許されてい良いはずがありません。
現在は、一応歴代4社長は起訴されましたが、住友金属工業の責任を回避させるために、無罪になるに違いありません。無罪になるような基礎の仕方しかしていないからです。有罪にするためには、ボルスタレス台車も問題にしないといけないからです。ボルスタレス台車を問題にすれば、住友金属工業の責任は当然のこととして、それを購入したあちこちの鉄道会社も問題になります。その購入を指示したそれぞれの鉄道会社の管理職も問題になります。それを回避しようとした裁判を行うから無罪になるに違いないと思うのです。
もし、裁判官や検察が法の下の平等を唱えるのならば、本当の罪で歴代4社長を起訴し判決していただきたいのです。
********** 資 ****** 料 **********
◎山崎前社長の初公判=ATS必要性の認識争点-JR西、福知山線脱線事故・神戸地裁 時事通信より引用
※記事などの内容は2010年12月21日掲載時のものです
兵庫県尼崎市で2005年4月に乗客106人が犠牲となった福知山線脱線事故で、業務上過失致死傷罪に問われたJR西日本前社長山崎正夫被告(67)の初公判が21日、神戸地裁(岡田信裁判長)である。山崎被告は、事故の危険性を認識できなかったとして無罪を主張する。 JR史上最悪の死傷事故から5年半。鉄道事故で経営幹部の刑事責任が争われる異例の裁判が始まる。
公判では、線路を急カーブに付け替えた1996年、山崎被告が安全対策の最高責任者だった鉄道本部長として、事故の危険性を予見し、自動列車停止装置(ATS)の必要性を認識していたかが主な争点となる。
検察側は冒頭手続きで、死亡した乗客106人と起訴状で対象とした負傷者計493人の名前を全て読み上げる。
起訴状によると、同社は96年12月に現場カーブの半径を半分の300メートルにし、翌年3月から速度の出る快速列車の本数を大幅増加。業界では当時、危険性が高いカーブでのATS整備の必要性が認識され、同社も半径450メートル未満の場所で路線ごとに順次整備した。山崎被告は、JR函館線で起きた同様の事故がATSで防げた例として報告されており、予見可能性がありながらATS整備を怠って、事故を起こしたとされる。
検察側は冒頭陳述で、被告だけが全てを認識してATS整備を決定できる立場にあり、ATS設置を指示する注意義務があったと主張する。
弁護側は、現場が他と比べ突出して危険な場所でなく、事故前はATSに関する国の基準がなかった上、社内で必要性を指摘する意見も出ず、予見可能性はなかったと反論する。
ウィキペディアより引用
2005年(平成17年)4月25日午前9時19分ごろ、列車は塚口駅 - 尼崎駅間の曲線で脱線し、先頭の2両が線路脇のマンションに激突した。事故は、福知山線の兵庫県尼崎市久々知の半径300mの右カーブ区間[1](塚口駅の南約1km、尼崎駅の手前約1.4km地点)で発生した。
事故列車は、宝塚発JR東西線経由片町線(学研都市線)同志社前行きの上り快速列車である。列車番号は5418Mの7両編成で、前4両は、網干総合車両所に所属する207系0番台Z16編成(クハ207-17+モハ207-31+モハ206-17+クハ206-129)同志社前行き、後ろ3両は、同所所属の207系1000番台S18編成(クモハ207-1033+サハ207-1019+クハ206-1033)京田辺行きである。列車の前5両が脱線して、先頭2両は線路脇の9階建てマンションに激突し、先頭車は1階駐車場へ突入、2両目はマンション壁面へぶつかり原形をとどめない形で大破した(当初は状況などから2両が重なるように壁面で大破していると誤解されていた)。
事故列車は、直前の停車駅である伊丹駅で所定の停車位置を超過(オーバーラン)していた。これについて、事故が起きる前に運転士が車掌に対してオーバーランの距離を短くするように打診して、車掌が新大阪総合指令所(現在の大阪総合指令所)に対して約70mのオーバーランを8mと報告し、JR西日本も当初車掌の証言通り8mのオーバーランと発表していた。 このことから、事故後に他の路線や鉄道会社において発生した列車のオーバーランについても大きくクローズアップされた。さらに、JR西日本が事故当日に行った発表の中で、線路上への置き石による脱線の可能性を示唆したことから、愉快犯による線路上への置き石や自転車などの障害物を置くといったことも相次いだ。
事故発生と同時刻には、並行する下り線に、新大阪発城崎温泉行きの特急「北近畿」3号が接近中だったが、事故を目撃した近隣住民の機転により近くの踏切支障報知装置(踏切非常ボタン)が押されて特殊信号発光機が点灯したために運転士が異常を察知し、およそ100m手前で停車して防護無線を発報しており、二重事故は回避された。事故後、現場の半径300mの曲線区間は制限速度70km/hから60km/hに(運輸省令における制限速度算式での300R97Cの制限74km/h台を5km/h単位に丸めて制定したものであるから、安全に掛かる技術的な必要性から 制限を厳しくしたわけではない)、手前の直線区間は120km/hから95km/hへとそれぞれ変更された。
事故列車は、4両編成と途中の片町線(学研都市線)京田辺駅で切り離す予定だった3両編成を連結した7両編成で運転していた。前から1・4・5・7両目の運転台のある車両に列車の運行状態(非常ブレーキ作動の前後5秒間)を逐一記録する「モニター制御装置」の装備があり、航空・鉄道事故調査委員会が解析を行ったところ、前から5両目(後部3両編成の先頭車両)と7両目に時速108kmの記録が表示されていた。ただし、これが直ちに脱線時の速度を示しているとは限らない。先頭車両が脱線、急減速した影響で車列が折れ、連結器部分で折り畳まれるような形になったために、玉突きになって被害が拡大したものとされる。
当時、事故車両の1両目は、片輪走行で左に傾きながら、マンション脇の立体駐車場と同スペースに駐車していた乗用車を巻き込み、マンション1階の駐車場部分へと突入して壁にも激突。続く2両目も、片輪走行しながら、マンションに車体側面から叩きつけられる状態に加えて3両目に追突されたことによって、建物に巻きつくような形で大破。3両目は、進行方向と前後が逆になる。4両目は、3両目を挟むようにして下り方向(福知山方面)の線路と西側側道の半分を遮る状態でそれぞれ停止した。なお、事故発生当初、事故車両の2両目部分が1両目と誤認されており、1両目は発見されていなかった。のちに本来存在しているべき車両数と目視で確認できる車両数が一致しないことから捜索され、発見された。
駐車場周辺において電車と衝突して大破した車からガソリン漏れが確認されており、引火を避け被害者の安全を確保するためにバーナーや電動カッターを用いることができず、救助作業は難航した。また、3両目から順に車両を解体する作業を伴い、徹夜で続けられた救助作業は事故発生から3日後の4月28日に終了した。
ダイヤ面での問題
事故発生路線の福知山線においても、阪急電鉄の宝塚本線・神戸本線・伊丹線と競合しており、他の競合する路線への対抗策と同様、秒単位での列車の定時運行を目標に掲げていたとされている。
もともと全体的に余裕のないダイヤのうえ、停車駅が増加したにもかかわらず、所要時間は2003年12月に快速が中山寺駅に停車する前と同じであったため、遅延が常態的だった。特に当該列車においては基準運転時分通りの最速列車で、特に事故発生区間である塚口駅 - 尼崎駅間では2004年10月のダイヤ改正によりさらに短縮されていた。
事故調査委員会が全国のJR・私鉄・公営鉄道事業者のダイヤを調べたところ、余裕時分のないダイヤを組んでいたのはJR西日本だけだった。
路線の設備での問題
当該事故発生前は運行本数が多く、速度も比較的高い大都市近郊路線であるにもかかわらず、速度照査用の設備が設置されていなかった。信号機に対する自動列車停止装置には旧型の速度照査機能がないATS-SWが利用されていた。ただし、ATS-SW形式でも信号とは独立の速度照査機能を付加して、必要箇所に地上子対を設置すれば、速度超過に対する緊急停止機能が動作する。有名な例では東海旅客鉄道(JR東海)の主要路線でこの形式が採用されている。
また、JR東西線との直通に対応した尼崎駅の改良に伴い、過去の線路付け替えで曲線半径が小さくなった。これは、当初の上り線は現場マンションを挟んだ東側にあり、下り線に併設されていた尼崎市場への貨物線跡地などを利用する形で現在の上り線が敷設された。この時点で東西線区間には新型ATSが設置されたが、福知山線においては付け替え区間を含めて設置されなかった。カーブでの高速運転をするためにカントを付けるが、現場は緩和曲線が短く、カントは上限105mmより少ない97mmなのでその分制限速度が5km/h低くなっていた。半径300mでカント105mm(上限値)での制限速度は75km/h。従前の「本則」では60km/h - 65km/h。
事故発生現場のカーブには、国土交通省の定める脱線防止ガードの設置基準にも該当せず、脱線防止ガードは設置されていなかった。ただし、脱線防止ガードがあったとしても、今回のように極端な速度超過による転覆脱線を起こした場合はほとんど効果が期待できない。
事故乗務員の問題
本件事故を起こした運転士は運転歴11か月で、運転技術や勤務姿勢が未熟だった可能性がある。この背景には、国鉄分割民営化後の人員削減策で、特にJR西日本においては他のJR各社と比べると長期間にわたって新規採用者を絞り、定年退職者がまとまった数になったのを契機に採用者を増やしたため、運転士の年齢構成に偏ったばらつきが出て、運転技術を教える中堅およびベテラン運転士が少なくなったと言われている。
日勤教育の問題
目標が守られない場合に、乗務員に対する処分として、日勤教育という、再教育などの実務に関連したものではなく懲罰的なものを科していた。それが十分な再発防止の教育としての効果に繋がらず、かえって乗務員の精神的圧迫を増大させていた温床との指摘も受けている。日勤教育については事故が起こる半年前に、国会において国会議員より「重大事故を起こしかねない」として追及されている。また、日勤教育は「事故の大きな原因の一つである」と、多くのメディアで取り上げられることになった。事故を起こした運転士は、過去に運転ミスなどで3回の日勤教育を受けていた。
日勤教育(ウィキペディアの別の項目)
JR西日本において、機器取扱誤り・オーバーラン・信号違反などといった事故や事故に至らない阻害を起こした運転士や車掌に対して、事故再発防止を図るために、乗務から外して必要な教育が行われていた。運転士の勤務パターンには、乗務する際の「乗務」と、本社・支社社員や駅の助役、工務職場の社員などと同じように朝9時から17時45分までの乗務以外の勤務である「日勤」とがあり、乗務から離れて行われる事故再発防止教育の勤務は「日勤」となることから、この事故再発防止教育を「日勤教育」と俗称的に呼ばれる場合があった。なお、1分遅れただけで「日勤教育」が行われたとの報道等があったが、単に列車の時間が遅れたことのみをもって「日勤教育」が行われることはなく(新幹線を除く)、あくまでも機器取扱誤り・オーバーランなど人為的ミスを起こした場合や、全く関係ない会社の都合で「日勤教育」は行われた。しかしながら、列車が遅延することは日常頻繁に見られること、列車の遅れの多くは接客や他の列車の接続待ちといった運転士の責任とは全く無関係なものであり、1分遅れたことをもって「日勤教育」にしていたら実際に運転する運転士がいなくなることからも、遅れをもって「日勤教育」を行われたとの指摘は誤りの可能性もある。日勤教育に対しては様々な内部告発がなされている。
それらを要約すれば、日勤教育というものの「教育」とは名ばかりであり、「いじめ」・「八つ当たり」・「からかい」・「スパルタ教育」などに近いものである。またミスを犯した者に肉体的・精神的・経済的な打撃を与える「懲罰」的や「暴力」的なものである。場所は職場の中で最も目立つ場所(内勤事務の真ん中など。いわゆる晒し者にさせるためである)や別室で監禁状態にして行われた。内容は毎日、直接的原因と関係ないレポートや作文、就業規則の書き写しのほか、草むしりや車両清掃などが行われていた。又、複数の管理者に取り囲まれ、恫喝・暴言・罵声を浴びせられた。給与も減額された。期間や内容は現場長や管理者の裁量で決まるため、いつ終わるかわからない絶望感から、自殺や鬱になる人も多かったという。また、教育期間終了後に再乗務できず他職(駅・車両管理部門等)に異動となる場合もあった。
この問題が社会に表に出るようになったきっかけは、JR西日本尼崎電車区に勤務していた運転士の男性が自殺し、それを労災認定を行わせるために行われた2000年の裁判である(自殺した運転士の遺族が会社を相手に損害賠償を求めた裁判では、大阪地裁が「日勤教育が原因と認めるものの、自殺することは予見不可能」として遺族の請求を棄却する被告側勝訴の判決を2005年2月に言い渡し、現在、大阪高裁で係争中)。2001年11月8日に参議院でも質疑され、国会で「日勤教育を行うといった体質では今後重大事故を起こしかねない」と追及された。後にこの言葉は現実のものとなる(JR福知山線脱線事故のケース)。また、これとは別に、JR西日本所属の運転士3人が、日勤教育で不当な扱いを受けたとして同社などを訴えた訴訟があり、2009年5月に大阪高裁で、運転士や車両管理係(森ノ宮電車区所属)の2名に対し90万円の支払いを命じる判決が言い渡され、2010年3月11日付で最高裁で判決が確定した。
なぜ福知山線脱線事故は起こったのか 著者 川島令三出版社 草思社
プロローグ
事故は転倒脱線
しかし、この推定はまったくの間違いであったことが判明する。事故調(航空・鉄道事故調査委員会の鉄道部会)の何度目かの発表では、カーブの外側にはいくつかのフランジ痕が認められたが、内側には認められないという。
さらにその後、脱線が先ではなく、転倒が先にあり、車体に引きずられて台車が浮いたために脱線した転倒脱線であると発表した。その証拠にマンションから2本目の架線柱に車体やパンタグラフの当たった跡が認められるとし、その写真も公開した。
それを聞いたとき、いったいどのくらいの速度でカーブを通過したのかと疑問が湧いた。国鉄の計算式をあてはめると136キロだが、JR西日本によれば133キロであるという。それほどの高速を出していたのかと驚いてしまう。ところが、このときの発表では非常ブレーキをかけたときの速度は108キロとされていた。
しかし、カーブの外側への転倒脱線は130キロを上回る速度を出さなければ起らない。もしくは軽量のボルスタレス台車のせいで、もっと低い速度であっても起こったのかのいずれかである。
転倒脱線の要因としては曲線半径と速度によるものがほとんどで、乗り上がり脱線とくらべて、他の要因は二の次であるとされる。
しかし、その後、台車の左右に各1個ある空気バネのうちカーブの外側のほうが収縮し、内側のほうが膨らんだため、車体が外側に傾いて転倒脱線を起こしたと説明された。空気バネの撓みも大きな要因として加わったということである。
これはボルスタレス台車に特有のものである。要するにボルスタレス台車が要因であることを示唆している。ところが鉄道業界ではボルスタレス台車の導入を推進してきたので、ボルスタレス台車が危険であるとは言いにくい、あるいは言いたがらない雰囲気がある。
ところが筆者は当初からボルスタレス台車に疑問を持っていたし、台車メーカーや一部の関係者で、あまりよろしくないどころか、危険と言う人までいた。
ボルスタレス台車であっても車軸のところにある軸バネに撓みを持たせて、ここでも曲がりやすくしているものもある。しかし、新快速用の223系やその前の221系にはそれがあっても、207系にはないように見える。
事故の当日から少し前の4月12日前後と16日にも筆者は大阪を訪れて207系を見ているが、そのとき、どういうわけか207系の台車に目が行き、カーブ通過時に事故を起こさなければよいがと、なんとも言えない不安感を感じたのを憶えている。
ともあれ事故調はボルスタレス台車が要因の一つと言いたげだったが、ボルスタレスのボの字も口にしていない。やはりタブーなのであろう。
そして、カーブの手前で非常ブレーキをかけたと言ったかと思うと、衝突寸前にかけたかもしれないとか、事故電車が宝塚で折り返す前後にATSによるものか、運転士によるものかわからないが、何度も非常ブレーキがかかったとかの話が出てきて、運転士の心理状態を考える必要があるとの考えを示した。
しかし、非常ブレーキを一度でもかける、あるいはかけられると、次には絶対にかからないようにするのが運転士の習性である。心理的な重圧をいくら強く受けていようとも、そうするはずである。
事故調は車両は正常だったと早期に発表している。しかし、前の4両は大破しており、そう簡単に言えるものか疑問であるし、事故電車に乗っていて助かった人は事故を起こす前に異常な揺れがあったと証言している。
非常ブレーキが何度もかかったからには、車両になんらかの異常があった可能性も捨てきれないはずである。
ところで筆者はコメンテーターとしてテレビ局が作った悲惨な状況のVTRを見続けただけでなく、現場に何度も訪れた。
東京から新幹線に乗ると、大阪に近づくにつれて息苦しくなり、反対に現地を離れ、新幹線に乗って居眠りをすると、事故現場の悲惨な状況の夢を見てしまう。軽いPTSD(心的外傷後ストレス障害)に陥ったように思えてならない。
筆者はまだしもいい。しかし、事故にあわれた方、救助に携われた方、あるいはご遺族の方はもっと苦しい思いをされている。
そういうことからも、この尼崎事故の真相を探り、どうすれば防げたのかを、次章から検証してみたい。それが亡くなられた方への鎮魂になり、ご遺族や関係者への慰めにもなると思う。
川島令三
1950年、兵庫県生まれ。芦屋高校鉄道研究会、東海大学鉄道研究会を経て「鉄道ピクトリアル」編集部に勤務。現在、鉄道アナリスト、早稲田大学非常勤講師。小社から1986年に刊行された最初の著書『東京圏通勤電車事情大研究』は通勤電車の問題に初めて本格的に取り組んだ試みとして大きな反響を呼んだ。著者の提起した案ですでに実現されているものがいくつかある。著書は上記のほかに『全国鉄道事情大研究(シリーズ)』『関西圏通勤電車徹底批評(上下)』(草思社)『徹底チェック 車両(シリーズ)』(中央書院)『新線鉄道計画徹底ガイド』(山海堂)『私の電車史』『鉄道「歴史・地理」なるほど探検ガイド』『幻の鉄道線路を追う』(PHP研究所)『日本の鉄道名所100を歩く』『鉄道カレンダー』(講談社+α新書)などがある。尼崎での事故後、多くの報道番組にコメンテーターとして出演し、解説に当たった。
ボルスタレス台車は、1981年(昭和56年)4月1日に初めて導入 秦野エイト会より引用
東京地下鉄(旧・帝都高速度交通営団)半蔵門線向けの通勤形電車として、 8000系電車が、80年代に入って導入された。
この8000系電車の営業運転の開始は、1981年(昭和56年)4月1日である。
車体そのものは、千代田線用6000系および有楽町線用7000系に準拠するところが多いが、営団の8000系は、日本最初のボルスタレス台車の本格的導入だった
しかし、ボルスタレス台車のせいで、8000系の乗り心地の悪さは有名だった。
おまけに、ボルスタレス台車のせいで、8000系の速度は100km/h以上は出せなかった。
ボルスタレス台車は、住友金属工業製の「SS-101」
この8000系電車は、1980年(昭和55年)から1994年(平成6年)にかけて190両が東急車輛製造、日本車輌製造、川崎重工業、近畿車輛で製造された。
半蔵門線の路線自体は1978年(昭和53年)8月1日の渋谷駅~青山一丁目駅間が最初の開業区間であり、この8000系が営業開始するまでの約2年半の間、営団は自ら車両を保有せず、乗り入れ先の東京急行電鉄8500系のみで運用していた。
営団としては、試験車や電気機関車を除き、日本初のボルスタレス台車を採用した。
このボルスタレス台車は、住友金属工業製の「SS-101」と呼ばれるものだった。
110km/h運転もできないボルスタレス台車の電車
しかし、このボルスタレス台車の影響で、乗り入れ先の東急田園都市線内での 110km/h運転に対応できないなどの問題が生じることになる
そのため、100km/h運転しかできないようなリミッタが取り付けられた。
ボルスタレス台車は、驚くべきことにたったの110km/h運転さえできないお粗末な代物なのだ。
車なら110km/hの速度など知らない間に出てしまうぜ。
H23.1.2
押尾学保護責任者遺棄致死罪裁判の判決が出ました。懲役2年6月の実刑です。田中香織を遺棄したのは、MDMA使用に付随した問題です。押尾判決について MDMA使用の罪が主であるのにそれよりもうんと重い刑は異常です。しかも、一事不再理の原則に反しています。押尾学被告は、田中香織の容体の悪化を放置したという道徳上の責任は重いと思います。しかし、法律上の責任はないと思います。一方、マスメディアは、「裁判員の判決」というような欺瞞に満ちた言い方をしていました。つまり、本当は裁判員裁判と言っても、裁判官の意見の方が重要視されているのです。「裁判員の意見を配慮したから、一事不再理も保護責任者の問題も無視した。」という言い訳をしたいようです。つまり、マスメディアも東京地裁も押尾学をどんなことをしても有罪にしたいということです。むしろ、東京地裁が裁判員裁判にしたのは、裁判官が押尾学被告を保護責任者遺棄致で有罪としたいためにだからだと予想されます。もともと、裁判官自身は、保護責任者(註1)でない押尾学を有罪にすることは法律上問題なことを知っているので、「保護責任者遺棄致死罪」の致死まで入れることは心が痛んだということでしょう。保護責任者とは、病院で治療を担当している医者や看護婦が患者を保護する責任があるとか、交通事故を起こした運転者が被害者を保護する責任があるなど、法律上で責任が位置づけられた立場でしか、保護責任者とは言えないのです。
最近の裁判官は、自分が法律だと思っているふしが見られます。裁判官は、法の番人です。裁判官は、法律にあることでしか裁判してはならないのです。それが、裁判官のモラルです。裁判官は立法をしてはいけません。法律にないことで人を罰してしまったら、裁判官として失格です。東京地裁(山口裕之裁判長)の本件で押尾学被告を有罪と判定した裁判官は全て職を辞すべきです。鈴木政洋は、裁判官は、人を道徳で裁判せず法律で裁判することを切に望みます。それが法治国家です。
東京地裁には、次のような野望があるのではないかと疑います。中共では麻薬を取り扱うと簡単に死刑(註2)にします。東京地裁の裁判官は、つい日本を中共のようにしたいのではないかと疑ってしまいます。清(満州の女真族が中国を支配した国)はイギリスの持ち込んだ阿片に苦しみました。その苦しみを背景として、現在の中共政府は麻薬には死刑という厳しい処置をしているのです。
最近の日本では、麻薬がはびこってきています。それを解決するのは、国民と政治の問題です。政治家が、麻薬を撲滅させるための法律と行政を考えることが本質なのです。そして、国民が麻薬を撲滅させるように政治家に働きかけることが本質なのです。裁判官が、法律の解釈を曲げて人を罰してはいけないのです。
次にこの裁判で問題なのは、弁護士が弁護をしていないということなのです。一緒にMDMAという毒を飲んで片方が死んだからと言って、死んだのは片方の責任でしょうか。双方に責任があると思います。両方成人です。MDMAが危険なことも分かっていたはずです。双方が死の危険があるのを承知してドラッグSEXをしていたのです。それで、死んだのです。例えば、次のようなことが考えられます。
1.押尾学被告が保護責任者であったという根拠を追求していません。
2.押尾学被告がMDMAを摂取していたのにもかかわらず正常な判断力があったことを前提に話しています。検察がそのような異常な裁判を進めていこうとしているのに、問題にしていません。
3.そもそも、この裁判が一事不再理の原則に反していることを問題にするべきなのにしていません。。
4. 双方平等な立場でMDMAを使用していたことを追求していません。
5.田中香織も危険なMDMAを使用し死亡する可能性もあることを知っていて使用したことを追求していません。
5.裁判官が道徳的な問題と法律上の問題を混同していることを追求していません。
更に問題になるのは、押尾学被告のその弁護士と裁判官とグルなのではないかと言うことです。それは、前述したように弁護士がまともに押尾学被告の弁護をしていなかったからです。裁判官が弁護士に対して「押尾学被告が保護責任者にならない」という弁護はするなということを指示・命令している可能性すら感じます。このような暗黒裁判が行われるようでは、日本は危ういです。押尾学被告は上告すると言っています。東京高等裁判所は、法律に則った判決を出して欲しいと思います。公正な裁判をして欲しいと思います。
註1:保護責任者(ウィキペディアより引用)
その発生根拠が問題になる。法令や契約などがこれに含まれるが、一定の行為(先行行為)を行った者についても事務管理や条理により保護義務が発生すると解されている。そのため本来保護義務を負っていなかったはずの者であっても、親切心で要保護者の保護を開始した(例、自室に引き取って看病した、病院へ連れて行くため車に乗せた)ために保護義務を負わされることもある。
註2:中共による日本人死刑囚まとめて処刑の目的 (酒井信彦の日本ナショナリズムより引用)
2010年4月 4日
三月三十日、麻薬密輸の罪により中共で死刑判決を受けている赤松光信なる日本人が、間もなく死刑を執行されることが明らかになった。直後の四月二日には、同様の罪で死刑判決を受けている、武田輝夫・鵜飼博徳・森勝男の三人の日本人にも、死刑が執行されることが明らかになった。前日に、遼寧省の外事弁公室から瀋陽の日本領事館に、七日後に執行すると伝えられたと言う。これは最初の一人の執行が伝えられた段階で、日本政府が強い抗議を行わなかったからである。 . 麻薬密輸の罪はそれなりに重いことは確かだが、どれだけ正確に捜査が行われ、公正な裁判が行われたのか、はなはだ疑問である。中共では死刑者の数字を公表していないが、年間に数千人だと推定されている。まさに死刑超大国である。日本でも足利事件の冤罪が明らかになったばかりである。裁判において、どんなデタラメなことが行われているか、想像に難くない。
もし判決が正当だとしても、日本の政府には出来るだけ日本人の生命を守る義務がある。それが国家というものである。しかし施政方針演説で「命を守りたい」と絶叫した鳩山首相は、最初の執行予定が伝えられたときに、残念だと言っただけであった。昨年末、イギリス人が同じ罪で死刑が執行された場合には、イギリス政府は猛然と抗議を行った。その日本政府の腑抜け振り・弱腰振りを見て、中共政府は即座に、更に三人の執行を決定した。つまり日本人の精神を徹底して屈服させるのが真の狙いである。
これだけやられても民主党政権は、卑屈に迄に弱腰で、四月三日の朝日新聞に拠れば、「日本人への死刑執行に関して、日本政府の対応は抑制的だ。岡田克也外相は程永華・駐日中国大使を呼んで懸念を伝えたが、執行中止は求めなかった」という。自己の責任を放棄して日本の死刑を行わない、確信犯的死刑廃止論者である千葉景子法務大臣は、中共の法制度のことであるとしてノーコメント。法務省幹部は、「他国の刑事司法手続きに、こちらが意見することは内政干渉であり、できない」という。中共の企みは、ものの見事に成功した。
政府の弱腰振りは論外だが、この件に関するマスコミの報道も変である。テレビの報道は余り熱心に見ていないが、報道そのものが少なく、殆ど問題としての関心が無いらしい。新聞はそれなりに報道しているが、中共のやり方とそれへの日本政府の対応に、奇妙に理解を示す傾向が見られる。中共の走狗である朝日は言うまでも無いが、そのような論調は産経も見受けられた。
例えば、中共では麻薬が蔓延しているから、更にはアヘン戦争の歴史があるから、麻薬犯罪を厳罰にするのだと説明しているが、別に麻薬犯罪だけを厳罰にしているわけではない。また日本が抗議できないのは、日本にも死刑制度があるからで、死刑を廃止したイギリスとは違うのだと解説する。しかし日本で死刑になっているのは、人間を何人も殺したような人間だけで、実質的には存在しないのと変わらない。いくら人口が多いと言っても、年間数千人を死刑にする、世界の中で飛びぬけた死刑超大国とは全く異なる。要するに中共おける命の値段の異常な安さこそが、根本問題なのであるが、それは言わない。
日本の死刑廃止論者は、日本の僅かな死刑に抗議しながら、中共の膨大な死刑に全く沈黙してきた。これは日本人の命は大切だが、中共国民の命はどうでも良いと言っているのと同じである。今度の問題で明らかになった事態は、更に進んで、中共による死刑であるなら、日本人の命も大切ではない、という白痴的な表明に他ならない。死刑廃止論者を何人も抱える、民主党内閣がそれを行った。当人たちは気付いていないだろうが、死刑廃止論は完全に破産した。そして日本人のシナ人に対する精神的な隷属も、より一層深まった。
H22.9.19
押尾学被告と知人のやくざと関係のあるホステスとMDMA(註1)を使用し、ドラッグSEXを行いMDMAのせいでホステスが死亡した事件です。ところが、保護責任者遺棄致死罪だけ、別の裁判が行われようとしています。MDMAを使用したためにホステスが死亡したのだから次のような事件になるはずです。
押尾学被告・・・麻薬及び向精神薬取締法違反及び保護責任者遺棄致死罪
田中香織・・・・麻薬及び向精神薬取締法違反
田中香織被告は死亡したため不問。押尾学被告は、麻薬及び向精神薬取締法違反については、有罪だと思いますが、保護責任者遺棄致死罪については、押尾学が田中香織の命が危ないと思った時間とMDMAの薬物が切れて正常になった時間が問題となるはずです。この裁判記録のように救急車を呼べば助かったかどうかが主な議論になるのは問題のすり替えです。通常は双方ともMDMAを使用しているので不問になるはずです。
もう一つの問題は、一事不再理の原則に反していることです。この原則は、同じ事件なのに、別々に裁判を行い被告を異常に長い時間拘束することができるし、行った犯罪を分割することによって、それぞれの裁判の判決ででた懲役の合計を異常に長くすることができるからです。その意味で、一事不再理の原則があるのです。明確に、この保護責任者遺棄致死罪については、一事不再理の原則に反していると鈴木政洋は考えます。押尾学は、このMDMAの判決は既に出て執行猶予中なのです。裁判官は、裁判員を使って、詳細に検討することを放棄し、世論に訴えかけ、法律に名を借り法律以上の重罰を科すつもりではないでしょうか。
この法治国家の日本で、人民裁判が行われるようになっては、国民がどんな法律でも守るのが正義であるかが問題になってきます。法治国家の崩壊は、テロを生みます。是非、人民裁判を行った裁判官は全て退官していただきたい。そして、不当な判決を行った不文については、それなりの処罰を受けていただきたい。
註1:合成麻薬MDMAは記憶系統の混乱を発生させる要因を作り出す。その作用として神経細胞の破壊及び永続的な(数ヶ月~数年とも言われている)後遺症をもたらす。特に混合成分(合成麻薬と言われる由縁)の内、覚醒剤や亜覚醒剤と併用された場合には複雑な精神面・身体面における害反応があり、前述の多様な記憶障害を引き起こす。運動を行う直前及び多量の摂取を強要した場合、最悪(使用者死亡の場合など)、殺人罪及び殺人未遂に問われるケースもある[要出典]。海外で行われたレイヴパーティー等では死亡者が続出している。 ウィキペディアより引用
以下資料
【押尾被告 初公判】検察側、懲役1年6月求刑 平成21年10月23日
押尾学被告 合成麻薬MDMAを飲んだとして、麻薬取締法違反(使用)罪に問われた俳優、押尾学被告(31)に対し、検察側は23日、懲役1年6月を求刑した。
押尾被告はこの日、東京地裁で開かれた初公判で「(間違いは)ありません」と起訴内容を認めており、検察側と弁護側の間で事実関係に争いはないため、公判では刑の重さが争点となる。
押尾学被告、香織さん9割方救えた 平成22年9月11日 サンデースポーツより引用
10日に東京地裁で開かれた押尾学被告(32)の裁判員裁判に検察側証人として出廷した救命救急医は「(香織さんが)早く搬送されていれば9割方助けられた。100%に近い9割方と言える」と証言した。保護責任者遺棄致死罪を問う最大の争点「救命の可能性」にかかわる重大証言で、押尾被告側の「すぐに119番通報しても助からなかった」との主張を完全に否定した
押尾学被告、香織さん9割方救えた (操作メニューをスキップして本文へ 特集 : 事件 100%近く救命できた-。救急のエキスパート、昭和大医学部教授の証言で押尾被告はますますピンチに立たされた。
香織さんがMDMAを服用して異変が起き始めた昨年8月2日午後5時50分ごろからの容体の変化と、救命可能性を詳細に検証した。重要な証人だけあって、尋問は予定を大幅にオーバーし、2時間超をかけた。
検察側が法廷で示した資料では、同5時50分ごろに香織さんが「急にハングルのような言葉でブツブツ言い出し、『しっかりしろ!』などと怒鳴り始めた」と異常な症状を示した。救急医は「一般的には、この時点で119番通報するのが普通」と説いた。
その上で、早めに病院に搬送していれば、院内で心停止の一歩手前の危機的状態に陥った場合でも、「香織さんは若い女性なので9割方助けられた。100%に近い9割方だ」と断言。搬送中に心停止一歩手前になっても、「救急隊員の蘇生措置により、90%に近い9割くらいの確率で救えるはず」。いずれにしても高い確率で救命可能性があったと言い切った。
実際は、放置された香織さんの症状は進行。初公判時に検察側が明かした白目をむき出しにする“エクソシスト状態”を経て、午後6時20分ごろ「突然ベッドに倒れ、息が止まり脈も打っていないような状態」となった。これは「心停止の一歩手前、あるいは止まってしまった状態」と説明した。
この時点の119番通報では「1分間で生存の可能性は7%近く下がるので、通報から救急隊到着まで5分とすると65%の可能性で助かる」と明言。一般的に遅すぎるこのタイミングでも、50%以上の確率で救命できたとの見解だ。しかし、通報はなされなかった。
これまでの裁判で押尾被告は、メモをとりながら証人をにらむ場面もあった。が、救急医の証言中は時折メモを取る程度で、力ない目つきで証人を見たり、うつむきがちに。13日の自ら語る被告人質問では、どのような態度で臨むのか。
田中香織はパチンコ力欲しさに押尾学と変態SEX?稲川会交流の芸能事務所社長語る!
押尾学と田中香織がピーチジョン社長の野口美佳(正確には野口美佳の資産管理などをする個人会社)から借りた六本木ヒルズレジデンスB棟2307号室で2人きりの、所謂、密室での事件であり、田中香織は亡くなり、今や押尾学以外に当時の状況を知る人間がいないことを考えれば、救急車を呼べば確実に救命できたことを証明する必要があるため、検察側に課せられた立証のハードルは高い。
検察側は、検察側は電話やメールのやり取りのほか、現場に駆け付けた押尾学の関係者らの証言などによる状況証拠の積み上げで有罪を立証していく方針とみられる。
9月6日、押尾学の保護責任者遺棄致死及び麻薬取締法違反についての公判が行われた。
証人A(短髪で恰幅の良いスーツ姿の中年男性で芸能プロダクション経営者)
証人Aと田中香織は4年前(2006年)くらいに居酒屋で知人の紹介により知り合った。
当時、田中香織が新宿で働いていて、銀座(のホステスとして)で成功したいので応援してもらえないかということで、お店を紹介したりと助力した。
証人Aが田中香織から押尾学について話を聞いたのは、2008年末だという。
2008年末に証人Aの経営する会社に訪れた田中香織は、雑談中に「◎▽会長」を知っている?と切り出した。
証人Aは、「◎▽会長」と直接会ったことはないが、パチンコ業界の大物と称され、いろんなスポンサリングをしている人物であり、押尾学をかわいがっているということは知っていた。
2008年末頃、田中香織は、銀座8丁目の高級クラブJ(ジュリア、2010年7月クローズ)でホステスとして働いていたが、まだ「◎▽会長」の担当ということではなくヘルプだった。
「◎▽会長」と押尾学ら3人が高級クラブJ(ジュリア)に入店したとき、ヘルプについた田中香織は、押尾学を「食っちゃったんだよね」と証人Aに語った。
つまり、田中香織と押尾学は、2008年末に肉体関係を持ったということだ。
また、今までの報道などを考慮すれば、「◎▽会長」=フィールズ会長の山本俊英だと思われる。
もう一人、パチンコ業界ということで押尾学と接点のある人物として報道されたのは、コスモ・イーシー 社長の熊取谷稔で、息子が押尾学の保釈金を出したといわれるが、マスコミは「政財界のフィクサーやゴルフ場やパチンコ関連のレジャー企業のオーナー」的な表現をすると思うので、芸能・格闘などのスポンサーとして、銀座界隈でブイブイ豪遊しているフィールズ会長の山本俊英と感じた。
証人Aは、田中香織がこれまで付きあってきた男性は年配の人が多かったと語る。
証人Aは、押尾学と会ったのは、9月6日公判が初めだというが、押尾学は女性関係が盛んだと聞いていたので、「気をつけろ」的なことを田中香織に言った。
証人Aは、田中香織が押尾学と肉体関係を持ったのは、最初はタレントだからと思ったが、田中香織は上昇志向が高く、押尾学の)取り巻きが大きいと主張していたので、店を持つ夢のために押尾学にいろいろと支援を受けたかったのではと思うようになった。
田中香織「(押尾学)の取り巻きが大きいから」・・・・
証人Aが田中香織と会った直近の出来事は2009年7月24日、八王子で証人Aの同級生(指定暴力団稲川会系組長の男性)の誕生会。
証人Aは、誕生会が行われた店から八王子駅まで行く道中での田中香織との会話内容を語る。
田中香織「変なのと付き合ってるんだよね」
証人A「変なのって何?」
田中香織「性癖が」
証人A「道具か何か使うのか」
田中香織「薬を飲ませたがるんだよね」
証人A「薬ってシャブか」
田中香織「エクスタシー」「(薬が)効くまで飲ませたがるの」
証人A「なんだそいつ。誰だそいつ」
証人Aは、田中香織は内臓系が丈夫じゃなく、相談を受けていたこともあったので、「ここがやられんぞ」と言った。
田中香織「でも、効くまで勧めるからしようがないよね」
証人Aは、相手を探る・・・
証人A「(相手は)金持ってんのか」
証人A「じじいか」
田中香織「いや、若いんだよね。自分と同じぐらい」
証人A「ITか」
田中香織「違う」
証人A「自分の業界か」
田中香織「まあ、そんなもん」
証人Aは、田中香織から相手の名前までは聞き出せなかったが、田中香織の兄貴分という認識だったので、かなり注意した。
しかし、田中香織は、「取り巻きがでっかいからさ」「今、私にとってチャンスなの。兄貴(証人A)にも恩返しするから」と話していた。
「取り巻きがでっかいからさ」・・・・。
証人Aは、高級クラブJ(ジュリア)従業員(もしくは、指定暴力団稲川会系組長、)から「アゲハが亡くなりました。自分も分からない。分かったら電話します」連絡が入り、田中香織が亡くなったことを知った。
証人Aは、高級クラブJ(ジュリア)従業員から「『テレビを見てください」と電話があり、押尾学に関する報道で田中香織の死亡理由を知った。
証人Aは、2009年7月4日のシーンがオーバーラップした。
芸能人ということ、銀座ホステスということ、薬ということ・・・・あ、これだ、やられたと思った。
やられたと思った?
MDMAを飲まされていた聞いていたからだ。
押尾学にMDMAの飲まされたあげく、死んでしまった・・・と証人Aは思っている。
弁護人は、証人Aの証言をつくり話ではないのかと疑う質問をしていたが、途中から、事件報道を見た証人Aが田中香織のの交際相手を押尾学と判断した理由に移った。
弁護人は何故、田中香織の交際相手の名前うぃ、きつく聞かなかったのかととう。
証人A「そういわれると、まさか死ぬとは思わなかったので...」
弁護人は証人Aと田中香織に暴力団関係者がいたことを強調すべく証人Aを問う。
暴力団稲川会八王子一家の組長と、田中香織の肉体関係を証人Aに問うが、証人Aは「ないと思います」と答えた。
証人Aは、暴力団稲川会八王子一家の組長と田中香織の関係は、新宿のクラブでの客とホステスの関係だと説明する。
田中香織には「パパリン」と称する山口組関係者とも付き合いがあったことを証人Aは認めた。
田中香織が住吉会系関係者と男女関係があり、30万円貰ったことを弁護人は問うたが、証人Aは否定する。
弁護人は証人Aに質問することで、田中香織は暴力団、ヤクザと交際していたことを、印象づけたいようだ。
田中香織は石川県で10代にヤクザと結婚した。
そのとき、田中香織は入れ墨(刺青、TATOO)を背中にする。
離婚した田中香織は、上京し、新宿や銀座で将来は店をもつためにホステスとして働くのだ。
弁護人の意図は、田中香織が複数の暴力団関係者と付き合いがある=違法薬物を入手しやすい環境であるとしたいからです。
検察官は、田中香織と押尾学の交際について、再度証人Aに問う。
2008年末、田中香織から押尾学の話をされたとき、「食っちゃったんだよね」と発言したが、「付きあっている」「交際している」ということは言わなかった。
2009年7月24、25日、田中香織は「変なのと付き合ってるんだよね」と発言している。
どちらも、証人Aは、田中香織が恋愛しているという認識は持てなかったとする。
そこで、裁判員は、証人Aに、田中香織が複数の男性と肉体関係を持つような女性かを問うた。
証人A「年が明けてから(田中香織)女性の方と暮らし始めました。『なかなか不幸な子なんだ。それで私の家に住ませている。その子が妊娠していて、私がお父さん代わりになるんだ』と話していました。それから彼女は何かにせかされているように仕事をして、働きづめでした。子供を養っていかないといけないという決意の表れだったのかと思います」
う~ん、その答えでは複数の男性と肉体関係をもつような女性か、いちづなのかは分からないが、証人Aにより次のようなことがわかった。
•田中香織は上昇志向で、なにかにせかされているように働きづめであった。
•田中香織は銀座で店(クラブ)経営をしたかったので、そのためには、人脈を広めたかった。
•人脈ということでは暴力団関係者や証人Aなどの芸能関係者もいたが、スポンサーとなりえるタニマチやパトロンを見つけたかった。
•高級クラブJ(ジュリア)で上客のフィールズ会長の山本俊英が押尾学らを連れて豪遊していたときに、ヘルプについた田中香織は、キッカケをつくるべく、押尾学と肉体関係になった。
•田中香織は2009年7月頃、MDMASEXを求め続ける交際相手がおり困っていたが、「取り巻きがでっかいからさ」という理由で、交際を拒否することはしなかった。
夜の街、風俗・水商売には暴力団が関わることが多い。
芸能界や格闘技でも同様だ。
田中香織がホステスとして生活のために稼ぐというよりも、店(クラブ)を経営したい気持ちが強く、そのためになりふり構わないというならば、「あらゆる力」というものを利用したいと思うことだろうし、ホステスとして売上が高まる上客を掴み、スポンサーとなりえるタニマチやパトロンを得るべく、押尾学と付き合うのである。
田中香織は交際相手を間違えたと感じる。
なぜなら、田中香織自身が死んでしまったら、店(クラブ)経営もできないのだから。
PS。
稲川会八王子一家の組長と交流している短髪で恰幅の良いスーツ姿の中年男性の芸能プロダクション社長とは誰だろう?
フィールズ会長と親しく、泉田勇介を押尾学に紹介した、クラブオーナーで芸能プロダクション社長でもあるNとは違うんだよなぁ~???
H22.9.12
昨年、平成21年5月21日より、検察審査会(註1)の評決に法的な拘束力が生じるようになりました。この法改正には、検察のモラルが低下した場合は有用であると思います。しかし、そうでなければ、いたずらに裁判の数を増やすだけなような気がします。しかし、平成22年の1月27日の9年も前に起きた「明石花火大会事故」(註2)について、明石署副所長を今頃起訴するのは問題だと思います。つまり、事後法によって罰することになるからです。極東軍事裁判が事後法で裁いたという違法行為と同じなのです。鈴木政洋も個人的には、明石署副所長が起訴されなかったことは、身内に甘いという印象をもちます。しかし、事後法で裁くことは問題です。やはり、日本が法治国家であることを思えば、今、明石副所長を起訴することも法治国家であることを放棄することと同様なのです。つまり、被告に不利な法律を事後法で裁くと言うことは、どんなに法律を守って生活をしていても、合法であった過去に行ったことをあとで新しい法律を作られて有罪にされるかもしれないと言うことなのです。これでは、不安で仕方ありませんね。だから、近代国家では事後法は許されないのです。事後法が許されているのは、独裁国家です。ある人間を捕まえて処刑したい場合、あとで新しい法律を作って逮捕して、裁いて有罪にして処刑するのです。
更に問題なことがあります。この下村誠治さんが小さい2歳の子供を、人混みに連れ出したことに対して、落ち度があったと考えます。そのことが一切不問にされていることは問題です。2歳の子供を人混みに連れ出せば、事故に遭うかもしれないのは予想できたはずです。刑事責任があるかは別にして、父親に道徳的な責任があります。しかし、明石警察署副所長に刑事責任があるというのならば、父親にも刑事責任があるとするべきでしょう。しかし、鈴木政洋は、法の不遡及の原則に基づき明石署副所長を起訴してはいけないと考えます。そして、父親も道徳的な責任はあるのですが、刑事責任はないと考えます。人ばかり恨まずに、自分の責任も考え、反省するべきです。自分の責任を明石署副所長に責任転嫁しただけではありませんか?
最近は、被害者の復讐のために裁判所が活躍することが多くなりました。法治国家として許されないことです。これほどまで、裁判官のモラルが低下したのは問題です。日本の危機だと思います。裁判官は、法の番人であって、被害者の復讐を助けるのは仕事ではありません。
註1:Wikipediaより引用
平成21年5月20日以前は検察審査会が行った議決に拘束力はなく、審査された事件を起訴するかの判断は検察官に委ねられるため、「不起訴不当」や「起訴相当」と議決された事件であっても、結局は起訴されない場合も少なくなかった(ここ数年でも起訴される確率は2-3割[1])。しかし、司法制度改革の一環として、検察審査会法を改正するための法律(平成16年法律第84号)により、この起訴議決制度が、平成21年年5月21日から導入され、議決に拘束力が生じるようになった(平成21年5月21日に施行)[2]。平成22年1月27日には、明石花火大会歩道橋事故について、初の起訴議決がなされ、明石警察署の元副署長が強制的に起訴されることとなった[3]。
註2:明石花火大会事故 検審が起訴議決 父の執念 実結ぶ
平成22年1月28日 東京新聞より引用
事故現場の歩道橋で慰霊碑に手を合わせる遺族の下村誠治さん=27日午後、兵庫県明石市で
検察の四度の不起訴を経て“市民による起訴”が初めて実現する。兵庫県明石市の花火大会事故で二十七日、検察審査会は当時の明石署副署長を「起訴すべきだ」と議決。「ようやく真実が明らかになる」。事故から約九年、真相究明を求め、審査申し立てを繰り返した父の尽力が報われた。一方で、市民感覚の過度な尊重を不安視する声も。市民の視点は法廷で判断される。
次男智仁ちゃん=当時(2つ)=を失った神戸市垂水区の保険代理業下村誠治さん(51)は、遺族の先頭に立ち当時の明石署幹部の責任を問い続けた。「できることはすべてやる」。強い思いが検察審査会の議決を引き出した形だ。
二十七日夜、神戸市内で議決書に目を通し、何度もうなずいた後で記者会見に臨んだ。「遺族が訴え続けてきたことが反映された百点満点の議決。扉を開けた」と歓迎した。
二〇〇一年七月のあの日、一家で花火大会に来ていた下村さんは悲鳴を聞き救助へ。後を追った智仁ちゃんは、崩れる人垣に一瞬でのみ込まれた。必死に戻って抱きかかえたが手遅れだった。「おれもつぶされて死ねばよかった」。ひつぎに取りすがって泣いた。
〇二年に警備の現場担当者だった明石署の元地域官らは起訴されたが、元署長(〇七年に死去)や元副署長は不起訴に。下村さんは「なぜ署のトップが責任を問われないのか」と疑問を抱いた。
「一人では戦えない」と遺族同士で話し合いを重ねた上で〇三年に検察審査会に審査を申し立て。起訴相当議決が出たが神戸地検は再度不起訴にした。〇五年にも申し立てて再び同じ経過をたどった。それでも「智仁からもらった力がある」とあきらめなかった。
一九五六年に雑踏事故で百二十四人が死亡した新潟・弥彦神社に足を運び、信楽高原鉄道事故や日航ジャンボ機墜落事故などの遺族と交流を深めた。〇六年に最高検に申し入れに訪れた際には、応対した職員が名前を確認せずメモすら取ろうとしなかったため抗議。後日、検事総長が陳謝した。
改正検察審査会法施行の昨年五月二十一日当日、待ち構えたように三度目の審査を申し立てた。「泣き寝入りで息子の死が忘れ去られたくない」との一念が支えだった。
「遺族は法廷ですべてを出してもらうことが一番の望み」。会見後、事故現場を訪れ、慰霊碑の前でそっと手を合わせた。
※起訴機能変質も
元最高検検事の土本武司筑波大名誉教授(刑法)の話 起訴議決制度は司法の民主化という点で画期的だ。ただ議決は、有罪の確信が得られた場合のみ起訴するという従来の検察官の立場と大きな隔たりがある。起訴の機能が変質しかねず、違和感を覚える。過失犯に共犯はあり得ず、共犯性を認め公訴時効が停止しているとの判断には無理がある。「先例がないから迷う」としているが、被疑者に不利益をもたらしており問題だ。
※国民感覚を重視
諸沢英道常磐大教授(被害者学)の話 被害者・遺族は刑事裁判で真相を明らかにし、特に組織上の責任が重い立場の人が事件をどう考えているのかただしたいとの思いが強い。起訴議決により公判が開かれ、被害者参加制度で直接質問できる意義は大きい。議決は有罪か無罪か勝ち負けを意識するこれまでの裁判ではなく、国民感覚に立って事件を解明し刑事責任を判断するのが大切との視点を打ち出した。
H22.1.31
大阪で小学4年生に対する殺人事件が起きました。しかし、不思議なことに「保護責任者遺棄致死容疑」です。内縁の夫である小林容疑者が、自分になつかない松本聖香さんを疎ましく思い虐待を繰り返し最後に殺したというのが事件の概要だと思います。
しかし、これがもし、親が殺したのではなく、他人が拉致して、ベランダに置き去りにして、ほとんど食事も与えず死に至らしめた場合は、どうなるのでしょう。おそらく検察は殺人罪で起訴するのではないかと思います。
他人が子どもを殺すと罪が重くて、親が子どもを殺すのは罪が軽い(註1)ようです。何か間違っていると思いませんか。殴って殺したら殺人で、「子どもは死の恐怖におののきながら、ほとんど食事も与えられず衰弱ながら死んだ。」のです。こちらの食事を与えずに殺したのは「保護責任者遺棄致死容疑」です。どちらの殺し方が残忍なのでしょうか。鈴木政洋は、後者だと考えます。残忍な殺し方の方が罪が軽いのは奇妙です。間違っています。お金がなくて、病気の子どもを病院に連れて行くことができずに無くなってしまったのとは違います。子どもを疎ましく思って虐待をし、衰弱させ死に至らしめたのは、殺人と言っても問題がないと思います。法律上で難しいというのならば、法律を改正する必要があるかもしれません。法律のことはよく知らないので悪しからず。暴行して殺すのと、何週間もかけてじわじわとなぶり殺しにするのとどちらが罪が重いのでしょうか。後者の方が罪が重いと思います。道義的に罪がある方が刑罰としての罪が重くなるべきです。まず、短い時間で殺してもの長い時間をかけて殺しても、殺人には変わりありません。このことを忘れるべきではありません。また、別の例を考えてみましょう。これが、グアンダナモ基地でイラク人収容者に対して行われるとするならば、拷問と殺人で起訴されるのではないでしょうか。
この松本聖香さんの事件がどのような処理がなされたか気になりますが、マスメディアでは報道されていないようです。最近、検察は世論を気にして犯人に対して過剰な求刑をすることがありますが、この件については、過小な求刑となっています。不思議な現象です。これでは、まるで「保護者の責任を追及してはいけない。」とでも思っているようです。「保護者は憎しみで子どもを殺しても罪は軽い。」とでも思っているようです。検察は、「保護者の責任を追及すると世論の反撃を得る。」と思っているのかもしれません。こんなことでは、検察も裁判所も信頼しきれません。正しい検察と裁判官に出会えればよいですが、そうでなければ不当な目に遭うかもしれないと言うことです。
このような態度では、法治国家は保たれません。子どもをベランダに監禁した上に食事を与えず死に至らしめたのは、虐待かつ殺人と考えるのが適切だと思います。小林康浩は、虐待及び殺人、松本美奈は殺人幇助あるいは殺人の共犯が妥当ではないでしょうか。正当な判決が下りることを望みます。
註1:平成21年5月22日 読売新聞より引用
大阪の小4女児遺体遺棄、1日に水500mlだけ
大阪市西淀川区の小学4年松本聖香さん(9)が衰弱した状態で放置されて死亡、遺体が遺棄された事件で、母親の美奈(34)、内縁の夫の小林康浩(38)両被告(いずれも保護責任者遺棄致死容疑で再逮捕)に食事を制限されていた聖香さんが、1日に与えられていた水分は、必要量を大きく下回る、500ミリ・リットルのペットボトル1本分だったことが、大阪府警の調べでわかった。
ベランダに放置する際は、夜間でも布団を渡さずに寝させていたことも判明。府警は、暴行などに加え、水分制限や寒冷な場所での放置も聖香さんの衰弱の要因の一つとみて調べている。
捜査関係者によると、聖香さん宅に週に数回、出入りしていた知人の杉本充弘被告(41)(死体遺棄罪で起訴)が、小林被告が水などを入れたペットボトル1本を「1日分」と言いながら、聖香さんに渡すのを複数回見た、という。
食事については、杉本被告は「3月半ば頃から、ほとんど食べさせてもらっていなかった」と供述。専門家によると、9歳前後の児童(想定・体重30キロ)が1日に必要な水分量は、食事による摂取も含め、2・4リットルという。
ベランダでの放置が夜通しにわたることも度々あった。聖香さんの死亡前日夜から十数時間放置した際は「寒かったのでコートは渡した」(小林被告)としているが、ほとんど布団も敷かずコンクリート面に直接、寝させることが多かったという。府警は22日午前、小林、美奈両被告を送検した。
西淀川女児死体遺棄 衰弱の聖香さんを何度も殴打 平成21年5月15日産経ニュースより引用
松本美奈被告 大阪市西淀川区の市立佃西小4年、松本聖香さん(9)の遺体が遺棄された事件で、聖香さんの死亡前日の4月4日深夜、衰弱してほとんど動けなくなった聖香さんを、母親の松本美奈被告(34)の内縁の夫、小林康浩被告(38)が何度も殴ったり、頭を踏みつけたりしていたことが15日、西淀川署捜査本部への取材でわかった。知人の杉本充弘被告(41)=いずれも死体遺棄罪で起訴=が止めに入るほど激しい暴行だったという。
捜査関係者によると、死亡前日の4月4日夜、小林、松本、杉本の3被告は聖香さんが玄関先でぐったりしているのを放置したまま食事に出掛けた。帰宅後もぐったりしたままで、失禁に気付いた小林被告が激怒、聖香さんの頭を殴打するなど暴行を加えたという。
その後、小林被告は聖香さんをベランダに引きずり出し、5日夕まで十数時間にわたって放置していた。
松本被告はこの間、「おかゆのようなものをベランダで聖香さんに与えた」と供述しているという。司法解剖で聖香さんの胃の内容物に少量の米があったことが確認されている。
聖香さんは4月に入って衰弱が目立つようになり、立ち上がるのも困難な状態に。食事を与えられても吐いてしまうこともあったという。さらにたびたび失禁するようになり、小林被告が「臭い」と怒鳴ってベランダに閉め出していた。風呂にも入らせなかったとされ、せっかんを恐れた聖香さんは自らベランダに出ることもあったという。
【西淀川女児遺棄】内縁の夫が虐待を主導 平成21年4月29日 産経ニュースより引用
このニュースのトピックス:暴行・虐待
大阪市西淀川区の市立佃西小4年、松本聖香さん(9)の遺体が山中に遺棄された事件は、母親の松本美奈(34)ら3容疑者が死体遺棄容疑で逮捕されてから29日で1週間。西淀川署捜査本部の調べなどから、内縁の夫の小林康浩容疑者(38)が聖香さんへの虐待を主導していた実態が明らかになってきた。松本容疑者も虐待を容認する一方、悩んでいた可能性を示す事実もわかった。
捜査関係者によると、聖香さんへの虐待について、小林容疑者が「しつけのためにやった」と供述。小林容疑者の長男(6)も「お父さんがたたいたりベランダに出したりした」と小林容疑者主導を裏付ける証言をしているという。
また、今年1月まで同居していた聖香さんの双子の妹(9)は同小の教諭に「今のお父さん(小林容疑者)にたたかれる。ご飯を食べさせてもらえない。お母さんは黙っている」と説明していた。
しかし、松本容疑者の携帯電話の通話記録から、聖香さんを遺棄する3日前の4月3日午後、大阪市中央児童相談所に約5分間電話していたことが判明した。相談所に記録はなく、職員も覚えていないことから内容は確認できないが、聖香さんへの虐待について何らかの相談をした可能性もあるとみられる。
H21.6.27
従来、一般的には中学卒業の有職少年や高校卒業の18歳以上の喫煙は黙認されてきました。そのような現状から、18歳以上は喫煙を許可する法律に改正してもよいようなものですが、法律は改正していません。改正しない代わりに、黙認してきました。ここになって、突然喫煙者でなく売った者を逮捕(註1)というのは唐突です。まるで、神奈川県警の売名行為に見えます。逮捕するより指導する方が先決ではないでしょうか。あまりに、杓子定規でよくないと思います。
これでは、まるで神奈川県警の「一生懸命がんばっているぞ!」というアピールのための逮捕に思えます。鈴木政洋的には、18歳成人には反対ですが、18歳成人の議論をしているのに、「20歳よりも18歳の方が成人がふさわしい」と言っているのです。従って、成人ならば、たばこを吸ってもよいはずです。なぜ、今、18歳の子どもにたばこを提供したからと言って、逮捕するのでしょうか。
最近、恐ろしいと思うことは、経済・教育・官僚などあらゆるところで、利己的な人間が増えたことです。「自己顕示欲」が強くなり、「評価制度」により、自分の成果のことばかり考える人が大半になりました。だから、全体のバランスを調整するよりも、自分の成果を大切にする人々が増えたのです。「自分よりも全体」ではなく、「全体よりも自分」と言うことです。
はじめは、経済界が金の亡者となり、モラルを低下させました。規制緩和の美名の元に、半奴隷制度である人材派遣を製造業まで拡大させました。そして、経済界で、導入した賃金を低下させるための手段である評価制度を公務員まで拡大しました。そして、次に向かったのは公務員です。公務員のバッシングを始め、公務員にまで評価制度を拡大させました。公務員の賃金を下げ、法人税を上げさせない、あるいは下げるためです。評価制度(註2)のおかげで、公務員のモラルも低下しました。もちろん、公務員のモラル低下はそれだけが原因ではありませんが、その一つの原因であることは間違いありません。本来、公務員は、評価制度で働くのではなく使命感で働く者だからです。そして、最後に裁判所もモラルが低下させたのです。警察は、法律を杓子定規に解釈し逮捕します。そして、裁判所は、法律のために法律で裁きます。そして、もっと問題なのは、見せしめのための、逮捕劇である疑いが強いのです。つまり、このようなたばこを未成年に提供している人々はたくさんいます。そして、全て、このように逮捕されるわけではありません。ほんの、少しの人間が立件されるだけです。これでは、運が悪いとしか言いようがありませんし、突然、法律を厳しく適応させるなんて、問題です。もし、警察が未成年のたばこをやめさせたいのならば、今後は、18歳以上の未成年についても厳しく処罰することを宣伝し、そして、たばこを未成年と知りつつ提供した者についても厳しく処罰することを宣伝すべきです。今回は、たばこを吸った方は処罰されていないという異常な状況です。たばこを吸って体に害がある未成年を逮捕するのではなく、提供した方を逮捕するという主客転倒した状態です。
鈴木政洋は、次のように考えます。
・18歳以上の未成年で高校を卒業している者→基本的に検挙しない。
・16歳以上の18歳未満の未成年で中学を卒業している者
ア)すでに働いている者→基本的には検挙しない。
イ)高校生である者→検挙する。
ウ)専門学校に通う者→多くは検挙する。
そして、検挙、検挙しないにかかわらず高校生や専門学校生、中学生、小学生には保護者共々指導する。特別の場合を除いて有職少年については指導しません。法律上は問題があるのかもしれませんが、現実的な対応だと思います。有職少年は、自分で働いて自己責任が高校生よりもあると考えられるからです。しかし、フリーターは微妙な問題があるので、指導の必要があるかは場合によります。また、指導するのは警察がよいのか、児童相談所などの施設にそのような部署をつくるかは、検討の余地があります。
註1:読売新聞(平成21年5月22日)より引用
18歳長男の喫煙黙認、母親とたばこ店主の女2人書類送検
18歳の長男が喫煙しているのを黙認したとして、神奈川県警山手署は21日、横浜市中区に住む会社員の女(42)を未成年者喫煙禁止法違反容疑で横浜地検に書類送検した。 同署幹部によると、会社員の女は昨年6月頃から今年4月5日まで、自宅などで長男が喫煙しているのを知りながら、止めなかった疑い。「たばこを吸わせないといらいらしてきょうだいげんかすることがあったので吸わせていた」と供述しているという。
また、同署は21日、自ら喫煙することを知りながら未成年者にたばこを販売したとして、いずれもたばこ小売店経営の59歳と74歳の女2人を同法違反容疑で横浜地検に書類送検した。
2人は、「タスポの導入で、未成年者が自動販売機でたばこを買わなくなり、売り上げが落ちたので、直接売っていた」などと供述しているという。
同署幹部によると、県警では同法違反容疑の取り締まりを強化しており、たばこ小売店の検挙は2007年は2件、08年は16件、今年1~4月は24件という。
註2:評価制度は本来、管理職や中間管理職のための制度です。それを、末端まで適応させたのが間違いの元です。評価が正しく評価されればよいのですが、ほとんどの場合、正しく評価できないのです。数字で評価しやすい項目で評価するので、本来の仕事とのずれが出るのです。正しく、評価することは難しいのです。
H21.6.14
夜中両親が子供を連れ回し、酒気帯び運転の加害者の脇見運転による3人の幼児が事故死しました。痛ましい事故(註1)です。しかし、3人を殺すつもりで自動車を運転していたわけではありません。第1審の判決で十分だと思います。その加害者は市役所を解雇され、交通刑務所を出所した後は多額の賠償金が待っています。それを真面目に賠償することを望みます。ただし、第2審の判決は間違っていると思います。遺族やマスメディアが望んだ危険運転致死傷を認めてしまいました。法律を公正に適応したら第1審の判決になると思います。しかし、福岡高裁は違いました。これは、福岡高裁は、日本が法治国家であることを忘れていると思います。「福岡高裁は、日本はマスメディアに治められていると考えている。」と判断せざるを得ません。裁判所は法の番人です。裁判所は、加害者の行った行動を方に照らし合わせてどうかということ判断することが仕事です。裁判所は、被害者の復讐を助ける場ではありません。また、マスメディアの意見を反映する場でもありません。法が加害者の行為が法に照らし合わせてどうかを判断する場です。裁判官は政治家ではありません。政治家は、被害者の立場を考え今後同じ事が起きないように法律を考えたりすることが役目です。裁判官が政治家の役目を果たしてはならないのです。それが、三権分立(註2)です。裁判官は三権分立を守るべきです。
最近の裁判所は狂っています。地方裁判所には法治国家としてまともな裁判官が多くいますが、高等裁判所や最高裁判所には自分の名誉や名声のために「裁判官としての倫理を踏み外す」裁判官が多くなってきました。そう、裁判は世論やマスメディアの影響を受けてはならないのです。しかし、福岡高裁は世論を気にして、危険運転致死傷で懲役20年にしたと思えます。他の犯罪とのバランスがとれていません。例えば、この福岡高裁のような判決が許されるのならば、福知山線の脱線事故を起こした社長や管理職は、死刑にならないとおかしいですよね。なぜか、死亡した福知山線の運転手の責任は追及されて、、会社の管理体制はほとんど問題になっていません。速度オーバーをしなくては仕方がないようなダイヤを組んでいることは、事故を予見させたはずです。その意味からすれば、「お酒を飲んで自動車を運転することは危険だと予見できたはずだ。」と同じ事に思えませんか?ここで、お酒を飲んだ人というのはJR西日本の管理職と言うことです。今回の福岡高裁の判決の勢いならば、「危険運転致死傷の適応と同じ勢いで、積極的に危険な行為をしたという共犯における主犯という勢いで」判決を出すべきです。つまり、重過失致死罪の適応です。おそらく、東大卒というような学閥などの仲間意識があるので、管理職は通常の法の裁きなので有罪にはならないと思います。法治国家では、「同じような犯罪については同じような処罰であるべき」です。
もちろん、現段階で、福知山線脱線事故の管理職を重過失致死罪を適応させることは、法治国家として間違っていると思います。それと同じ理由で、今回の福岡高裁の危険運転致死罪の適応は間違っていると思います。福知山線脱線事故の件については、今後同じ事故が起きないように、管理責任を問えるような法改正が必要だと思います。
兎にも角にも、日本の法治国家を回復して欲しいと思います。明治時代の大津事件(註3)の時は、法治国家であることのデビューでした。明治にできたことが平成にできないのではいけません。
註1:「危険運転致死傷」適用、懲役20年…3児死亡で福岡高裁 平成21年5月15日 読売新聞より引用
子どもたちの遺影を抱え記者会見場を出る大上哲央さん夫妻たち=大野博昭撮影 福岡市東区で2006年8月に起きた3児死亡飲酒運転追突事故で、危険運転致死傷罪と道交法違反(酒気帯び運転、ひき逃げ)に問われた元同市職員今林大(ふとし)被告(24)(福岡市東区奈多)の控訴審判決が15日、福岡高裁であった。
1審・福岡地裁判決は脇見が原因として業務上過失致死傷罪などで懲役7年6月(求刑・懲役25年)としたが、陶山博生(すやまひろお)裁判長は「脇見ではなく、飲酒の影響で前方を認識できなかった」と指摘。
3児死亡事故控訴審の傍聴券を求め福岡高裁前に集まった大勢の人たち=大野博昭撮影 1審判決を破棄し、危険運転致死傷罪などを適用して懲役20年の実刑判決を言い渡した。
危険運転致死傷罪の適用は、正常な運転が困難なほど酔っていた状態が条件。控訴審では1審同様、同罪の適否が最大の焦点となっていた。
陶山裁判長は、今林被告の酒酔いの程度について「相当量の飲酒をし、事故当時、先行車を認識するために必要な目の機能にも影響が出る程度の危険な状態だった。飲酒により前方注視が困難で正常な運転が難しかった」と認定し、危険運転致死傷罪が成立すると判断。同罪と道交法違反との併合罪により懲役20年とした。
1審判決(2008年1月)は、被告が事故現場まで蛇行運転などをせず、事故後に警察官が酒気帯びとしたことなどを理由に、「飲酒の影響で正常な運転が困難な状態だったと認められない」と判断。被告が最大10秒以上も脇見した可能性を指摘し、事故原因は「脇見運転による過失」としていた。
控訴審で、検察側は現場をパトカーで走行して撮影した動画を提出。「道路は傾斜しており、前方を見てハンドルを調整しなければ走行できない」と脇見の可能性を否定した。
その上で、「被告はアルコールの影響で、車線に従って直進させることがようやく可能な状況だった。遠方の先行車を十分認識する能力を失っていた」と主張し、危険運転致死傷罪の適用を求めていた。
高裁は、動画は証拠として採用したが、検察側が請求した裁判官による現場検証は却下していた。
一方、弁護側は1審同様、飲酒の影響を否定して、「事故原因は脇見」と主張。「被害車両は居眠り運転だった」などと被害者の過失を改めて指摘し、刑の軽減を求めていた。
註2:三権とは、
立法権:法を定立する権力
行政権:法を執行する権力
司法権:法を適用する権力
註3:以下ウィキペディアより引用
大津事件(おおつじけん)は、1891年(明治24年)5月11日に日本を訪問中のロシア帝国の皇太子・ニコライ(後のニコライ2世)が、滋賀県大津市で警備にあたっていた巡査・津田三蔵に突然斬りかかられ負傷した、暗殺未遂事件である。行政の干渉から司法の独立を確立し、三権分立の意識を広めた近代史上重要な事件。議論の末津田三蔵は無期徒刑となり、司法大臣山田顕義は辞任した。
旧刑法116条は日本の皇室に対して適用されるものであって、外国の皇族に対する犯罪は想定されておらず、法律上は一般人と全く同じ扱いにせざるを得なかった。つまり怪我をさせただけで死刑を宣告するのは法律上は不可能であった。ただし裁判官のなかでも死刑にすべきという意見は少なくなかった。
時の大審院(現在の最高裁判所)院長の児島惟謙は法治国家として法は遵守されなければならないとする立場から、「刑法に外国皇族に関する規定はない」として政府の圧力に反発した。要するに「国家か法か」という回答困難な問題が発生したのである。
H21.5.17
最近の日本では、殺人事件や爆破事件(註1)が起こると「社会に不安を与えたから・・・重罰を処す。」という判決が増えてきました。社会に不安を与えること自体は、道徳上の罪です。しかし、法律上の罪であってはならないと思います。このようなことを法律上の罪とすると日本のマスメディアも残忍な事件を報道することによって社会に不安を与えたら罪になるということになります。そのことを認識した上でマスメディアは報道するべきです。そして、自殺報道のようにWHOの自殺に関するガイドラインを無視する報道はいけません。報道モラルの問題です。「社会に不安を与えることは」倫理的な罪であっても法的な罪があるのは間違いです。たとえば、残忍な殺人をして、社会を不安に陥れたことは法的な罪に問うてはいけません。残忍な殺し方をしたこと自体は法的な罪に問われるべきです。
例えば、社会を不安に陥れることを罪だというのならば、たとえば、政府に反対する行動をとった場合、政府が「その行為を社会を不安に陥れる罪」と言って、政府に反対する人々を法的な罪に問うてよいことになります。このような事態も考えられるのにマスメディアは「社会を不安に陥れる罪」問題にしてません。結果的に報道の自由を制限するかもしれないのに・・・です。
「社会を不安に陥れる罪」がまかり通るのは中共や北朝鮮などの独裁国家です。裁判所は、日本を独裁国家にしたいというのでしょうか。
「社会を不安に陥れる罪」を別の見方をしてみましょう。マスメディアの騒ぎ方によって量刑が変わるという意味にもとることができます。「つまり、法によって裁くと言うよりもマスメディアのご機嫌を伺って裁判しますよ。」と言うことでしょうか。結果的に「マスメディアが裁判の判決に参加している」とか、「マスメディアが判決に影響を及ぼしている」と考えられます。
もう一つ、裁判所は「TBSを閣下に納めようとしたライブドアの堀江貴文さん」にTBSに有利なような偏った判決を出しています。素人考えながら、堀江さんの証券取引法違反なんて、きちんとした会計士を雇っていれば回避できたことのような気がします。それなのに、大問題にされました。つまり、裁判所や検察の過剰なマスメディアに有利な告訴・裁判に思えてしまいます。裁判所も検察もマスメディアの見方なのでしょうか。もちろん、マスメディアに刃向かうメディアは公正に告訴・裁判してくれるようです。
鈴木政洋は、「社会を不安に与えること自体」は、法的な罪だとは考えません。道徳的な罪だと考えます。もちろん、脅迫されている本人に対しては法的な罪があると考えます。「その事件の話をマスメディアを通して知り不安になったこと」については、法的な罪はないと考えているのです。そして、鈴木政洋は「社会を不安に陥れる」という道徳上の罪を法律上の罪に転嫁することは民主主義に反することだと考えます。道徳上の罪を犯した者は道徳上の償いをするべきです。裁判で問題になるのは「犯人が被害者に行った法律上の罪」のはずです。
註1:徳島新聞 より引用
堀被告に懲役9年 徳島市連続爆破で地裁判決「社会不安あおった」 2009/4/9 10:29
徳島市内で昨年十月に発生した連続爆破事件で、爆発物取締罰則違反罪に問われた徳島市不動東町二、無職堀太●(たかあき)被告(36)の判決公判が八日、徳島地裁であった。畑山靖裁判長は「独り善がりな考えから、関係者らに恐怖や不安を与えることを目的に敢行した卑劣な犯行」と述べ、懲役九年(求刑同十二年)を言い渡した。
判決理由で畑山裁判長は「犯行は計画的で、一歩間違えれば人身に危害を及ぼしかねず、広く社会の恐怖や不安をあおった。同種の犯罪を防止する見地からも厳重な処罰が必要」と断じた。
弁護側は「人間としての弱さが起こした犯行。人に危害を加えたり、社会に不安を与えたりする意図はなかった」と主張していたが、畑山裁判長は「明白な意図的犯行で、心の弱さゆえに行われたというには無理がある」と指摘した。
判決によると、堀被告は昨年十月十三日午前一時二十四分ごろ、県日中友好協会(南内町一)出入り口ドアの取っ手部分の上に手製爆弾一個を置き、爆発させた。
さらに、同日午前四時二十八分ごろ、同様の手口で創価学会徳島文化会館の正面出入り口ドアで手製爆弾一個を爆発させた。
堀被告の弁護人の話 非常に重い判決。弁護側の主張が分かってもらえず、残念だ。
徳島地検の織田武士次席検事の話 検察官の主張がほぼ認められ、妥当な判決と考えている。
(注)●=「日」の下に「高」
H21.4.19
裁判官は、法の番人です。法律によって、法律違反した人を裁きます。決して、世論で裁くのではありません。裁判制度は、リンチ(私刑)を防ぐために作られました。同じ法律違反をしたら同じように罰せられるべきだからです。リンチを認めると、法律違反者は厳しい裁判官や被害者に会うと厳しい判決を受け、常識的な裁判官に会うと通常の判決になります。法律違反者は、裁判所によって刑が変わってしまうことになります。近代国家は、リンチを否定します。日本は裁判制度を近代国家から野蛮国家に戻そうとしています。いくら、口当たりのよい「庶民感覚を裁判所に入れる」というような言葉を使って「裁判員制度」を擁護しても、やろうとしていることは、近代化からの逆行です。文明国からの逆行です。裁判所に庶民感覚を入れることは間違っています。
国民が政治に参加し、政治に参加する中で法律を作ります。その法律を守っているか判定するのが裁判所です。間接的に、国民は裁判に関わればよいのです。直接、関わるのはリンチに繋がるので、良くないのです。
NHKでジャッジⅡ(註1)というドラマがありました。裁判官が政治家的な判断をする内容でした。江戸時代の三権分立が無かった時代の「遠山の金さん」的な時代ならともかく、近代国家である日本が、裁判官が政治家の役割を担うのは良くないです。裁判官が庶民感覚的な立場で政治家の役割を担っていました。この番組をそのように受け足らない人々の方が多いと思いますが、鈴木政洋には、そのように受け取れました。次のように番組を解釈しました。
殺人の実行犯は、森が仕組んだ罠に引っかかって、森が借金を支払うために稲村をだまして、沙耶が金銭要求をしているとでっち上げました。判決は、沙耶には何の罪もないので稲村の懲役12年。しかし、稲村にとっては、沙耶は恐喝犯に見えたはずです。稲村にとってどう見えたかで裁判が行われるはずです。なぜなら、裁判は、稲村がどれだけ法を犯していたかを判断する場だからです。けっして、被害者の復讐をする場ではないからです。鈴木政洋的には、主犯は森、実行犯の稲村は、主犯よりも罪が軽い必要があると考えます。
裁判所は加害者の立場で加害者を法に照らしてさばくことが仕事です。けして、被害者の立場で裁くものではありません。ましてや、被害者の復讐の場ではありません。裁判所を法治国家として機能させていかなくてはなりません。
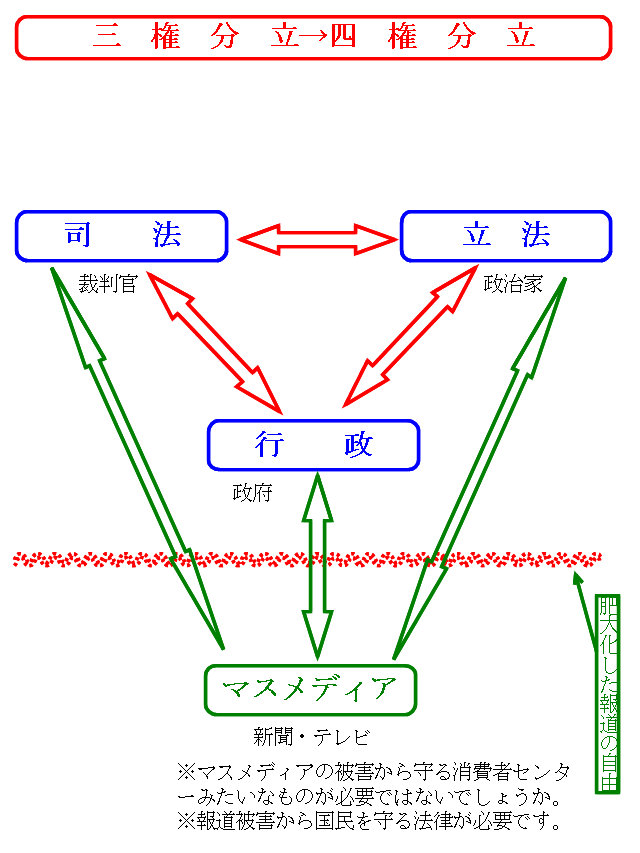
註1:NHK ジャッジⅡ【第2話】〔共犯〕
若い女性の殺人事件が起こる。
調書によれば、稲村(柄本佑)が被害者・沙耶(柳沢なな)に交際を迫って拒絶され、
そのいざこざの中で沙耶を負傷させてしまう。
沙耶は告訴しない見返りに金銭を要求、稲村はそれを支払ったにも関らず、沙耶が更に上乗せを要求したため、衝動的に殺害した、というものだった。
ところが稲村の態度に疑問を持った夏海が新たに引き出した供述から、友人・森(中村倫也)との共同正犯の疑いが持ちあがる。
H20.11.30
三浦和義の日本政府と最高裁判所が、米国のロサンゼルス郡上級裁の下僕であることを明確にした事件です。日本政府(福田政権)と日本最高裁判所は日本人を守らないと言うことがはっきりしました。「小泉政権、安倍政権、福田政権」は、愛国心が大切だと言ってきました。三浦和義が自殺(註1)するという結果に終わりました。日本がまともな法治国家ならば、日本の最高裁で無罪と判決されたのだから、三浦和義を何とか救出(註2)したはずです。救出の条件として、米国への再入国禁止くらいはしても良いかも知れません。本来は、条件は無いはずです。日本の最高裁の権威は、どうなったのでしょうか。日本は米国の植民地ではありません。このような米国の裁判所の特権が許されて良いわけがありません。愛国心があるのならば、このような米国を許してはいけません。
一方、マスメディアもロス疑惑の解明を望んでいるようですが、「日本の最高裁で決着したのだから、終わりにするべきです。真相を解明したいのならば、取材のみで解明するべきです。ロサンゼルス疑惑の裁判は終わったのです。こんな結果に終わって国辱です。三浦和義を守ることが重要なのでなく、日本の最高裁の判決を無視する米国を許さないことが重要なのです。違法な極東軍事裁判を憎むのと同じ理由です。日本の司法の敗北です。
註1:平成20年10月12日 読売新聞より引用
“主役”の自殺でロス疑惑に幕、「まさか…」捜査官も絶句
【ロサンゼルス=飯田達人】四半世紀もの間、社会の関心を集めた「ロス疑惑」が、主役の自殺という形で突然、幕を閉じた。
米自治領サイパン島で7か月にわたって拘束され、米ロサンゼルスに移送されたばかりだった元輸入雑貨会社社長、三浦和義容疑者(61)(日本で無罪確定)が10日夜(日本時間11日昼)、ロス市警の拘置施設で自らの命を絶った。この日午前に面会した日本総領事館の館員は衝撃を隠しきれず、今回の捜査を担当したロス郡検事局の捜査官も「まさかこんな展開になるとは」と絶句した。
「自殺するなんて全く信じられない」
この日午前10時すぎ、ロス市警の拘置施設内で、三浦元社長と面会した日本総領事館の出木場勝・領事部長はそう振り返った。
三浦元社長は同日午前5時ごろ、ロサンゼルス空港に到着し、ロス中心部のロス市警本部に移送された。同9時50分ごろ、拘置施設内から「領事と面会したい」と日本総領事館に電話をかけてきた。
出木場領事部長が面会室でガラス越しに対面すると、シャツにジーンズ姿の三浦元社長は、「長旅で体調は大丈夫か」という質問に「元気です」と答え、「私は食物アレルギーがあり、油で揚げたものは食べることができない」などと語ったという。
この時、三浦元社長は仮眠した後だったようで、出木場領事部長は「顔色が良く、話し方もしっかりしていた。自殺を聞いてまさかと思った」と語った。
27年前の一美さん銃撃事件で三浦元社長と一美さんが搬送された病院と、今回死亡が確認された病院は、同じだった。事件の発生当初から捜査にあたり、今年2月に三浦元社長がサイパンで拘束されたことを受け、ロス郡検事局に復帰したルイス・伊藤さん(77)は、「ミウラは自殺をするような男だとは思わなかった。サイパンを出る時は『ロスで戦う』と言っていたそうで、こちらも裁判で長い戦いになると覚悟していたのだが……」と絶句し、「法廷で真相を明らかにすることができなくなってしまい誠に残念」と語った。
三浦元社長の弁護を担当するマーク・ゲラゴス弁護士は滞在中のイタリアで、元社長の自殺を担当検事から知らされた。ゲラゴス弁護士はAP通信の電話取材に対し、「衝撃を受けた。担当弁護士の一人が昨日(10日)、元社長に12時間付き添っていたが、精神状態はよいように見えた。彼は、この事件を戦うのを楽しみにしていたのに」と話した。元社長の妻はロサンゼルスに向かうところで、到着後、同弁護士と面会する予定だったという。
註2:米国による日本人拉致事件とも言えます。三浦和義が疑惑事件を起こさなければなお良かったですが・・・。
H20.10.12
日本は、三浦和義のために三浦和義を救うのではなく、日本の主権のために三浦和義を救うべきです。そして、日本が法律や人権を大切にする国であることを海外に指し示す必要があります。
サイパン島の三浦和義元容疑者が殺人容疑が一事不再理で殺人容疑では無効。殺人の共謀容疑は、有効であるという判決(註1)は不当であると思います。ロサンゼルス郡上級裁主犯である殺人罪が無罪であるのにどうして、同じ殺人の共謀罪の審議を米国で続けるというのは筋が通りません。鈴木政洋的の個人的印象からすれば、三浦和義元容疑者の殺人については、非常に怪しく思えます。しかし、それは鈴木政洋の主観であって、日本の判決ではありません。日本の最高裁で無罪の判決が出たのに、米国の裁判所が、米国の正義を日本に押しつけてくるのは問題だと思います。つまり、日本の主権が侵害されていると言うことです。言い方を変えれば、米国が三浦和義を、米国の正義の論理で三浦和義という日本人を拉致したと言うことです。米国も法治国家らしく、日本に三浦和義の審判を任せたのだから、後から口に出すのはいけないのです。早速、米国は謝罪し拘留した賠償を行い釈放するべきです。
米国がこのような米国の正義の押しつけを行うと、大東亜戦争の原爆投下の論理「米国人を助けるためには日本の民間人を殺戮しても構わない。」を思い出させます。日本は、米国の奴隷ではないと言うことを言いたいです。勿論、中国の奴隷にもロシアの奴隷にも、どの国の奴隷にもなりたくありません。日本に対する主権侵害(註2)をひとつひとつつぶしていく必要があります。
註1:2008年9月27日07時29分 読売新聞 より引用
ロス疑惑逮捕状、殺人罪は無効・共謀罪は有効…郡上級裁決定
ロス疑惑
【ロサンゼルス=飯田達人】1981年11月のロス疑惑「一美さん銃撃事件」を巡り、米自治領サイパン島で拘置中の元輸入雑貨会社社長、三浦和義容疑者(61)(日本で無罪確定)が逮捕状の破棄を求めた訴訟の審問が26日午後(日本時間27日午前)、ロサンゼルス郡上級裁判所であった。
上級裁は逮捕状のうち殺人容疑は無効とする一方、殺人の共謀容疑は有効とする決定を出した。三浦元社長側は控訴するとみられるが、逮捕を認める司法判断が示されたことで、ロス郡検事局は元社長の身柄をロスに移し、本格捜査を進める方針だ。
ロス郡上級裁の審理では、日本の刑事裁判で殺人罪の共謀共同正犯に問われながら、無罪になった三浦元社長を米国で裁くことについて、同じ犯罪で再び罪に問うことを禁じた「一事不再理」に当たるかどうかが最大の争点となった。
カリフォルニア州では2004年9月の州刑法改正で外国での判決を一事不再理の適用から除外した。しかし、三浦元社長の無罪が日本で確定したのは法改正前の03年3月で、スティーブン・バンシックレン裁判官は、殺人罪については州刑法改正前に日本で裁かれているため一事不再理に当たると認定した。
ただ、サイパンで執行された逮捕状に共謀容疑が含まれている点については、日本の刑法の共謀共同正犯と、米国の共謀罪は異なると指摘。共謀罪は日本では裁かれていないことから一事不再理の規定に反しないと結論付けた。
註2:竹島の韓国による侵略、尖閣列島に対する中国人の上陸、ロシアによる北方領土侵略、中共の潜水艦とおもわれる領海侵犯、北朝鮮による拉致問題、米国による日本の経済政策に対する内政干渉、中共や韓国による日本の教科書政策に対する内政干渉など
H20.9.28
三浦和義を逮捕されたグアムからカリフォルニア州に移送することが問題となってます。グアムでは、米国の保護領です。一事不再理の原則があるはずです。なぜグアムで逮捕できるのでしょうか。グアムで一事不再理を破るカリフォルニア州の州法が有効であるとは思えません。米国の自治領であるからそう言う立場と言うことでしょうか。少なくとも、米国が法治国家を名乗る以上、一事不再理の原則に違反する行為は許されてはなりません。
福田首相に愛国心があるのならば、米国(カリフォルニア州)が日本の法律、国際法を尊重するために、三浦和義を救うべきです。選挙のために、法治国家足るべき日本を犠牲にすることはあってはならないことです。
そして、三浦和義のために三浦和義を救うのではなくて、
・日本が確固たる法治国家であることを世界に示すために三浦和義を救うのです。
・日本が人治国家(註1)ない国であることを示すために三浦和義を救うのです。
・東京裁判(註2)を二度と行わせないために三浦和義を救うのです。
・他国を尊重しないような野蛮なカリフォルニア州を放置しないために三浦和義を救うのです。
・カリフォルニア州(シュワルツェネッガー州知事)は日本政府を無視しても良いという先例を作らないために三浦和義を救うのです。
・日本が、法的な野蛮な行為に二度と会わないようにするために、三浦和義を救うのです。
平成15年3月 日本で三浦の無罪が確定しました
平成15年8月 シュワルツェネッガー氏(註3)カリフォルニア州知事に就任。
平成17年1月 カリフォルニア州法、外国人について一事不再理の原則を外しました。
鳩山法務大臣が米国の捜査協力をすれば、鳩山法務大臣が法律を知らないか、「あんな悪いやつを助けるなんて、ひどい人だ。」という世論を恐れ、「自分の政治生命を世論に奪われないために、法治国家としての誇りを捨て去る。」と言うことになります。鳩山法務大臣には、法治国家としての日本を守るために、三浦和義拉致事件の解決を望みます。法の不遡及の原則に反する「東京裁判」の二の舞は、ごめんです。こんなことを許せば、米国や中共などは、日本に無理難題をふっかけてくるきっかけを作ることになります。鳩山法務大臣は、将来の日本のために働いて欲しいと思います。
現在を含め、今後国際犯罪が増えてくることになると思います。従って、同じ犯罪で同一人物が各国で処罰されるというのもおかしな話です。ただし、一定以上の犯罪は、入国禁止などの罰則の整備が必要です。
註1:人治国家とは、権力者の意向が法令よりも優先する国のことです。
註2:東京裁判は、事後法によって日本人が罰せられました。事後法とは、ある人の行為を罰するために、行為の行われたときは合法であったのに、後で違法となる法律を作ってその人を罰する法律のことです。
註3:シュワルツェネッガーの父がオーストリアでナチス党員(突撃隊員)であったことが、平成17年の州法改正の遠因になっているかも知れません。
H20.2.9
カリフォルニア州法が平成17年1月に改正され、他国での判決は一事不再理の原則から外すことにしたそうです。しかし、日本で三浦の無罪が確定したのは平成15年3月であったので、「刑罰不遡及の原則」(註1)に反しています。従って、法治国家では、三浦和義を逮捕することは、米国であっても違法なことだと考えられます。この考えを推し進めていくと、米国合衆国による日本人拉致事件とも言えます。ただ、残念なのは三浦和義が清廉潔白な人間では無かったことです。しかし、法治国家としての日本、日本人の生命と財産を守ることが日本国の義務であると考えれば、どんなに、グレーな人であっても守られるべきです。その意味で、米国合衆国による日本人拉致事件と言えるかも知れません。
本件については、「三浦和義がやったに決まっている」という感情に押し流されることなく、法治国家としての原則を守って日本政府は対処して欲しいです。このようなことを放置しておくと、他国は、日本を馬鹿にして、無理難題やごり押しをしてくる可能性が高いです。例えば、中共産の餃子にメタミドホスが入っていたことを中共政府と人民警察が隠蔽する。例えば、北朝鮮が拉致事件は解決済みとして、一切進展させないし、拉致した日本人を暗殺してしまうとか。このようなことが起こる可能性も考えられます。この2つだけで、済むとはとても思えません。
註1:東京裁判のように、米国が法の不遡及の原則を無視しして日本を罰したことを思い出します。
H20.3.3
米国ロサンゼルス市警は平成20年2月23日、27年前のロス疑惑「 一美 ( かずみ ) さん銃撃事件」で殺人罪などに問われ、最高裁で無罪が確定した元輸入雑貨会社社長、三浦和義容疑者(60)を2月22日午後、渡航先の米自治領サイパン島で一美さん殺害の容疑で逮捕したと発表しました。
日本では、事件が終了しているのです。法治国家ならば、同じことで2回裁判を受けることはないはずです。それでないと、安心して暮らすことができません。どんなに怪しいと思っても感情で、2回罰してはいけないのです。一度、無罪判決の結審しても、いくら新しい証拠が見つかったと言っても、もう一度同じ事件で裁判を行ってはいけないのです。
本来ならば、日本で結審した段階で、米国でも捜査を終了しなくてはいけません。米国では、時効が成立していないと言っていますが、「時効とは」起訴されていない場合であって、起訴され裁判が行われた以上。時効ではなく事件が終了していると考えるべきです。日本で起訴することを米国が認めた以上、米国では、同じ事件で起訴してはいけないことになります。起訴してはいけないのですから、捜査もしてはいけないのです。
これを認めれば、日本の裁判は米国では無効と言うことになり、米国が友好国であるか疑問であることになります。米国の司法の方が日本よりも上位であることになります。それでは、米国が文明国であるか疑問を呈します。このような理不尽なことが行われれば、次のことを思い出します。米国は大東亜戦争中にアメリカ人となった日本人を強制収容所に入れました。米国の国籍を持っていたり、市民権を持っていたのにも関わらず収容所に入れられたのです。米国はドイツ人は強制収容所に入れませんでした。日本人に対する人種差別が行われたのです。まるで、米国人は、「野蛮な日本人の裁判なんて、米国人は認めないぞ。」と言っているように聞こえます。
もし、このようなことを米国人が強行すれば、次のようなことをすると言えばよいと思います。
この米国のやり方に従えば、例えば、沖縄の米国軍人が沖縄の少女を強姦したとします。その事件は、米国軍の軍事法廷で無罪になったとします。何年かして、日本で新しい証拠が見つかったとします。日本が沖縄の米国軍基地の門を出たとたん強姦した米国軍人を逮捕しても良いと言うことになります。この例に従って、日本で犯罪を起こした米国軍人を米国軍基地の門で逮捕すると言えばよいのです。そんな例、いくつも探し出すことができることでしょう。このように言えば、米国も反省するかも知れません
この件を曖昧にすることは許されません。日本が法治国家であり続けることの試金石です。この件を曖昧にすれば、日本が法治国家でないことを国際的に認めることになります。
なお、このようなことが可能だと二度と米国に言わせないために、国外犯に対する法の未整備(註1)の問題かもしれません。
註1:法律は専門ではないのでよく分かりませんが、日本で結審した事件について海外で再逮捕されるようなことが起こることが、日本で合法だと言うことになるのならば法あるいは米国との条約の未整備だと考えられます。法の整備を急がなくてはなりません。
H20.2.24
裁判員選ばれた場合、裁判に出席するために休みを取らないといけません。そのため会社に裁判員であることが知られます。一般の人も裁判の傍聴ができるので、裁判員がどんな判断をしたか分かってしまいます。それは、公にされることは無いと思いますが、裁判員の会社に漏れる可能性も否定できません。
まず、裁判員に任命されたために、その期間会社の仕事ができなくなってしまいます。裁判員として働いている間、その人の会社での役目を誰が果たすかという問題です。運が悪ければ、部署替えをされてしまうかも知れません。もっともらしい別の理由を考えてね。次に、裁判員が出した判断が、会社の上司と意見が違った場合、裁判員に不利益な人事上の扱いがされる可能性もあります。
そして、会社から不利益なことがもたらされても、不利益が持たされたという証拠がないと、裁判員制度に対する保証は得られないので、現実的には不利益な目(不利益な人事、転勤、出世が遅れる、配置転換など)にあっても保証されることは滅多にないのではないでしょうか。
次に、マスメディアの影響を受ける(裁判員のマスメディアなどの視聴に関する制限がない)ということが問題になります。次のようなことが考えられます。
・会社で話題になります。それを恐れてマスメディアの論調に沿った判決を出しやすいのです。
・マスメディアが直接裁判員を取材する可能性→法的に罰せられる(個人情報を含む場合)、個人情報が含まれなければよいことになっています。すると、マスメディアの記者がインタビューに来る可能性があります。そして、なあなあになる可能性がでてきます。
裁判員制度が日本の現状にあっているとはとても思えません。労働基準法が守られていない現状から考えると難しいことだと思います。
H19.5.14
東京に本社が移転するまでがんばった。無理矢理大阪本社の「りそな」の不良債権を負担させられた。まるで、大阪圏の問題は大阪圏で対処せよといいたげ。挙げ句の果てに、金融庁に不良債権の処理が悪いことを指摘され窮地に追い込まれた。最終的に東京に本社を置くことになり、三菱UFJフィナンシャル・グループとなった。その結果、東京都の外形標準課税の対象になり、もともと東京が本社の銀行は平等感を持ったことだろう。しかも、東京都の税金が増えるのだ。
UFJ銀行 - Wikipedia